この記事では、私がこれまで受験したITパスポートについて合格までの道のり紹介したいと思います。
1回目から4回目までの点数
まずはこれまでの点数を紹介します。
| 1回目(不合格) | 2回目(不合格) | 3回目(不合格) | 4回目(合格) | |
| 総合評価点 | 400点 | 415点 | 590点 | 665点 |
| ストラテジ系 | 385点 | 395点 | 550点 | 650点 |
| マネジメント系 | 400点 | 385点 | 715点 | 685点 |
| テクノロジ系 | 320点 | 345点 | 455点 | 600点 |
ITパスポートは誰でも取得することができる資格と言われていますが、みんながみんなそうではないと実感する結果となりました。簡単というのは、自分に合った勉強法を分かっている・コツコツと勉強を行うことが可能な方を指しており、私は大学卒業後からテキストや問題集を利用した勉強を長らく行わず、勉強をする癖がなかったため、簡単に合格という言葉を鵜呑みにして、資格試験を受けたのは間違いでした。
3回目の受験
2022年2月に2回目の試験にて不合格になり、3回目の試験を2022年3月の頭に申し込みましたが、再度不合格となりました。(点数は上部記載)
(2回目の不合格についての記事はこちら↓)
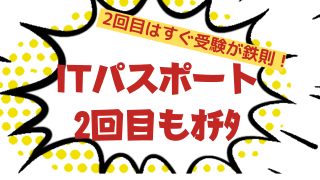
(1回目の不合格についての記事はこちら↓)

3回目の受験前に、2回目に落ちた記事にて「次で合格する必要がある」と記載しましたが、点数が足りず不合格。点数もあと少しという所だったため悔しかったのですが、不合格を確認した次の日に再度受験申込を行いました。2022年4月からのシラバス変更・受験料値上がりの影響のためか東京会場はほぼ満席でしたが、3月中旬に1枠空席を見つけることができ、急いで申し込みました。
4回目の受験
2022年3月中旬に4回目の受験をし、ようやく合格することができました。「簡単に・誰でも取得できる」という資格でありながら、かなりの時間が掛かりました。
勉強方法
ここからは合格した際の勉強方法について紹介したいと思います。
私が行った勉強方法
- テキストを読む
- 過去問を解く
基本的には以上のサイクルを行うことが合格への道のりですが、このような内容は多くの記事で書かれています。上記のサイクルを具体的にどのように行うかが合格・不合格への分かれ道だと思うので、どのように進めていたかを紹介します。
テキストを読む
使用したテキスト…いちばんやさしいITパスポート 絶対合格の教科書
ITパスポートがどのような内容かを把握するためにテキストを読みます。ここで大切なのは内容を理解し覚えようとするのではなく、ITパスポートとは何か・登場する用語はどのようなものがあるのかといった把握が目的です。最初は聞き慣れない用語や内容ばかりで、嫌気がさすかもしれません。わたしも初めてテキストを読んでいる時、わからない内容が多すぎて嫌になることが多々ありました。1回目で理解しようとしていたからだと思いますが、これは間違いです。特に日ごろから勉強をする癖がない方々はいきなり理解しようすることは不可能です。
テキストを読む=まずはITパスポートがどのようなものかを把握するために行うことと意識しましょう。
過去問を解く
使用した過去問…ITパスポート過去問道場
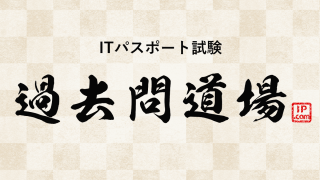
テキストを1周した後は過去問に取り掛かります。私はWEBサイトの過去問を利用しました。【ITパスポート 過去問】とネットで検索するとトップに出てきます。書籍を購入しなかった理由は、単に費用を掛けたくなかっただけです。
ここでポイントですが、過去問道場を利用する際は必ずユーザー登録を行いましょう。登録を行いログイン状態で問題を解くことで問題データが保存され、学習履歴機能を通して、正誤履歴・正答率・試験ごとの成績を保存することができます。登録は無料なので必ず行いましょう。
登録後、さっそく問題に取り掛かります。過去問道場では「試験回を指定して出題」、「分野を指定して出題」、「模擬試験形式で出題」と出題形式を選択することが可能です。私は「試験回を指定して出題」という形式を選択していました。
問題を解き進める中で、テキストを1周しただけではもちろんわからない問題も多いと思いますが、それが普通です。ここで重要なことが、1回目の過去問を解く目的は出題形式に慣れることであり、正解を多く出すことではありません。全く答えられない、自分はダメだと諦めるのではなく、「こんな感じで出題されるのか。ふーん。」ってくらいでいいのです。
そしてここでさらに重要なのが、解答の正誤に関わらず、すべての解説をしっかりと読み込むことです。過去問道場は問題を解くごとに正解・解説が表示されます。解説は飛ばさず必ず読んでください。また解説はその問題の答えの解説だけではなく、すべての選択肢の解説を読みましょう。全ての解説に目を通すことで1つの問いに対して、最大4つの知識を入れることが可能です(ITパスポートの試験は選択肢が4つあるため)。ここで全ての解説を読む・読まないによっても合格の分かれ道になると思うので、必ず読み込みましょう。
私は目で読むだけでなく、口に出して読みつつさらにノートに書いていました。書くといっても、解説を全て書き写すという行為は時間が掛かるので、要約程度に書いていました。正直ノートに書き写すのは好みの問題です。私は書きながらの方が覚えやすいので行っていましたが、読むことで十分な方は必要ないと思います。
試験1回分が終わり次第、「復習を開始」というボタンがあるのでそこをクリックし復習を始めます。この復習においても解説は必ず読みましょう。
復習が終わり次第もう一度同じ試験回を1から解き、100点を取ることができた場合、次の試験回を選択しまた同じように解いていきます。私は過去5回分の試験を解きました。
ここで注意すべきことがあります。数をこなしていくと、問題文を読んだだけでなんとなく正解はこれだなとわかっていくと思います。しかしそこでいきなり解答を選択するのではなく、4つある選択肢がどのような内容であるか1つ1つ確認しながら解いていきましょう。具体的にはこのような感じです。

【引用:ITパスポート試験ドットコム ITパスポート試験過去問道場】
まず問題文を読みます。そして4つの選択肢がどのような内容であるかを1つ1つ以下のように確認します。
ア:FAQとは、何回も繰り返し質問さえる項目とその質問への回答をまとめたもの
イ:SLAとは、サービス提供者とサービス利用者間でサービスの品目や品質に関して結ぶ契約
ウ:エスカレーションとは、サービスデスクで対応できない場合に、より優れた上位の組織・担当者に依頼して引き継ぐこと
エ:ワークアラウンドとは、インシデント発生時の応急処置的な回復策
ここで全ての選択肢を説明できなかった場合、私はその問いを不正解とカウントし、説明ができるようになるまで繰り返しました。
またユーザー登録することで、分野ごとの正答率も把握することができるので、ある程度過去問を試験回ごとに解いた後は分野別にも解答していきました。私の場合はテクノロジ系の正答率が著しく低かったので、試験2日前あたりはテクノロジ系を中心に問題を解いていました。
受験を終えて
4回目で合格することができたため、達成感というよりは正直今はやっと終わったという疲労感でいっぱいです。社会人になりテキストを利用した勉強をする機会が無かったため、勉強の進め方や癖をつけることにかなり苦労しました。勉強できない自分が簡単に合格するということがいかに無謀であったかを実感しています。私が取得すべき資格はITパスポートだけでなくまだ他にもたくさんあるため、今回の経験を活かしつつ、さらに自分に合う勉強法を見つけ、取得に向けて進んでいこうと思います。


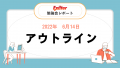
コメント