2022/2/25に行った勉強会「ハードウェア」についてのレポートと感想である。これからITに携わる人間として、知っておくべきIT基礎の一つとなる内容である。
ハードウェアとは
コンピュータはハードウェアとソフトウェアから成り立っている。ハードウェアとは、コンピュータ本体および周辺機器といった実体のあるものを指し、ハードウェア上で機能するプログラム等をソフトウェアという。コンピュータを操作し様々なプログラムを利用するにあたり、ハードウェアとソフトウェアはその土台となる部分である。
本体…コンピュータそのものであり、様々なパーツから構成されている部品の集合体
・CPU(Central process unit)
コンピュータの周辺機器やソフトウェアからの処理、制御等を行う装置であり、コンピュータの頭脳といえる。中央演算処理装置と日本語で訳され、その名の通り演算や記憶装置といった役割を果たす。MHz・GHzといった単位でCPUの性能の高さ、いわゆる頭の回転の速さを表しており、この数値が大きいほど処理能力が高くなる。
・メモリ(メインメモリ)
コピーした内容等を一時的に記憶する場所にあたる部分。記憶と言ってもコンピュータの電源を切った際それらの記憶は消えるため、一時的な記憶場所と言われている。
メモリとは机や作業台のような役割であり、メモリの容量が大きいというのは作業場所が大きいということである。容量が大きいことにより処理のスピードは速くなり、容量が少ない場合は記憶の置き場所が足りない・確保できない状態であり、コンピュータの動作が遅くなる。
・外部記憶装置
コンピュータ本体の記憶装置ではなく、USBメモリやHDDと言われる、コンピュータに接続し利用する外付けの記憶装置を指す。フォルダやファイル等の保管場所であり、メモリとは異なる記憶装置である。
・マザーボード(メインボード)
コンピュータの土台であり、CPUやメモリ、電源やUSBのコネクタといった様々な部品を構成するため必要な基盤となる板を指す。マザーボード自体はコンピュータの性能に大きく影響することはないが、すべての部品の土台にあたる部分であり、高性能なCPUやメモリを搭載するために基盤は頑丈である必要がある。
・拡張カード(グラフィックカード・サウンドカード)
映像を高画質に滑らかに映す・音質を上げるといった、コンピュータの機能を追加・増強するための電子基板。マザーボードにある拡張スロットと呼ばれるインターフェース(差し込み口)から差し込んで利用する。
・電源ユニット
コンピュータの電力供給装置。コンセントを接続し外部から電力を取り込み、マザーボードを介して様々なパーツに電気が送られることでコンピュータは機能する。
周辺機器…本体にケーブル等で接続して使用する機器
・ディスプレイ
文字や画像、映像を表示する機器。画面やモニタとも呼ぶ。現在は液晶のものが多い。
・キーボード
コンピュータの操作や文字入力に用いられる入力装置の一つ。
・マウス
コンピュータに用いられる入力装置の一つであり、カーソルによる方向や移動の指示、選択を行うことが可能。
・スピーカー
様々な音を電気信号から変換し、外部に出力する装置。
・プリンタ
コンピュータから文字や画像、図形等のデータを受け取り、紙に出力する装置。
・スキャナ
紙上の文字や画像、図形等をデジタルデータに変換する入力装置。
・モデム
コンピュータのデジタル信号と電話回線を相互に変換する機器。
・ルーター
コンピュータやスマートフォンといったデバイスをインターネットに接続する機器。
感想
これまでハードウェアが実体のあるものという理解はしていたが具体的にどのようなことを指すのかまでは理解していなかったと、今回の勉強会を通して感じた。しかし、内容に触れてみると、CPUやメモリといった聞いたことのある単語も多く出てきた。ただそれらがどのような機能・役割を果たしているのかという内容は知らなかったため、ITの知識はまだ乏しいと実感した。
個人的な話だが、私はノートパソコンを長年同じものを使い続けており、買い替えようと考えていたところだが、容量や性能といった部分でよくわからないと感じ、先延ばしにしていた。今回の勉強会の内容を参考にするとともに、これからITに携わる人間として、知っておくべきITの基本や知識を、これまで以上に吸収し身につける必要があると感じた。
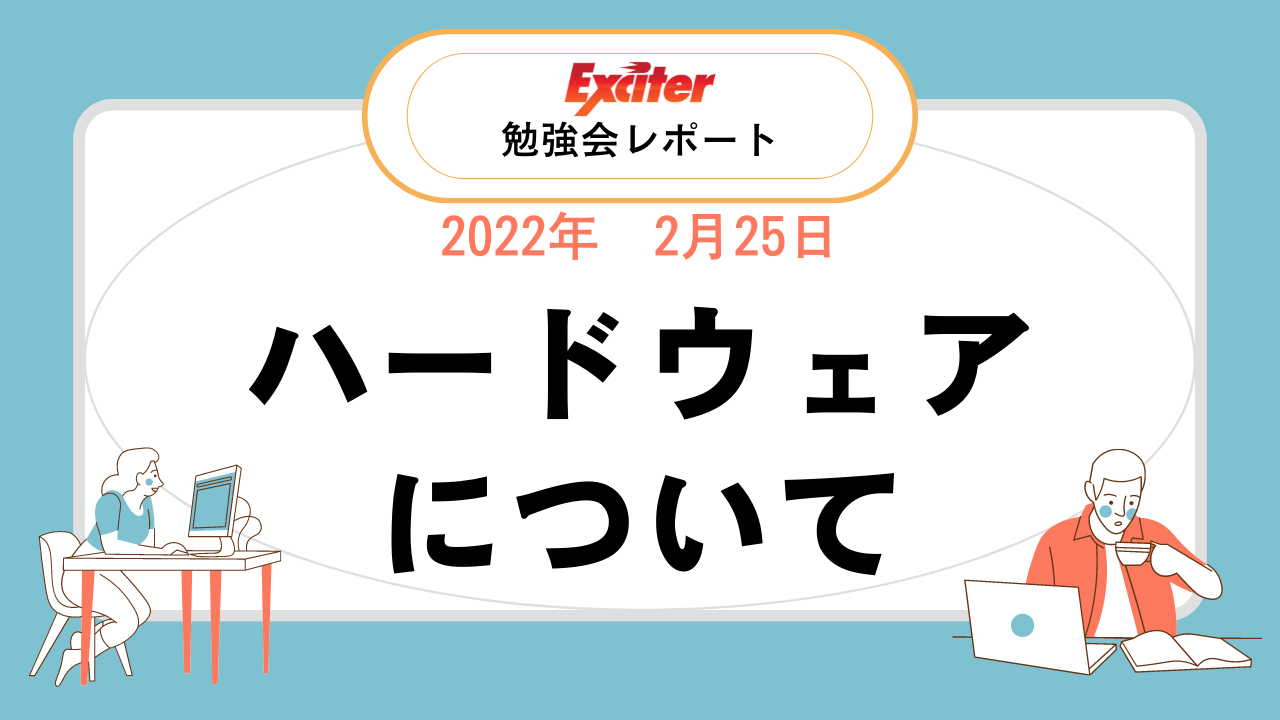
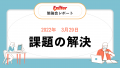

コメント