2022/1/7に行った勉強会「プラグマティズムについて」のレポートと感想である。
今回の勉強会では、一つの思考法として知るべきという提示であり、必ずしもすべての物事に対して適用すべきというものではない。実際の活用には時と場合の見極めが必要である。
プラグマティズムとは
プラグマティズムとは、実用主義・実際主義と言われる徹底した利益追求型の考え方である。
物事の概念、理論、思想体系を道具とし、それがどれほどの実用性があるのかで価値を図るとするもの。
言い換えると「道具というモノの価値は道具自身にあるのではなく、その使用の結果に現れる作業能力にある」ということ。
数人の哲学者が唱えたものであり、その中の一人であるジョン・デューイがプラグマティズムを掘り下げ発展させ、世に広めたと言われている。
プラグマティズムが支持されるようになった背景
プラグマティズムは1870年代のアメリカで生まれた。
1870年代のアメリカは第二次産業革命を迎えた時期。多くの人が工業というものをはじめ、お金を稼ぐということを始めたことで仕事に利益を追求し、より多くの利益を出すためには効率や実用性が図られるようになったからであると言われている。
しかし現代においてプラグマティズムという哲学は1870年代に比べると衰退してきている。それは、昔ほど「生きるために稼がなければならない」という時代でなくなってきたこと、人々の関心が「そのステージを乗り越えた上で、いかに幸せに生きるか」に移ったためではないかと思われる。
プラグマティズムと逆の考え方
役に立つか否かではなく物事の真理を追究するヨーロッパ的哲学は、プラグマティズムと真逆の考え方ということができる。
哲学とはすべての物事の根源であり、真理を追究することで根源を突き止め、それが結果として役立つというアプローチである。
プラグマティズムは価値をその実用によって測るという意味では非常に実践的かつ役立つものであるが、反面、即物的なものの見方となってしまうともいえる。
プラグマティズムの注意点
何かを学ぶときに役に立ちそうという考えを基準に学びを選択することは悪いことではない。
多くの学びがある今日において、自分にとって役に立ちそうな実用的なもの・すぐには役立たない実用的でないものというのが必ずあり、優先順位をつけるための基準としては正しい考え方である。
しかしここで注意すべき点がある。
役に立つ・立たないという判断をするには成熟した考え方が必要であるということ。
自分のような未熟な人間の場合、役に立つ・立たないを基準に判断が正しくできるほどの力量が備わっていないことを自覚する必要がある。
さらにもう一つ注意点があり、それはこの考え方は時と場合を選ぶものであるということ。
プラグマティズムを仕事の上で求めることはプラスになる考え方であるが、人生における学びには当てはめてはならない。人生における学びとは、行ったことないところに行く・会ったことない人に会ってみるなど未経験なことにチャレンジすることを指す。
ここにプラグマティズムのような実用主義を当てはめてしまった場合、人生における学びは役に立たないという判断をしてしまう可能性がある。
人生における学びは身につくまでに時間が掛かるものが多く、また仕事に役立つものばかりとは言えない。しかし、人生の学びは決して無駄なものではなく必要なものである。これを実用的であるかそうでないかで判断することは学びの幅を狭めることになりかねない。
仕事と人生の学びを混同することなく、正しい判断で学びの選択をする必要がある。
感想
今回の勉強会は思考法の一つとしてプラグマティズムという実用主義・実際主義について学んだ。
これまで様々なことを選択するとき、自然と実用的なものであるのか・役に立つものであるかを基準に判断していることが自分自身多くあったと思う。
確かにその判断が間違っていなかったこともあると思うが、実用性に縛られることで選択肢を自然と狭めていることに気づいていなかったとこの勉強会を通して思った。
考え方において未熟な思考しか持ち合わせていなかったことを自覚していなかったことに今まで自覚していなかった。
気づいていなかったこれまでに関して後悔をしても何も変わらないが、今回のように学ぶ機会が増えている今、正しい判断ができる人間になれるようにこれからも様々な考え方を学び、選択肢を自分の手で狭めないようにしていきたいと思う。
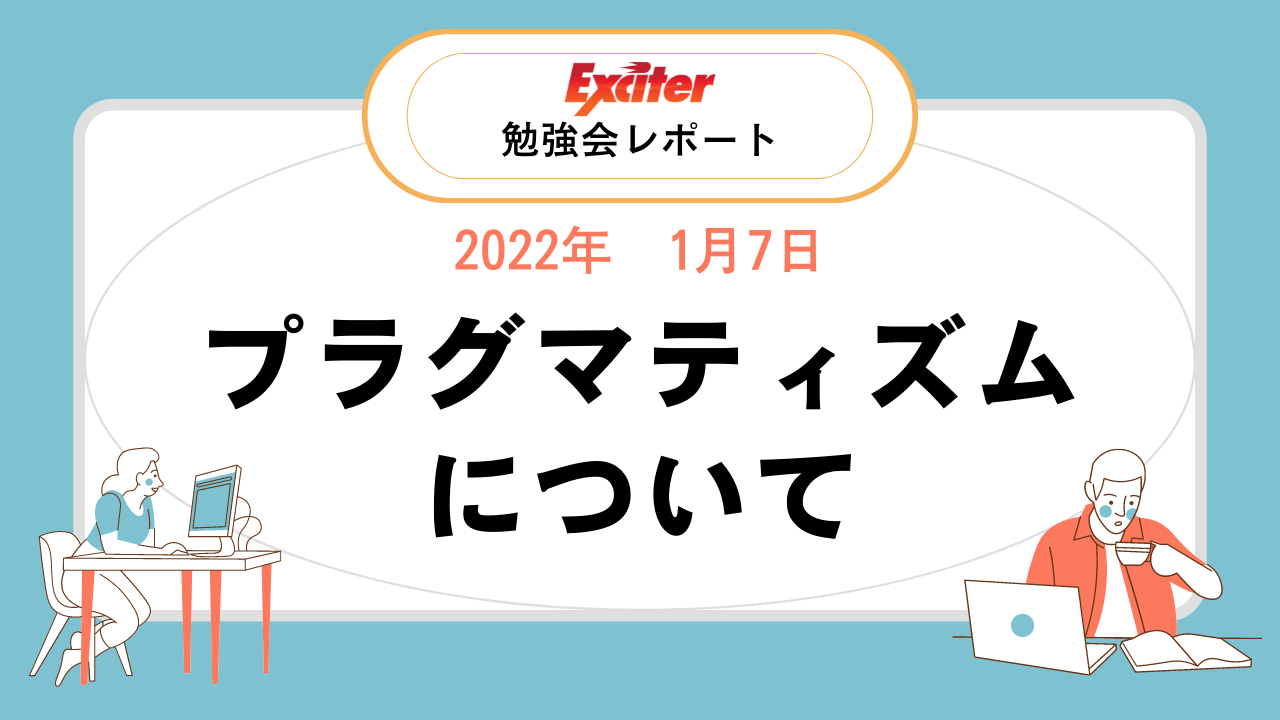
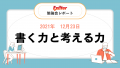

コメント