2022/2/1に行った勉強会「ITリテラシー」についてのレポートと感想である。ITリテラシーという言葉の意味、その概念を理解する目的で行われた勉強会である。
あらまし
ITリテラシーとは
ITに関しての理解をするための考えであり、ITLS(IT Literacy Standard)によって以下のように定義されている。
ポイント①正しく理解する
「正しく理解する」の主語は「社会におけるIT分野での事象や情報」だが、この社会とは、自分が働いている会社や仕事という狭義的なものではなく、社会全体を指しており、混同しないことが重要である。
ポイント②関係者とのコミュニケート
これはITリテラシーの目的の一つである。人は仕事をするとき、一人で進めるということはほとんどなく、特に若手の場合、一人でお金を生み出すことは不可能である。必ず関わりが存在する以上、コミュニケートは必要不可欠である。
ポイント③効率的・効果的に推進できるため
知識・技術は重要であるが、活用できなければそれらに価値は生まれない。そもそもの知識・技術を有効に活用することで、仕事を効率的・効果的に推進することができる。
上記それぞれのポイントについて、「ITに関するモノへの理解」、「適切に活用する力」、「必要な情報をピックアップする力」とまとめることができる。特に「必要な情報をピックアップする力」について、多くの情報が溢れる世の中で、正しく必要な情報をタイムリーに得られるとは限らない。そのため、必要かつ的確な情報を見極めることが重要であるということを表している。
ITリテラシーの意図
世の中にある種類・機能・仕組み・活用を理解する
ITリテラシーの中でも理解しやすい部分と言える。仕事やプライベートで利用しているITにはどのような種類・機能があるのか、そしてそれはどのような仕組みであるのか、それをどのように活用するのか(活用するしないや、活用できる範囲)、を理解する必要がある。
必要なITを選定・活用し、情報の取得・分析・表現を行い、解決に結びつける
選定…まずは選ぶことからはじまり、上記①に基づいて行う。
活用…ITとは道具に過ぎず、活用しなければ意味がない。
取得…情報を得ること。
分析…取得したものをそのまま鵜呑みにするのではなく、概論or各論、正or誤、等の視点で分析しなければならない。
表現…分析したものを資料化・プレゼン・口頭で伝える等の手段を通して、outputすることで価値が生まれる。
解決…ITを利用する最終的な目的になるもの。選定~表現のprocessは問題やテーマを解決するために必要な要素であり、そもそもの問題やテーマを解決するという目的がなければならない。
安全にITを活用するためのコンプライアンスやセキュリティ
ITは人畜無害な道具ではない。ITとは危険なものであるという認識を持つことが必要である。その上で、ITを必要性の高い便利なものとして活用するために、セキュリティやコンプライアンスの理解を深めることができる。
これらの意図はIT関係者であるか否かは全く関係なく、すべてのビジネスパーソンに要求される。その中でも我々のようなIT関係者は、他のビジネスパーソンよりも特段に要求されることを強く意識しなければならない。
知識領域
ITの動向を知る
常に最新情報を知る必要は無いが、過去の事実と現在の事実は時が進むことで変化することもあるため、全体的な流れを把握することが重要である。
ビジネスの改善と刷新
ここで言うビジネスとは商業を指し、商業は利益という価値と生産性を高める必要がある。そしてそれらを阻害するものは排除しなければならない。その概念に必要なものである。
リスク対応
ビジネスを行う上で、すべてが予定通りいくことは絶対にない。何かしらのトラブルにより計画やコストに影響が出る。そこで想定しうるリスクをあらかじめ考え、対策をしておくべきということである。
ITへの投資
ITは道具であるため経年劣化するのは当たり前であり、必要であれば新しいものに買い替えなければならない。新しいものに買い替えず、使い続けることによって、ビジネスの改善と刷新おとびリスクに対応できなくなってしまう。
種類
ITリテラシーは以下の3種類により構成されている。
基礎情報リテラシー
「正しい情報を見抜いて活用する」ということであり、以下の手順で行われる。
- 探す…必要なものを定めるため、何を・どこで・どのレベルまで探すのかということ
- 精査…探したものをさらに深く調べ検証し、情報を鵜呑みしないようにすること
- 活用…探す・精査という手順をしっかり踏むことにより活用につながる
コンピュータリテラシー
パソコン・プリンタのようなデバイスや、Word等のツールを操作して使いこなすということ。まずは操作ができなければ活用はおろか、探すこともできない。
ネットワークリテラシー
ネットを活用するためのスキルとモラル。
スキル…調べる対象に合わせた適切な検索手段・方法をとること
モラル…常識や倫理観を持ち、ITを利用すること
ITリテラシーが存在しないとどうなるのか
生産性の低下
ITを効率的・効果的に利用できなければ、高い生産性は得られない。また相対的に見ることで、他社がITの利用により自社よりも生産性が向上した場合、例え自社の生産性が向上したとしても、生産性が高いとは言えない。
コミュニケーションロス
連絡内容や緊急性によって連絡手段は変わってくるが、ITが活用できていない場合、適切な方法を取ることができない。ツールの種類・特徴を理解し活用できなければ、コミュニケーションロスにつながってしまう。
移行の停滞
ソフトウェア・ハードウェア・インフラは常に新しいものが生まれ続け、改善を繰り返している。知識領域の要素を知らない場合、新しいものに変える重要性を理解できないため滞ってしまう。
トラブルや情報漏洩が発生する
ITリテラシーがない人間はITの危険性を理解していないため、無用なトラブルを起こしやすい。例えばパスワードを付箋に書いてパソコンに貼っている人がいるが、これは情報漏洩につながりやすい原因である。取り扱いの重要性を理解しなければならない。
炎上とブランド毀損
炎上とはよく耳にする機会が多いが、SNSを通して日ごろの不満やストレスを理不尽に他人へぶつけることで起こる。世の中の風潮にそぐわない書き込み等が炎上し、その表面的な部分だけを見て、勘違いする人たちによりブランドイメージまでも悪くなる、いわゆるブランド毀損につながる。
言葉が凶器になることを理解し、表面部分だけで理解したつもりにならないという意識を持つべきである。
「できる人」への負荷
コンピュータを理解していない人間は、理解しようと努力をしない。そのような「できない人」のせいで「できる人」への負荷が大きくかかってしまう。ITの重要性を理解していれば、できる人」への負担は軽減されるが、「できない人」は永久的に役に立たない場合が多い。
市場や顧客への情報が得られない
ITリテラシーがないということは、情報を探す能力、精査の必要性、活用方法の重要性を理解していないということである。そのような状態では適切な市場や顧客の情報を得ることは不可能である。
ITリテラシーとは、低レベルかつ自分で考え理解できない人間のレベルに対して定義されていると言える。常識がある・モラルがある・自分で考えられる人間は上記のことを自然と行っているからである。
これらは知識や経験の基礎となる概念であり、我々IT関係者は特に意識すべきと言える。
感想
ITリテラシーという言葉は耳にしたことはあったが、このような要素や概念があるとは思っていなかった。しかし中身を見てみると、コンピュータやスマートフォン・SNSを利用するときに自然と行っているようなことばかりであると感じた。
また前職での経験もITリテラシーに活用されていたと思う。メディア側の人間として情報を発信するときも、探し方・精査・表現方法などから、情報の重要性と危険性について無意識に感じている部分はあったと思う。これからはITに直接かかわる人間として、前職で培ったものからさらに理解を深め、活用することで今後につながると感じた。
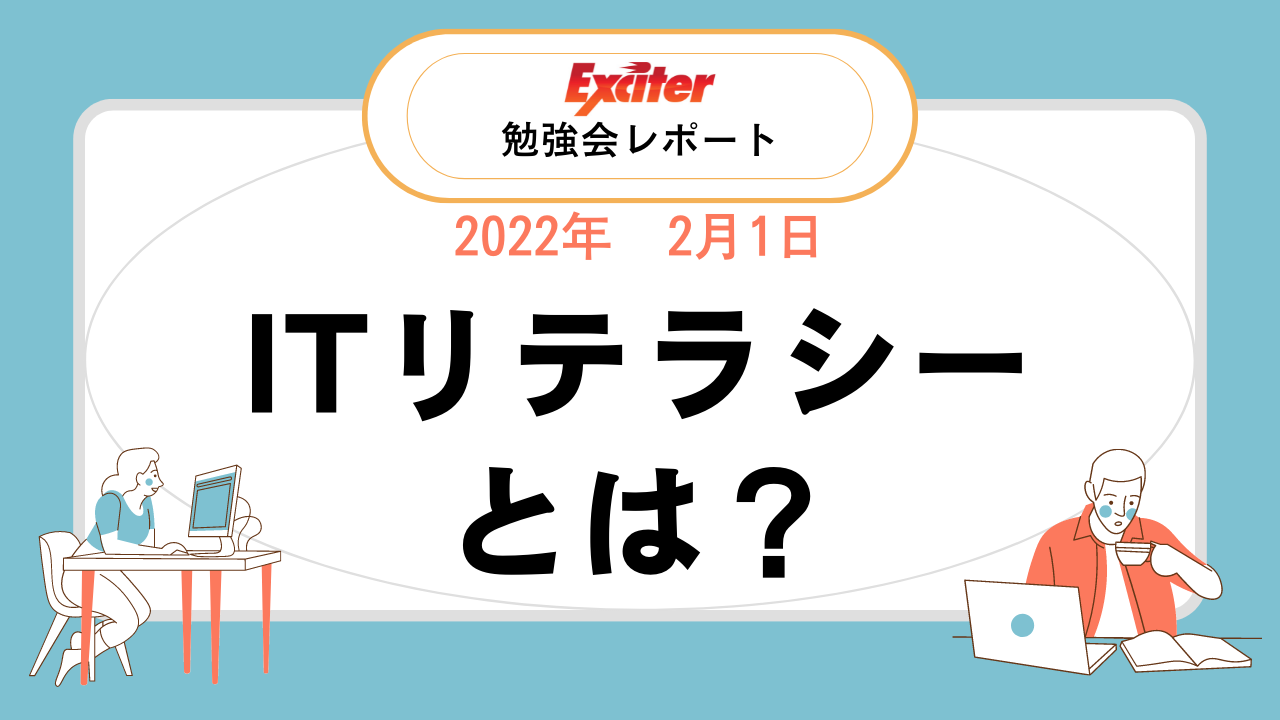

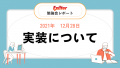
コメント