この記事はこちらの記事の続きです。
http://exciter.bz/staffblog/taichi_menkyo_gassyuku_gaiyou/
合宿生活について

ここからは僕が実際に送っていた合宿生活についてご紹介していきます。
合宿部屋
僕が泊まることになった部屋は1人部屋でした。
道路に面していて窓を開けると風通しは良く日当たりも良かったので過ごしやすかったです。
テレビ、冷蔵庫、クローゼットは完備されており、浴槽はユニットバスでしたが幅が広く取られていたので窮屈では無かったです。
入浴用品は常設では無かったので、ボディーソープやシャンプーなどは持参していきました。
食事
僕が申し込んだ教習所は3食付きの所で、自室ではなく食堂で食べるような形をとっていました。
昼食時には食堂に教習生が集まり賑やかでした。
食事は同じメニューをランダムに出す形をとっており、1週間ごとの献立表が食堂前に貼られ確認することができました。
合宿後半には食堂のメニューに飽きてきたので近くの飲食店に行って昼食を済ましていました。
その他設備
その他の設備については洗濯機と乾燥機があり、コインランドリーという形で別途お金が必要でしたが利用することができました。
それ以外にも喫煙所が設けられていたり、学習スペースが確保されていたりと充実していました。
服装
教習所へ行く際の服装については、これは合宿であっても通いであっても注意すべき点があります。
まずは男性から。
男性には特に服装の禁止事項はありませんが、強いて言えばタンクトップなどの過度に肌が露出しているものは避けた方がいいでしょう。
シートベルトに肌が触れる面が多くなり衛生面や摩擦などでのけが防止のため禁止されていることが多いです。
あとは厚底靴(スニーカーやブーツなど)やサンダルもオススメしません。
これらはアクセルやブレーキなどの操作がしづらくなり適切な運転が行えない可能性があるからです。
厚底靴は足裏の感覚が分かりづらく教習に向いていないとされています。
次に女性です。
一番好ましくないとされているのがロングスカートです。
これは単純に運転のしづらさも理由の一つですが、他にも運転する際に足元が見えなくなり、アクセルとブレーキの踏み間違いを起こす可能性があるからです。
運転に慣れていれば問題はなく、そもそも運転中に足元を見ることはわき見運転になるので危険行為ですが、教習中は低速走行をしながら車の機能について教習が行われます。
その際に足元が見えていないと教習がスムーズに進みません。スカート着用は避けるようにしましょう。
そして、男性の時と同じく、ヒールの高い靴や厚底靴、サンダルなどは教習には向いていないとされているので避けましょう。
技能と学科

ここからは教習所内で行う授業、学科教習と技能教習について触れていきます。
僕は合宿生だったので授業の日程は教習所に入る段階で既に決められており、初日に授業スケジュールが渡されました。
通い生の場合は受ける授業を自分で決めければならないのでその点、合宿生は楽でした。
学科教習
まずは学科教習から説明していきます。
これはいわば座学で、学校で行うような授業を受けていきます。
基本的な交通ルールや道路標識の種類と役割、免許証の種類などもここで学ぶことになります。
教科書を使って勉強していきました。
ちなみに技能にも教科書はありましたがほとんど使いませんでした。
学科に関しては教官の授業を聞いているだけなのでこれといって特に書くことは無いですが、教官によって教え方が様々で映像を流すだけの人もいれば、黒板にひたすら書いていく人もいるので受けていて楽しかったです。
教習所では授業に1段階、2段階と段階が設けられており、技能の場合1段階目は教習所内で、2段階目は路上に出ての授業になりますが学科はどちらの段階もすべて教室で行われました。
技能教習
次に技能教習の内容です。
これは実際に車を運転して車の機能やその扱い方について教官の方とマンツーマンで行う授業です。
授業は合宿初日から始まりますが、僕の場合は初めから運転するのではなく最初はシミュレーターを使って練習をしました。
シミュレーターとはゲームセンターにあるような機械のことで運転席が忠実に再現されています。
アクセルとブレーキの機能や扱い方、ミラーの場所とそれぞれの名称などを実際に自分で動かして確認しながら勉強していきます。
このシミュレーターでの授業を終えると、次からは実際の車を運転する授業が始まりました。
はじめは教習所内に設けられたコースをひたすらぐるぐると回るだけなのですが、いっぺんにたくさんの教習生がコースを回るので少し危ないような気もしました。
事故防止のために練習用の教習車には助手席にもブレーキが付いていて、教官が危険だと判断した場合こちらの意思に関係なく急ブレーキがかかります。
僕は踏まれることは無かったですが、僕が教習所で仲良くなった人は1日に5回ほど踏まれたらしく、教官から指摘を受けたそうです。
このブレーキですが、卒業検定と呼ばれる教習所での最終試験において踏まれると1発で不合格になってしまうので、普段からなるべく踏まれないようにすることが大切です。
路上教習
先ほど軽く説明した、技能教習の2段階目となる授業です。
いままでは教習所内をひたすら走っていましたが、ここからは実際に路上に出て教習を行います。
路上教習では、学科教習で学んだ交通ルールや道路標識に対しての知識を活かしながら走行していきます。
もちろん一般の道路なのでイレギュラーな事態、例えば救急車や消防車などといった緊急自動車が通ったり、細い路地から人が出てきたりなど教習所内では起こらないことも起こります。
しかし、これらに対しての対応は学科教習で必ず学ぶことなので、対応できるはずです。
僕の場合は救急車が後ろから来たり、歩道が狭いところを老人が歩いていたりして少し怖かったです。
教習所での試験
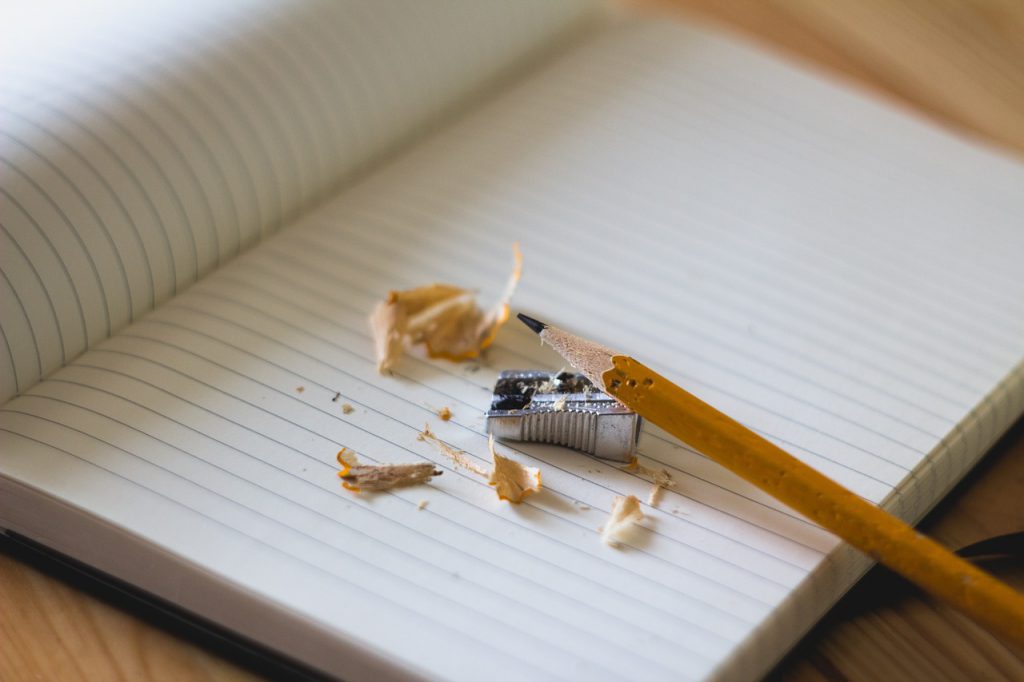
ここからは教習所で行う試験について触れていきます。
修了検定
先に教習所の授業は段階が分かれているというご説明をしましたが、この修了検定は1段階目から2段階目に切り替わるタイミングで行われます。
正しい運転技術が身についているかを見極める技能の試験で、これに合格しないとこの後紹介する仮免学科試験を受けることができず、2段階目に進むことができません。
仮免学科試験
前に紹介した修了検定の合格者のみが受験することができる学科の試験です。
試験時間は30分、50問の正誤式問題で、45問以上正解で合格となります。
ちなみに僕がこの試験を受けた時の全体の合格率は100%でした。
解答はマークシート形式で、選択肢が2つしかないので焦る必要は無いと思います。
これに合格すると、晴れて仮免許証が交付され授業も2段階目に突入します。
卒業前学科試験
この試験は実際に免許を取得する際に受けることになる本免試験の模擬テストのようなもので、学科の2段階目が終了する際に行います。
本免試験は全部で95問、合格基準は90点以上でこの試験も90点以上が好ましいとされているので、合格基準に近づけるように頑張りましょう。
所によってはこの試験に合格しないと次の卒業検定を受けることができない教習所もあるみたいですが、僕がいた教習所では合格不合格などの決まりは無かったです。
ただ、この試験で良い点を取っておけば本免試験を受ける際に少し余裕ができるので良い点を取っておいて損はないです。
卒業検定
いよいよ教習所で受ける最後の試験です。
この試験は技能の試験で、路上と教習所内の両方を使った試験になります。
修了検定も同じですが、試験が始まる時点で教習生は持ち点が100点あり、検定中ミスがあるとその都度点数が引かれていって、70点を下回った時点で不合格となります。
大きなミス(信号無視や速度超過などの危険な運転)をした場合は1発で不合格になることがあるので注意が必要です。
それ以外にも、修了検定と卒業検定は自分と教官以外に教習生を一人または二人乗せることになります。
卒業検定が終わり無事に合格していると、その日のうちに自宅へ帰ることができます。
卒業の際に、本免試験を受ける際に必要な書類と教習所までの交通費、そして初心者マークが支給されました。
本免試験

教習所を卒業した後はいよいよ本免試験です。
これは自分の住民票がある都道府県の免許センターで受けることになります。
試験時間は50分、問題数は95問で合格基準は90点以上。
問題の内容は、1問1点の正誤式問題が90問、1問2点のイラスト問題が5問です。
合格発表の際、試験を実施した教室内のモニターに合格者の受験番号が順番に表示されていくのですが、僕の受験番号は全体の中でも最後の方だったので発表されるまでに時間がありヒヤヒヤしました。
いざ発表されてみると僕の番号の前後の方たちは不合格になっていて、正直自分じゃなくて良かったと安心しました。
その後合格者のみで免許証用の写真を撮影し、しばらくしてからアナウンスがあり免許証を受け取りました。
本免試験自体、最低でも半日は掛かってしまうので時間に余裕のある日に受けることをおすすめします。
ただ早めに受けないとせっかく教習所で学んだことを忘れかねないので、できれば教習所を卒業した次の日に受けるなどが良いでしょう。
免許合宿に参加してみた感想

今回僕が合宿を選んだのは短い期間で早く取得したいからでした。
決められた期間の中で早く習得したい人とってこの方法はすごくおすすめです。
休息の時間もしっかりと確保されており、午後7時にはすべての授業が終了しそこからは自由時間でした。
次の日朝早くから授業が入っている場合は早めに寝て、試験が近づいて来たら対策のために勉強などをしていました。
外出することも可能で、合宿期間中にできた友達と外食や買い物に出るなどのことをしました。
門限は設定されていましたが、息抜きするには十分でした。
合宿の短所としては、スケジュールが決められているので自分のペースで授業を受けることができないことだと思います。
先にも少し書きましたが、朝早い授業だと午前7時から始まるものがありその時は大変でした。
しかしその場合、前日の授業が普段より早く終わるなどの対策がされていて余裕をもって準備をすることができたので助かりました。



コメント