とある地域で起こった「給食がまずい問題」という実例を元に、「考える力」を養うための勉強会を行った。勉強会の参加者が考えたことや感想を述べ、解説のポイントと自分の感想を述べる。
関連記事
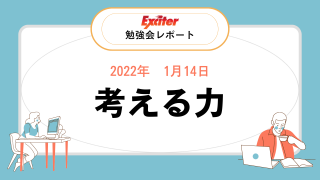
問題の概要
①とある地域の給食がまずい
②2017年の残食率が全国7%に対して、とある地域の残食率は大幅に上回り、25~55%に達した
考えられることと感想
勉強会参加者の、この問題に対する考え(なぜこのような問題が起きてしまったと考えられるか)と感想
(一人目)
考えたこと:
①児童の食が細い
②児童の好き嫌いが多い
③味がまずい
感想:
いまの子供たちはいつも美味しいものを食べているからではないのか。自分の頃は給食があまり残っているような印象は無かった。
(二人目)
考えたこと:
①食物の温度が適度ではない
②食物の匂いが良くない
③食物の見た目が悪い
④食事をする時間が短い
⑤献立が悪い
感想:
給食が苦痛だった経験はある。
(三人目)
考えたこと:
①給食の前に、早弁もしくは間食等の食事をしていたかもしれない
感想:
給食のメニューのバランスが良くないというイメージがある。
(四人目)
考えたこと:
①現代の子供たちは食事のカロリーを重視するかもしれない
感想:給食がそこまでまずいことがあるのか、ということにびっくりした
問題の追加情報
給食の導入は途中からで、以前は家庭から弁当を持参していた。
献立作りは栄養士が行い、健康のケアに配慮して塩分を控えめにした。
給食業者に委託する「デリバリー方式」で運び、またデリバリー方式では調理した給食は冷却した状態で運搬することが義務付けられていることから19度以下に冷却して運搬し、再加温せずそのまま提供している。
また、異物混入の件も多かった。地域の議会は業者側の責任だと考えていた。それについて、業者側は町と解約したが、反論していた。また給食業者側は異物混入も認めていなかった。その地域では代替業者を探していたが、大手3社と交渉したところ「(今回の騒動で)リスクが大きすぎる」とし断られたことが報告された。
結局、家庭から弁当を持参することに戻した。
解説のポイント
網羅性を追求する
この問題を考える中で、まず概要だけを聞いて出した各参加者の考えたことと感想が、実際の追加情報を把握する前と後では大きく変わることが分かった。前提条件の変化は、人の考え方や思考に影響を与えるため、初めの問題の概要だけではある程度の結論しか出せないかもしれないが、次の情報の段階では、状況の変化につれて、新たな結論も生まれることになる。現時点の情報だけでなく全体的な知識や情報を得た上で、答えをだすことを追求する、つまり、網羅性の追求が重要である。
フラットに考える、プロセスに当てはめる
各人の回答から分析すると、一人目の人は今の子どもたちはいつもおいしいものを食べていると感じているから、残食率の高さは子供の偏食だと思う。また、二人目のひとは給食が苦痛だった経験があるから、自分の頃は給食の匂い、見た目、温度など良くないイメージがあるため、とある地域の給食もそんな問題が存在していると思う。
二人とも自分の感覚から答えを出しており、つまり、自分の感情に思い込みがあり、主観的な考えになってしまった。
フラットに考えるには、例えばこの問題では、予算→献立→調理→運送→保管→配膳→給食という経路を立てることが必要で、この経路を全般的、全体的に把握し、各プロセスに考えられる問題の仮説を立てることができるようになる。
感想
情報の変化と共に、人の考えも常に変化していることに非常に共感している。情報が更に溢れている現世代では、情報の更新と知識の更新はITに携わる者にとって特段に求められる。しかし、現時点の情報を忘れないことと全体を把握した上で答えを出すことは非常に難しいと思っている。更に、自分の感覚に頼らず、客観的、フラットに考えることも非常に重要なポイントとして認識した。



コメント