このレポートでは、財務会計のあらまし②で学んだこと・感想をまとめる。
前回のおさらい
財務会計のあらまし①の勉強会の時は、会計を行う目的・仕訳とは・決算書とはという会計に関わる基礎概念や概要について学んだ。
また、貸借対照表や損益計算書についての概要も学んだ。
財務会計は、自身の企業で行われた日々の取引を正しく記録し、外部(取引先や融資先など)へ報告するため、税金を正しく支払うために行われる業務のことである。
また、日々の取引を正しく記録を行うことで、決算も正しく行うことができる。
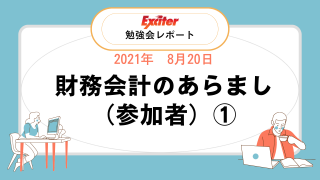
貸借対照表について
貸借対照表とは、会社の持ち物(現金・預金・商品など)を表す書類のことである。
取引の具体的な科目は、現金預金・棚卸資産・債権・債務・固定資産などがある。
| 現金預金 | 「お金」そのもの形で所持している持ち物。 |
| 棚卸資産 | 「形があるもの」という形で所持している持ち物。 |
| 債権 | 「他者から回収できる権利」という形で所持している持ち物。 |
| 債務 | 「他者へ支払う義務」という形で所持しているマイナスの持ち物。 |
| 固定資産 | 「車や建物など固定資産と分類される状態」という形で所持している持ち物。 |
上記の表は、あくまで一例であり記録対象はたくさんある。
この記録を日々正しく行わなければ決算書作成・外部への報告・税金を正しく納めることができなくなってしまうので、自分たちのためにも、他の企業のためにも注意して日々の記録を行わなければいけない。
損益計算書について
損益計算書とは、会社の成績表のような書類のことである。
主な記述内容は、売上・売上を生み出すための費用・会社が経営を続けていくための費用・本業と関係ない損益・突発的な損益などがある。
| 売上 | 販売・取引を行い得た利益のこと。 |
| 売上を生み出すための費用 | 企業が利益を得る為の準備で生まれる費用のこと。 |
| 会社が経営を続けていくための費用 | 会社運営のための費用のこと。 |
| 本業と関係ない損益 | 口座にかかる利子、手数料などのこと。 |
| 突発的な損益 | 自然災害などにより被害を受けた時に出る損失のこと。 |
上記の表は、あくまでも一例でこの他にも対象内容はある。
貸借対照表と同様に、損益計算書も、取引について、日々正しく記録していかなければいけない。
補助簿について
企業の経営には、主要簿(貸借対照表や損益計算書など)に記録がなくとも、取引についての詳細(誰が・いつ行った取引なのか、仕入れた商品の中にいくつ不良品があったのか)を記録しておく資料が必要である。
取引の詳細などを記録しておく資料は、補助簿という。補助簿の役割は、勘定科目だけでは、管理・記録しきれない部分を記録しておくことである。
この資料がなければ、取引において請求しなければいけない相手が誰なのか、いつどこで行われたのか、本当に正しい取引なのかを判断することができない。
補助簿は、企業にとっても重要な役割のある資料といえる。
業務の流れ
企業の決算は1年に1回行われている。
決算期は、社風や企業の方針によってそれぞれ異なっている。
また、決算期が他の企業とかぶってしまうと税理士に決算を手伝ってもらうことができなくなってしまう可能性があるということもあり期間をずらして決算を行う企業もある。
このような様々な要素があり、決算期は、企業によって自由に決めて良いということになっている。
企業は、決算期のみ決算の作業を行うのではなく、月に1度「月締め(プチ決算)」を行うことで、経営状況を把握したり、年度決算の負担を減らすことができる。
1年の間で決算を行うために、様々な手続きを行わなければいけない。
月に一度行う月締め(プチ決算)に加え、四半期ごとに行われる四半期締め、決算期で規定した1年が終了したら行う年度締めなどがある。
それぞれの締めで行う内容は異なる。企業の成績・状況をしっかりと把握するためにも決算はとても重要なものといえる。
感想
前回の財務会計のあらましの勉強会の時よりも、内容がより深くなっていた。
会計について、今までも勉強したことがあるので、勉強していた当時を思い出しながら話を聞くことができた。
貸借対照表・損益計算書と補助簿の関わりについて、決算を行う流れや、1年を通して行う作業がこれだけあるということを改めて学ぶことができて良かった。
企業にとって経営資源の1つであるお金は、一番記録を残す時にはミスをしてはいけないことであることをしっかりと意識しなければいけないということも再認識することができた。
今のうちから会計の知識をしっかりと身に付け、実際に仕事に取り組む時に、意識すべきところに注意して働きたいと思った。



コメント