はじめに
これはフィンランドの小学5年生が定めた10個の「議論」のルールである。
議論とは複数人で意見を交わすことであり、毎回何かしらの目的を達成するために行われる。何事も目的を意識して臨むべきであり、議論においては参加者も何らかの役割を担う。(だからこそ、参加する)
しかし、あくまで100%目的を達成できないから悪いというわけではなく、生産的であることが一番大切である。それぞれ自分の仕事で忙しい中で議論に参加しているため、ムダな時間となってしまわないよう自分の役割を認識したうえでしっかり果たす必要がある。
議論のための10のルール
1. 他人の話を遮らない
人の話を遮ってまで話すべきことは存在しない。尊重していない証でもあり、相手を不愉快にさせてしまう行為である。
2. だらだら話さない
要点をまとめ、ポイントを伝わりやすく話すことが大切。
極端な話、忙しい相手に対する敬意が見えないと捉えられてしまうため注意すること。
3. 怒ったり泣いたりしない
怒る・泣くといった行為は自分の感情のブレであり、その状態で論理的に話すことはできなくなってしまう。生産性の最大の妨げが「感情」であり、怒る・泣くは典型的な例である。
特に泣き落としは子供のように感情で押そうとしているだけであり、社会人がやってよいことではない。
4. 分からないときはすぐ質問する
分からないことを分からないままにしてしまうと、それ以降の内容は全てわからなくなってしまう。何でもかんでも質問し話の腰を折ってしまうことや時間をロスしてしまうことも良くないが、分からないまま時間を過ごしてしまうのはいけない。
5. 目を見て話を聞く
目は大事な情報源で、周りの人の目を見ながら話す内容を調整すべきである。また、相手を尊重しているという意思表示とも言える。しっかり聞いているという意思を示すためにも目を見て話す/聞くことは大切である。話し手も聞き手も同様。
6. 話を聞くときは他のことをしない
当たり前のように思えて意外とできてないと思う。メモを取ることに一生懸命になる人がいるが、議論はそもそもメモを取るために参加しているわけではない。メモを取るためには視線も手元に移ってしまうため、相手からしてもすごく気持ちのいいものとも言えないだろう。
議論の最中に他の作業をするなど、もってのほか。
7. 最後まで話を聞く
「他人の話を遮らない」の裏返しである。最後まで聞いた上でなければ結論が出ないテーマは多く、途中で遮ってしまっては浅い理解で止まってしまう。また脳もそれを更に深めようと働かない。
8. 議論が台無しになるようなことを言わない
それを言ったらおしまい、となることを言ってしまうと目的を果たせなくなり、生産的な議論にできない。また、論点をずらさないためにもそのような話は禁句である。
9. 間違いであると決めつけない
間違いと決めつけてしまうのは相手を尊重していない証拠である。決めつけられることで感情的になり、生産性の低下にもつながる。また0か100で捉えることも誤りであり、その中の良い部分をも間違いと切り捨ててしまうケースにも繋がる。
否定や批判はOutputへの評価であるが、そもそも決めつけは人間として礼儀を欠いた行動である。
10. 終わった話を蒸し返さない
議論が終わった後の話はムダであり、後ではなくその場で言うべきことである。後々いう事で今後のスケジュールにも影響が出てしまう。この影響の責任を持たされないようにするためにも議論の中で完結させるべきである。あとから言われたことを断るためにも能力・実績・信用が必要となる。
まとめ
この10個のルールを踏まえて、「生産性」と「他者への尊重」というワードがカギになると思った。自分や自分の意見が尊重されたいと思うのであれば、まず相手を尊重することから始めなくてはならない。これは議論というよりコミュニケーションの本質とも言えるのではないだろうか。
日本人は議論が苦手と言われており、それは意見が採用されないとき・批判されたときに自分自身を否定されたような感覚に陥るからである。それは場合によっては否定された側だけの問題ではなく、決めつけられる等礼儀を欠いた行動を受けてそのような感情に陥ってしまうのかもしれない。相手を尊重せずに目的を達成するには実力・権力・金が必要であり、一般的な人には持ち合わせていないものばかりである。つまり、自分が尊重されるためにも相手を尊重したコミュニケーションを用いて議論の役割を果たすことが重要だと思う。
そして、コミュニケーションのみではなく、そこに目的や生産性というエッセンスを追加したものが議論の本質に近しいものだと考える。ただ生産的に動けばいいわけではなく、相手の状況や立ち振る舞いを踏まえて挑まなくてはならない。


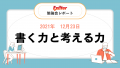
コメント