このレポートは8/4に実施した勉強会にて、設計書について教えた内容と感想をまとめたものです
はじめに
設計書を作る流れ(設計書とテストの関係性・重要性)
今後単体テストを行うにあたり、設計書が重要
設計書が間違っていると単体テストの際に問題に繋がってくる。
作成にあたってのポイント(端的に分かりやすいを心掛ける)
設計書は顧客に納品するものではあるが、顧客に対して説明するための資料ではなく、ベンダーが見ることもある。
そのため顧客向けに細かく書く必要まではないが、次段階のクエリ作成や単体テストに関わるものであるため、かなり重要な存在である。
オブジェクト関連図
ユーザグループ(SQ03)>インフォセット(SQ02)>クエリ(SQ01)の流れのおさらい
ユーザグループから作成し、インフォセット、クエリという順番であること。
※詳しくはクエリについての資料を参照するように指示
→そこから、クエリやインフォセットのシステムIDが分からない時の調べ方
インフォセット>クエリ>トランザクションコードという関係性より、インフォセットが分からない場合はトランザクションコードから逆算して考える。
結合の調べ方(SQ02)、外部結合と内部結合
インフォセット画面の結合ボタンより調べることが可能
結合には内部結合・外部結合とあり、クエリ上では外部結合の場合は「左外部結合」と記載がある。どこが結合しているかはテーブルのどの項目とどの項目が線で結ばれているかを確認。テーブルの左側のカギマークはキー項目と説明。
トランザクションコードの調べ方(SE93またはSE16→TSTCT)
「SE93」はトランザクションコードの定義を調べるトランザクションコード。
名前しか分からない場合でも調べることが可能。システムバリアントやクエリの情報を参照することができる
「TSTCT」はトランザクションコードを集めたテーブル。そのためSE16より参照可。
ZMM*のような形で検索できる。
システムバリアントとレイアウトの関係性
SQ01からの起動とトランザクションコード入力での起動の違いを説明
選択画面
選択画面とはどこを指すのか
クエリ選択画面のことを指す。
レイアウトをそのまま設計書excelに記載する。
項目定義欄の調べ方
SQ01の基本一覧よりそれぞれのデータ項目の一覧が表示される。
選択画面に表示された項目を1つずつテーブル名と項目名を記載する。
「◯◯-△△△」であれば◯◯がSAPテーブル名、ハイフン以降の△△△の部分が項目名となる。
データ項目名の右側には項目画面と設定画面のチェックボックスがあり、選択画面行のチェックボックスにチェックがついているものが選択画面に表示されるものである。
実行画面
実行画面のレイアウトの書き方
実際の設計書を見せ、実行画面と同じ順序でレイアウトを書いていく。
その際、「Ctrl+Y」を押すと、レコード全体ではなく、その項目に絞ってコピペをすることができるため、活用するようにアドバイス。
打ち間違いもあるため、基本コピペを推奨。
項目定義欄の調べ方、テキスト項目について
項目定義は選択画面と同様。
テキスト項目に関しては、SQ02のインフォセット画面よりテキストテーブルを参照することが可能。
SQ02上でデータ項目をダブルクリックするとテキスト項目という欄がある。
併せて左クリックのドラッグで(Ctrl+Cをせずとも自動で)コピーされる技を教えた。
勉強会の感想
復習用に一応パワポでの資料を作成しましたが、やはり実際にSAP画面をどのように動かしているかを見せるのが一番効果的だと思いました。
そういった面ではリモートで直接は見せられないものの、画面共有を活用できたのではないかと思います。
実際に自分達はSAPを立ち上げた際に、あの時の画面だ!と勉強会で見ていたものと結びついていてくれたら嬉しいなと思います。
ただ、今回クエリを履修済みの子とそうでない子と混ざっていたため、履修レベルがバラバラの人達相手に説明するのが難しかったです。
クエリの基礎的な知識(クエリとは?など)をもう少し序盤で盛り込んだ方がより全体的に分かりやすかっただろうなと後悔しています。
履修済みであってもずっとSAPを触っていないと忘れている部分も出てくると思うので、その辺りの配慮が足りず、今回一番の反省点だと感じております。
※CDSビュー/ドメイン/プログラムの追加項目 に関しては未説明です。
細かく説明しなくとも、このようなものがあると紹介しても良かったと思いましたが、混乱しないように一切触れておりません。
そのため、リモート解除後、設計書作成をさせる場合はそれらがない基礎的なものから依頼していこうかと考えております。
また後日勉強会第二回目を開催する予定です。
【総帥コメント】
初講師、お疲れさまでした。
ひとに教える側になることで、自分自身の理解が曖昧な部分がわかったと思うので、そのままにせず深堀りするように。
そもそも、今回のセッションでは、
「設計書ってどんなものなのか紹介します。例題はSAPクエリです」
「設計書の書き方を教えます。題材はSAPクエリです」
「SAPクエリの設計書を紹介します」
「SAPクエリの設計書の書き方を教えます」
上記どれなのかクリアになっていないことが問題だったのかなという印象。
そもそもの目的を明確にしつつ、講師をやるときは受講者の学びにならなければならないということを意識して進めるようにね。
ごく近い将来、後輩やPJの新規参入者に何かを教える機会が必ずあるから。


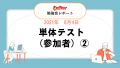
コメント