前回勉強会では、在庫購買管理では外部からの調達、また調達した在庫の管理だと学んだ。
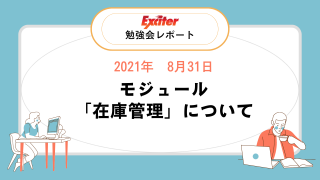
それを踏まえ、生産管理では主に何を管理しどういった役割があるかについて。また製造業の特性なども絡めつつ、業務理解の本質にも触れていく。
生産管理(Production Planning)とは
生産管理とは、いわゆるものづくりのための業務の管理を指し、調達した在庫を製造にまわす段階から製造を終えるまでのプロセスを含む。
しかし、ただ作ればよいわけではなく、売るタイミングや他の製造に部品として更に使われることもあるため、売り手としてお金を稼ぐためにも上手く生産の予定を立てる必要がある。
計画や所要(いつまでにいくつか…等必要な量を揃えること)、調達・受注を踏まえて製造フェーズに移る。
製造後は前述の通り、保管や在庫移動、販売や更に製造するといった工程が待ち構えている。
製造段階について
製造量や業種ごとに細かい作業は異なってくるものの、メインの作業は基本的に同じである。
業務を理解するためにもこのように共通する部分を洗い出し、本質の理解を第一に考えることが大切である。
原材料やレシピ、手順、設備など業界に関係なく物をつくる場合に必要なものと言えるだろう。
製造ではレシピ(部品表=BOM)があるため、材料の過不足が生じてはならない状態である。
そのため部品表を正確に作り、計画通り実行することが大切である。(BOM詳細はAppendixにて説明。)
予実(予定/実績)差異分析
自然の範疇に収まる差異なのか、それとも何か原因あっての異常値での差異なのか、など分析をし、対応する。
ここで原因が異常によるものなのかを見極めなければ一向にミスが解消されず、再発の恐れもあるため、しっかり原因分析を行うことが大切である。
一旦作って運用し、ブレが生じたところを補正し、クオリティを上げるというやり方もある。
⇒このシステムを成立させるには、マスタデータが過不足なく登録されていることが重要である。
つまり、マスタデータでシステムのクオリティが変わる場合もある。
製造業の特徴
製造業には大きく①組立系(例:自動車)②プロセス系(例:加熱や混練)と2つのグループに分かれている。
細かい作業工程はそれぞれ異なるが、ものづくりにおける基本的な考えは同じものである。
また、製造業では計画との差異が発生するケースが多いという特徴がある。
人の能率・効率などでバラつきが生じたり、機械によって不良が発生する場合があったり、季節や温度の差が生じてしまったり等、様々な要因が挙げられる。
しかし、そこで大事なことは、前述のとおりその差異が自然発生の範疇か、そうでないかの見極めとなる。
⇒対してITでは入力値と仕様に沿ってそのまま進むことが多い。
入力したものとシステムに反映されたものは同じにならないといけないため、そういった点が異なってくる。
IT業界における差異・ブレというものは存在してはならないものであり、テストフェーズで1つずつ対処されることから見かけない現象なのであろう。
これらのように製造を行う業務ほぼ全てに共通する事項を洗い出し、考えることが重要である。
業務への理解という観点からはまず共通する心理の理解を第一にし、その後細かいことへの理解を深めるという考え方が重要である。
これは製造業のみに言える話ではなく、他業種に関してもまず共通して行っている作業は何があるのかと考えてみてイメージを膨らませることが大切だ。
Appendix~BOM~
BOM=Bill of material(部品表)※マスタデータの一部
(以下の2つ以外にも設計や購買、保守などのフェーズで使うBOMが存在する。)
生産BOM
どのくらいの量がいるのか、どのくらい時間がかかるのかを計算するためにデータをまとめたものである。
その商品を作るために何の材料が必要か?どれくらいの量必要か?重さは?かかる時間は?在庫にあるものか発注しないといけないものなのか?更に加工されたものを材料として使う場合はその加工にどのくらいの時間・ものが必要か…というようにまとめていく。
こうして挙げるだけでも、1つの商品を作るために考えるべき項目というものが非常に多いことが分かる。
すなわち、人間の脳内で全て整理するのはとても難しく、計算もシステムに頼るようになっていったのであろう。
ではそのシステムは何に頼って動いているかというと部品表のようなマスタデータである。
データを過不足なく、正確に登録することがとても大切であり、かつ難しいとも言える。
この部分で誤りが発生してしまうと、原料や製品の在庫が出てしまったり、反対に不足してしまうという事態に陥ったりしてしまうことも考えられる。
しかし、正しく登録できていれば部品の不足、いつ頃材料の発注をすべきかをシステム上で計算してくれるため、企業側としてはなくてはならない存在であろう。
販売BOM
販売に関わるBOMをいい、例えば飲食店のラーメンセットは醤油ラーメンと半チャーハンがある。
※「セット売り」と「まとめ買いでのプレゼント・割引」は値段の考え方が別であるため、異なる。
後者は売れ残ると評価替えや処分の廃棄費用を検討したうえでプレゼントや割引という形で在庫を減らす方が得策という考え方。
まとめ
生産は人間の脳だけで全てを管理するのは至難の業であり、システムを活用できるか否かにより大きく効率面などで変化があるだろう。
システムはこちらの意図を読み取って動くものではないため、システムに入力するデータが正しいか正しくないかでも大きく差が生じてしまう。
またそこからマスタデータも重要といえる。
業務視点で考えると、購買・在庫・生産・販売と一連の流れが出来上がっているのが分かる。
同じようにモジュールを当てはめるとSAP上でも、MM・PP・SDの繋がりが少しずつ見えてくる。
その中でも生産管理は特に、在庫購買管理・販売管理どちらにも密接に関わっていることも含めて難しいとされるのではないかと思う。
物を作ることは仕入れや販売に関連することから、生産の段階で予定や計画に狂いが生じてしまうと大きく後工程に響くのだろう。
更に、生産計画で部品数などの予定が狂っていた場合には調達の段階で多く仕入れてしまうことや、処分せざるをえない数が増えることも考えられる。
ロジの世界でもこのような関連性があり、そして更に会計領域とのつながりも今後考えてくる必要があると考える。
最初はSAPの領域として捉えていたが、業務の観点からの講義であり、SAPに限らず考えられることだと自分の認識の違いにも気が付いた。
SAPという概念を一旦抜きにしても、自分の生活と絡めながら想像できる部分も多く、そういったイメージのトレーニングというのも今後の課題として取り組みたいと思う。

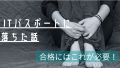
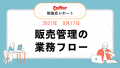
コメント