2022/01/14に行った勉強会「考える力」についてのレポートである。
「考える力」とはインプットから価値を生み出し、良質なアウトプットを生み出すために必要な基礎力の一つである。
考える力とは
考える力とはインプットから価値を生み出し、良質なアウトプットを生み出すために行われるプロセスにおいて必要な力の事である。
仕事においては、アウトプット(話す力や、書く力)で評価されることが多いが、全てアウトプットだけで評価される訳ではなく、前段階のプロセスも評価される。
プロセスをどう行うかによってアウトプットの質が変わるため、プロセスである考える力は大切である。
「考える」必要性
◎アウトプットのクオリティと、スピードを上げるため
頭脳労働者は、労働の全てが形になるわけではなく、ゴールまでどれくらい近づいているかがわかりづらい。だからこそ、他人の目からも見て分かるアウトプットのクオリティと、スピードを上げる事が必要であり、そのためには考えるべきである。
◎直感や経験に頼らないため
直感や経験という武器に頼るべきではないという事ではなく、これらだけを頼りにするべきではないという事である。
直感は、感覚的に感じたままを捉えたもので、相手から納得を得る力は充分でない。一方、経験は相手を納得させることができるが、経験に頼っていては経験ベースでしか判断できなく、未経験で不安を抱いていることに対しては何の太刀打ちもできないのである。
そもそもITの仕事は未経験の連続であるため、今までの経験や直感だけを頼りにしていては仕事にならない。
◎悩まないようにするため
悩むとは、へたりこんでいるだけでありゴールに向かって前進していない。或いは、ゴールがどこかも分かっていない状態である。一方、考えるとはゴールが定まっていて、そのゴールに向かって前進している状態。人は行き詰るとそれらを混同してしまうため、悩む事と考える事を切り離す必要がある。
頭脳労働者の仕事は特に、「考える」プロセスが形に残らず、目に見えにくいため、ゴールに向けてどのくらい進んでいるのかが見えにくいものである。しかし、ただへたり込んでいる状態ではそもそもゴールに向けて一歩も進まず、すなわち何もやっていないことと同じ事である。
考える必要性は上記で述べた通りである。では「考える」とはどういう事なのだろうか。
考える上で大切なポイント
「考える」の基礎・思考法・フレームワークが「考える」上で大切なポイントである。
「考える」の基礎とは、「考える」の概念であり、土台になる部分の事。思考法とは、考えるガイドラインや、コンセプトの事。フレームワークとは、考えるための道具の事である。
思考法・フレームワークに関しては即物的であるため、すぐに役立つ。とはいえ、「考える」の基礎の土台がしっかりしていないところに、思考法・フレームワークは機能しない。
だからこそ、最初に考える上で土台となり、おろそかにしてはならない「考える」の基礎について理解する必要がある。
「考える」の基礎
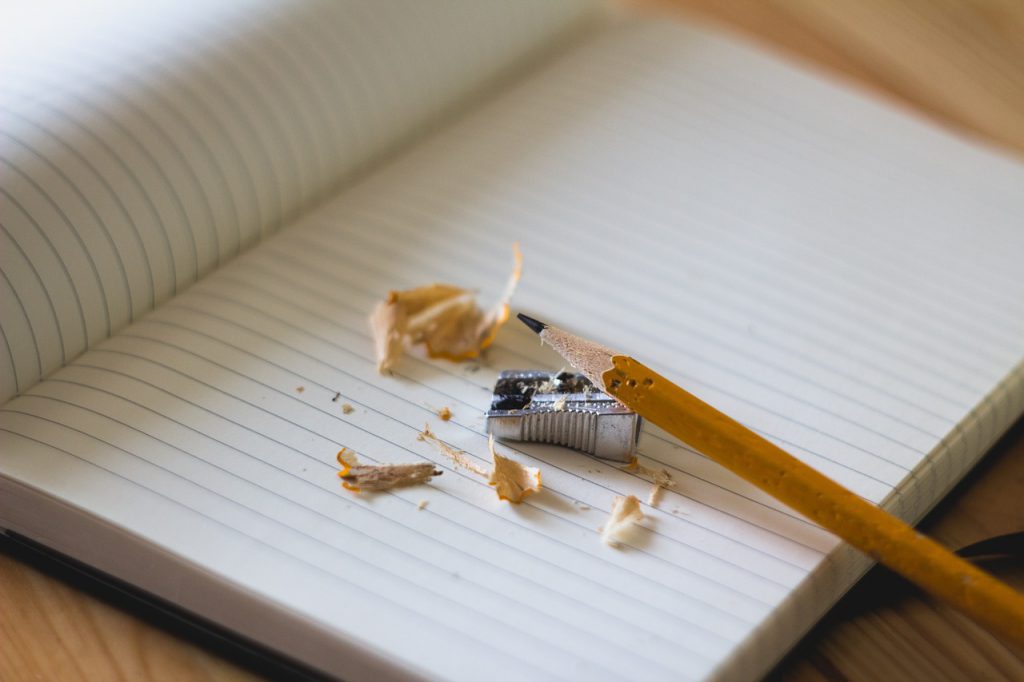
- 論理的に考える
- 概念の形成
- 要素分解
- 優先度と重要度を切り離す
論理的に考える
合理的・体系的・理性的であることを論理的であるという。合理的とは非効率がない事であり、体系的とは秩序立っている事であり、理性的とはものの道理に従っている事である。
論理的であるためには、どのような考え方が必要であるかを述べる。
論理的な考え方
◎問いと答えをセットで考える
物事には、必ず各問いに対して各答えがあり、それらをセットで考える必要がある。それが「なぜ」のように問いだけしか考えていない事や、「誰かがこう言った」のように答えだけを受け止めているのは論理的に考えているとは言えない。
◎主張と根拠をセットで考える
主張は、根拠に基づいている。根拠があるから、そこから導きだされる主張がある。それが、ただ「こうだ」のように、それを裏付ける根拠がない主張をする事や、「多分こうだろう」のように、根拠から主張をしない事は論理的とは言わない。
そもそも、何らかの主張(提案)をしてもらうために顧客はシステム屋に業務分析などを依頼する訳であって、そこで根拠がない主張をする事や、明言をしない事は主張と根拠をセットで考えられておらず、顧客に納得してもらえるはずがない。
◎目的を明確にする
考えるとはそもそも目的を達成するための行為であって、目的が定まっていない場合、どこに向かって考えれば良いのか分からない。だから、ゴールを明確に定める、あるいは暫定的なゴールを決め、そのゴールに到着した後、或いは近づいた時に新たなゴールを定める必要がある。こうすることで、自分が課した目的を達成する事ができる。
論理的に考える事は、物事を考えるという行為全般で必要ではあるが、特に問題解決や改善、リスクへの備えが必要とされる仕事においては大切であり、それらを達成するためには以上で述べた事が1つも欠けることなくできていなければならない。
論理的な考え方は述べたものの、実際にどのように考えるかは分かりにくいため、実践的な方法を述べる。
論理的な考え方を導きだす方法
◎答えをだす問いは何か、ゴールを定める
何のために考えるかを明確にしないと、どのようにゴールに向かえばいいのか明確にならない。
◎問いに対して、どう答えを出すかを考える
各問いに対して、各答えがあるため、その問いに対してどのような答えが出るかを考える事は大切である。
◎なぜその答えになるか考える
答えをどのように出したか検証する。そこには、根拠があるはずである。
上記3つを、1回1回丁寧に反復することで、自分にとってベストなやり方を見つけ出す事ができる。そして、その見つけ出したベストなやり方を自分に定着させる必要がある。
上記の実践方法は、いかに問題を認識するか、という所が起点となっているが、その問いはそもそもどのように見つけるか、実践的な方法について述べる。
問いを見つける方法
◎なぜ?と考える癖をつける
仕事のみならず生活のなかでも様々な事に興味を持ち、疑問を持つ癖をつける。その疑問こそが、問いになる。
◎理想と現実を考える
現実が理想通りであることは大抵ない。その時に、「理想通りにいかなかった原因は何であったのか」を考える。その「何で」の部分こそが、問いになる。
◎固定観念と貧乏マインドを捨てる
固定観念を持っていると、そこから「なぜ」という疑問が生まれる事はない。貧乏マインドを持っていると、健康的な思考ができず、頭の中が他のことでいっぱいになってしまい、目の前にある問いにも気が付く事ができない。
上記のように、問いは自ら見つけに行く姿勢が大事である。待っていれば、誰かが問いを差し出してくれるという事はない。
概念の形成
複数の物事から、共通要素を見出すことである。概念を適切に形成する事で、物事の本質を導きだす事ができる。
概念の形成は仕事を効率化するために特に必要である。例えば、新商品を作る際など既にある商品との共通要素を見出す事が出来ていれば、それを参考にする事が可能であり、いちいち始めから商品開発するという手間を省く事ができる。
次に述べる要素分解を行う際には、切り口を見つけ出すために概念を形成する必要がある。
要素分解
ごちゃ混ぜになっている要素を分解する事を要素分解という。
要素分解を行う手順について述べていく。
最初に、事実を認識する。要素分解をするにあたり、まずは覆ることのない、事実をベースにして考える必要がある。「ああ思う」、「こう思う」といった主観的な感情は、何の根拠も持たないため、そこから要素分解を行うべきではない。
2番目に、論理を考える。合理的・体系的・理性的に考える。論理は客観性を持っているため、覆ることのない事実の次に考えるべきである。
(論理に関しては、当レポート「論理的に考える」を参照の事)
3番目に、感情を考慮する。事実・論理という客観性を持った考えをした後に、主観的である感情を考慮するべきである。そもそも人間は、感情の生き物であるため、感情を排除し物事を考える事は不可能である。とはいえ、主観に基づいて考えた事には根拠がないため、客観的に考えた後に感情を考慮する必要がある。
最後に、結論を導きだす。事実・論理・感情の順を得て、結論を導きだす。
上記のように要素分解は正確性が高いものから順番に、1つ1つの手順を切り離し、考えていく必要がある。
要素分解を行う事で初めて、物事の本質に辿りつく事ができる。逆に、要素分解を行わないで物事を捉える事は、物事の表面にすぎず問題解決や改善、リスクに備えることができない。
優先度と重要度を切り離す
優先度とは、何を優先させるかを表したもの。重要度とは、どれくらい重要であるかを表したもの。優先度と重要度をそれぞれ客観的に評価し、その合計点によってどのように取り組むべきかを考える必要がある。
若手のうちは、優先度と重要度が混同しやすいため、仕事の時には意識的にそれらを切り離して考えて、客観的な評価を行ってから作業に取り組む必要がある。また、管理者と作業者の間で、優先度と重要度の認識が異なる場合もあるため、自らで勝手に判断するのではなく、確認する必要もある。
まとめ
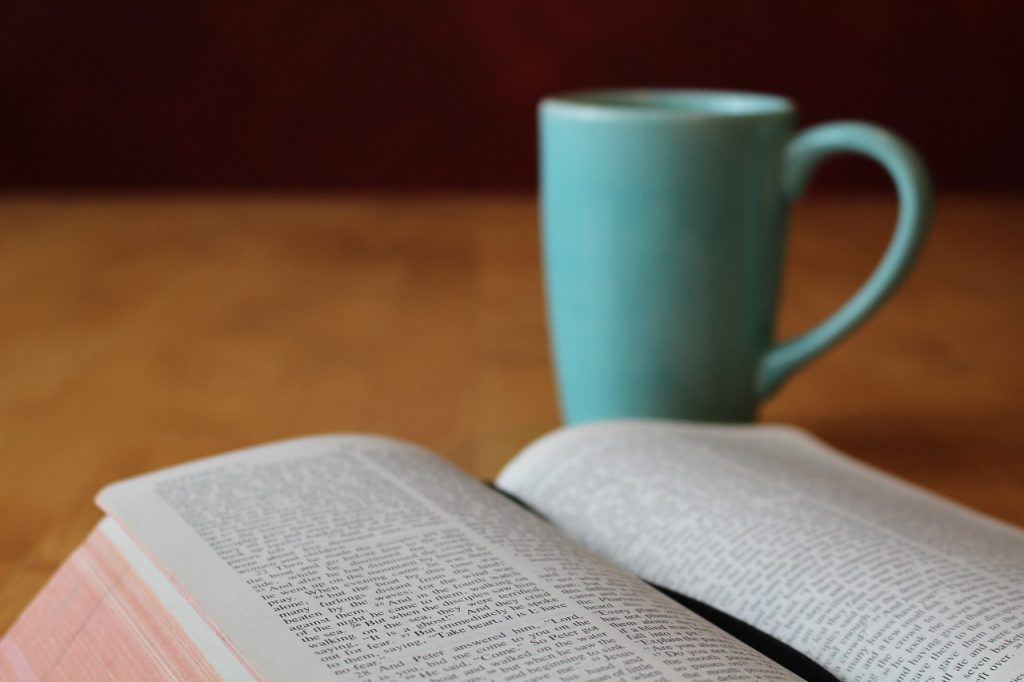
考えるとは、インプットから価値を生み出し、良質なアウトプットをするためのプロセスである。考える土台になるのは、「考える」基礎であり、それをまずは身に付ける必要がある。
「考える」基礎を理解し、実践し、そのフィードバックを受けながら自分のベストなやり方で考えていく必要がある。
感想
「考える」というのは、ゴールに向かって前進している状態である。私はよく考えろといわれた時に、ゴールが定まってないのに、漠然と考えているつもりになりながら、スタートの周りをぐるぐると回っていた。それは、考えるという事ではなく悩んでいる、或いは迷っているという事であり何も行っていないと同然のことである。
頭脳労働者は、「考える」ことに責任を負っていて、その責任の対価として給料が発生している。だから、私は「考える」ことに責任を果たさなければいけない。
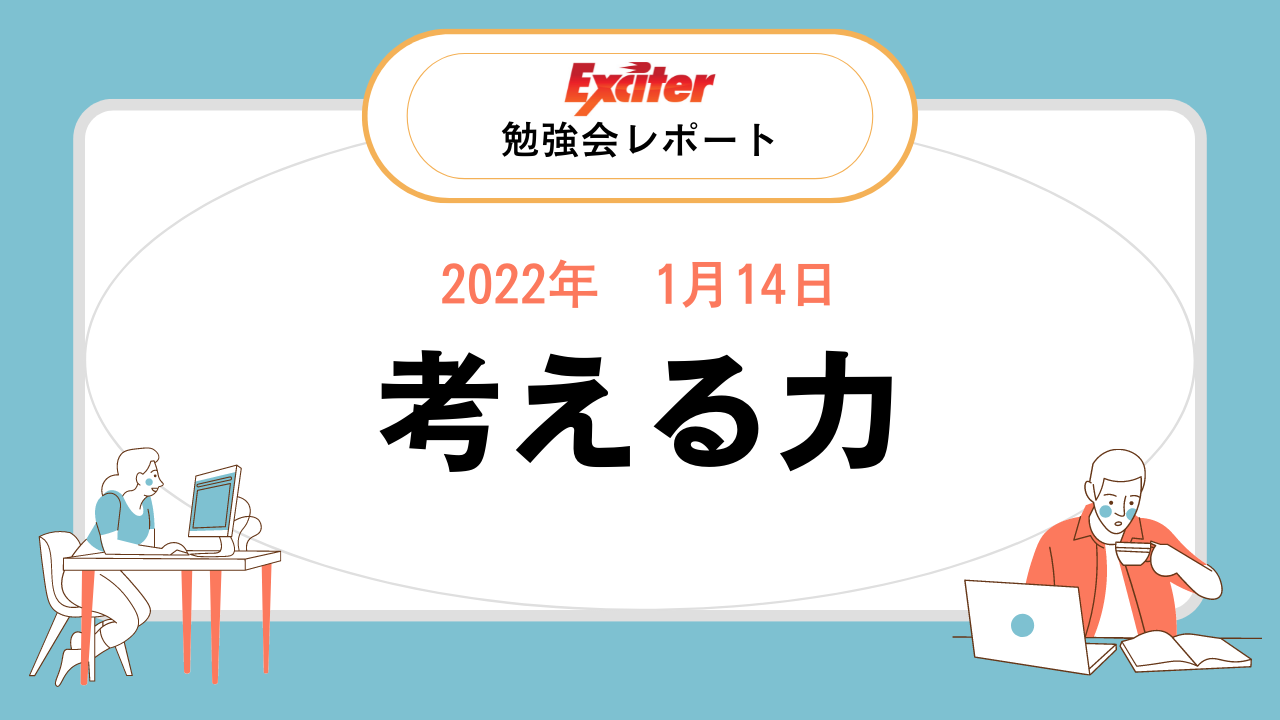

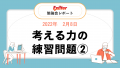
コメント