2022/02/04に行った勉強会「コミュニケーションの基本」についてのレポートと、感想である。
当勉強会は、伝える力の一部である「コミュニケーションの基本」について、コミュニケーションを行う上での基礎を理解する目的で行われたものである。
コミュニケーションの基本とは
コミュニケーションのゴールとは相互理解である。そのゴールを達成するためには、以下で述べる2つが必要になる。
①いかに伝えるか
事実や定量的な情報をヌケもれ誤りなく、いかに伝えるかを意識すれば、相互理解できるコミュニケーションを行う事ができる。
とはいえ、コミュニケーションはそれが全てではなく、それ以外にも信頼関係の構築が必要である。
②信頼関係の構築
事情・背景・感情は相手との信頼関係がないと理解する事が難しい。
例えば、仕事において害はあるけど有能な人がいた際に、害をもたらすからその人は敵だと判断するのは大いに間違っている。というのも、敵か味方かはその時点の状態に過ぎず、永続的な関係ではない。それを、事情や背景を考えずに敵と判断することは間違っている。
だからこそ、事情、背景、感情を理解するために信頼関係の構築が必要不可欠なのである。
信頼関係の構築方法
信頼関係を構築するためには、コミュニケーションの回数、コミュニケーションの時間、イベントの回数を増やす必要がある。
まずコミュニケーションの回数が多いと、人は相手に好感を持ちやすい。同様に、コミュニケーションの時間(一緒に過ごした時間)が長いと相手に好感を持ちやすい。楽しいイベントや、苦しいイベントを過ごした相手には心を開きやすい。
上記3つを満たすことによって信頼関係を築くことが出来るが、この3つのうち1つでも欠けてしまっては信頼関係を築く事が出来ない。
コミュニケーションの回数・時間を増やし、イベントを増やす方法
信頼関係を構築するための、コミュニケーションの回数・時間と、イベントを作るためには、何をすればよいのだろうか。
それには、挨拶と、「問いと答え」のコミュニケーションが必要である。
挨拶
はじめに挨拶について述べる。挨拶は他者への気遣いのきっかけになる。というのも、挨拶を交わすことによって相手の表情、声のトーンから相手の様子が分かるため、そこに異変があれば気が付くことが出来る。
また、挨拶を通して動静確認を行うことが出来る。動静確認とは、現状を把握しそこにリスクが潜んでいたら、それに対する策を講じ、事前にリスク回避する事である。挨拶から世間話に発展する事は頻繁にある事だが、その世間話を通して相手が何かリスクのあるような発言をしたら、こちらもそのリスクを回避するための策を講じる事ができる。
このように、挨拶は何気ない事であるが、コミュニケーションの回数・時間や、イベントを作る種、他者への気遣いのきっかけ、或いは動静確認を達成する事ができるため、しない手はない。
「問いと答え」のコミュニケーション
次に、「問いと答え」のキャッチボールについて述べる。問いに対して答えがあるコミュニケーションこそが、信頼関係構築に繋がるコミュニケーションの形である。というのも、一方的に、自分が話したい事を話す、或いは自分の事は話さないで聞き手に徹するというのは、お互いの事を知る事が出来ないため信頼関係構築には繋がらないのだ。
だから、「問いと答え」がセットになっているコミュニケーションが必要である。
「問い」には人間性が出る。というのも、問いには何を理解していて、何が理解できていなくて、疑問はどこにあるのかが、全て露わになるからである。
若手で多いのが、「質問はありますか」に対して、「ありません」という、認識が両者で同じであるかの確認もせずに、自分は分かったつもりになってしまっている事である。これは、話し手に自分は疑問がどこにあるかも分かりませんと言っているようなものである。
「問いと答え」のコミュニケーションに重要な「意図」
「問いと答え」のコミュニケーションは大事であると述べたが、そこには意図を意識する必要がある。「問い」に適切に意図が含まれていることで、「問いと答え」のコミュニケーションが成立するからだ。
例えば、「何食べたい?」の質問に対し、「なんでもよい」と返すのは、あまり良い「問いと答え」のコミュニケーションと言う事が出来ない。なぜなら、発信者側は問いに自分の意図を含む事をしておらず、答える側は、何の意図で発信者が質問しているか分からないため何を答えたらいいのかも分からない。そうすると、答える側はストレスを感じる。
このように、「意図」が欠落してしまうというのはコミュニケーションを適切に行えず、相互の理解が食い違ってしまう事や、相手を怒らせてしまう原因になるため、悪である。
コミュニケーションを阻害する3つのこと
「問いと答え」のコミュニケーションを行う上で、気を付けるべきコミュニケーションを阻害する3つのことについて述べる。
それは、未熟さと、自己肯定感と、貧乏マインドである。
未熟だと、「問い」が言い訳や、クレームのように受け取られてしまい相手を怒らせてしまう原因になる。他にも、「意図」にまで気が回らず意図を含んだ問い、或いは意図通りの答えができない。
自己肯定感が低いと、「問い」が自分を攻撃している。と感じてしまう。他にも、上司などから意見を求められた時に、自分は期待通りの意見を言えないなどと、卑屈になってしまう。
貧乏マインドがあると、無駄なプライドを持っているため、問う事がそもそも出来ない。
上記3つの要素を持っていると、「問いと答え」と意図を含んだコミュニケーションを阻害するため、信頼関係を構築する事が出来ない。或いは、相手から信頼関係を構築する気がない人だと誤解を生んでしまう。
信頼関係がない状態とは
信頼関係の構築はいかに必要かについては述べた通りであるが、信頼関係がない状態はコミュニケーションを行う上で、ハンデになるのかと言われればそうではない。
信頼関係がない状態とは、相手の事をフラットに見ている状態であるため、決して悪い事ではない。というのも、信頼関係がない相手に対しては、事実・論理・定量的な情報をいかに伝えるかを意識するため、相手に理解してもらおうと甘えるスキがない。或いは、相手に対して、決めつけがない。
一方、信頼関係があると、相手に理解をしてもらおうと甘えるスキが出て、事実・論理・定量的な情報をいかに伝えるかを意識する事を怠ってしまうため、信頼関係がある相手とのコミュニケーションには注意が必要である。
まとめ
コミュニケーションには必ず相手が存在するものであり、相手が理解できるように、抜け漏れなく事実や定量的な情報をいかに伝えるかを意識して相手と会話する必要がある。
しかし、それだけでは不十分である。それは、事実などの定量的な情報だけでは、相手の事情や、背景、感情を理解する事が出来ないからである。それらを理解するためには、信頼関係が必要であり、コミュニケーションの回数、時間やイベントを作る事が必要である。それら機会を生み出すのは、挨拶と「問いと答え」のコミュニケーションである。
感想
私は、コミュニケーションにおいて意図が欠落していると指摘をうけた事が多々ある。それは信頼関係を構築するコミュニケーションには繋がらない事や、相手を怒らせる原因になってしまうので、特に注意して意図が相手に伝わるようにしなければいけないと感じた。
他にも、挨拶は割と自分からできるが、そこから動静確認をするという発想がなかったので、挨拶をただ行うのではなく、そこからリスクなどを探知し、そこに備えることが出来たら、挨拶1つにものすごい価値を見出せると感じた。
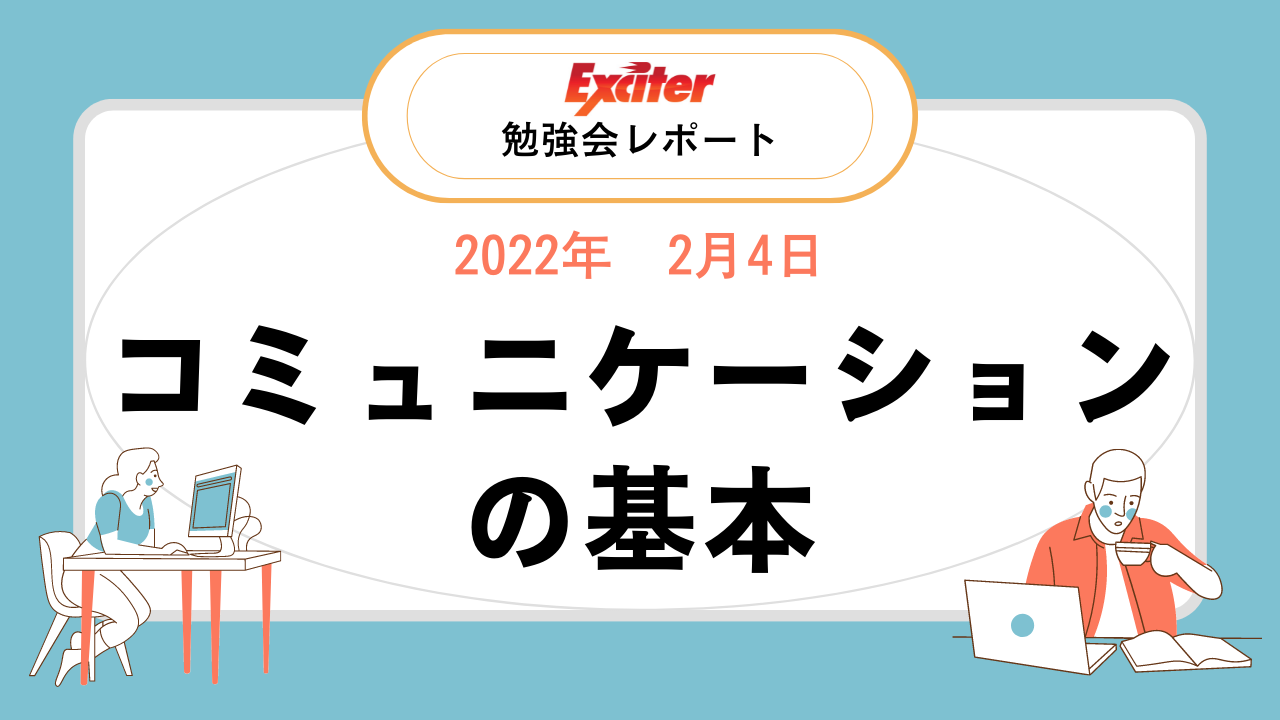
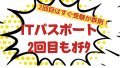

コメント