今回の勉強会のレポートは、前回行った勉強会「若手によくある誤解」の続きを紹介する。
【前回の記事はこちら↓】

若手が誤解することを減らして、若手の良いところと悪いところのバランスをとるために、これらをもっと理解することに役に立てばと思う。
若手によくある誤解の続き
ゼロから始まる
日本ではポテンシャル採用がメインだから、何もできない、分からないことが問題ではない。就職活動のとき、どんな仕事を選んでもゼロから始まるのは同じだ。何もできない若手に対して、採用担当者は将来性があるかどうかを見ている。
知識、技術、経験などがないので、若手はすぐに役に立てない。何もないから当たり前だ。しかし、上司や先輩は色々な知識、経験などがすでにあるから、実力にギャップがある。彼らはすでに役に立てる人たちなので、みんな忙しくて、あなたに何か優しくしてくれる理由はない。
それは、若手が何も知らないから周りの人があなたを手伝いたくないわけではない。みんなも忙しくて、あなたの面倒を見ることができない。だから、若手はいつも嫌な仕事をもらったときに、やめたくなる。また、彼らは続けることとやめることの間に何があるかを考えない。
先輩や上司は、仕事をしない、ミスが多い人より、ちゃんとタスクをやる、コミュニケーションを取る、確認することができるような人の面倒を見たい。
テイクが先
あなたが忙しいときは、誰も助けてあげられない。特に、自分に関係ない人や、何もしてくれなかった人たちは、なおさら助けようと思わないかもしれない。しかし、仲がいい友達や家族、あなたのために何かしてくれた人などは助けようとする。この人たちは何かをしてくれたなら、その人が助けを必要としている時に、それを返したいと思うのだ。このことを「Give-and-take」という。
ただし、若手は「Give-and-take」ではなく、テイクが先だと思っている。若手はまだ役に立てないから、周りの人が何かを与えてくれると思っている。だから、テイクが先と思っている。例えば、上司または先輩に、いつも自分の面倒を見てもらいたい、と思っていることである。しかし、あなたはまだ何も与えてないので、始めから何かをもらおうとすることはよいことではない。何かをもらえるために、まず自分で何かを誰かに与える必要がある。例えば、上司や先輩があなたの面倒を見てくれるように、彼らから与えられるタスクをちゃんとし、約束を守り、雑用などもするべきだ。
察してくれない
子供が泣いている時に、話さなくても泣いている理由はお母さんが分かっている。しかし、仕事では、そうはいかない。上司や先輩はあなたのお母さんではないので、あなたが言わなければ、彼らはあなたが何を必要としているのか分からない。
また、みんなも忙しいので、あなたが助けてほしいと言わないと、彼らはあなたに尋ねることはない。だから、誰かに伝えるべきことを自分から伝えること。
例えば、テストするときに、エラーが出てくる。
- よくない言い方は、「すみません、エラーが出てくるけど、…」。これを言うと、みんなはエラーが出てくる理由や背景を知らないので、アドバイスができない。
- 良い言い方では、「すみません、このボタンを押すとエラーが出てくるのですが、何をするべきか教えてください。」これを言うと、みんなはエラーが出た理由を理解できるし、何かアドバイスをすることもできる。
何を言うかよりも誰が言うか
本来、何を言うかは重要だが、誰が言うかはもっと重要である。同じことを言っても、言う人によって相手の受け取り方が違う。例えば、同じ意見を言ったとしても、人はミスばかりする新人よりも、きちんと仕事をしている人のほうに耳を傾ける。
だから、あなたは新人なので、みんなから信頼されるためにはきちんと仕事をしなければならない。ちゃんと真面目に仕事をし、知識、能力などを高めていけば、話を聞いてもらえるようになるだろう。
タイミング命
何を言うのか、誰が言ったのかだけではなく、いつ言うかも大事だ。一番良いタイミングはないが、できるだけ適切なタイミングが必要である。ただし、適切なタイミングを探すことは難しいので、まずは最悪のタイミングを避けることから始めよう。例えばディベートのとき、最悪のタイミングの例としては以下のようなことがある。
- 決めた後に言う
- ギリギリに言う
- 結論が出る前に言う
- 早すぎる、もしくは遅すぎる
「わからない」禁止
わからなくても「わからない」と言わない方がいい。わからないと言うより、「私は○○と思う」とか、「私はこのように○○と考える」と言った方が良い。若手はまだ色々なことが足りないから、わからなくても当たり前だ。また、上司や先輩は正しい答えを求めていないので、答えがわからなくても、あなたはどう思うか、どのように考えるかを言うことが大事だ。あなたなりの考えを伝えず、わからないだけで済ませてしまうと、上司や先輩はどこを修正したらいいのか分からないし、そもそもやる気がないと思われてしまう。
また、仕事だけではなく、面接の場面でも同じだ。面接の最後に、「何か質問がありますか?」と聞かれたとする。そこで「分かりません」や「何もないです」と言うのは、その会社に興味がないことを示していることになる。
まとめ
若手は何もないので、役に立てないことは当たり前だ。しかし、日本ではポテンシャル採用がメインだから、ゼロから始まるのは大丈夫だ。若手はまだ役に立てないから、せめて与えられた仕事をきちんとする、約束を守る、というような形でできることから能動的に動くことが求められる。誰かが何かをしてくれたなら、その人が助けを必要としている時に、それを返したいと思うのだ。
また、みんなも忙しいので、誰かに伝えるべきことを言わないと、あなたに何か助けることができない。
さらに、本来、何を言うかは重要だが、誰が言うかがもっと重要である。これらだけではなく、いつ言うかも大事だ。
最後に、わからないと言うより、「私は○○と思う」とか、「私はこのように○○と考える」と言った方が良い。
感想
勉強会について
勉強会は3回目ですが、やり方にはだんだん慣れてきた。毎回やるのは、私のリスニング力や、理解の力が練習になる。知らない言葉もあるのが、前の勉強会のおかげで馴染みになった言葉もある。例えば、知識、将来性、成長して、信頼などの言葉である。
トピックについて
今回のトピックは、前のトピックの続きだから、もう概念を理解することができる。トピックについて、次のポイントを理解することができる。若手は価値がある。一つ目は、若さ、二つ目は将来性である。しかし、悪いところがたくさんある。例えば、知識、経験などがなく、プライドが高いことである。良いところは二つだけあるから、価値のバランスをとるために、これらの悪いところを減らすべきだ。だから、これらの誤解を理解することは大事だ。
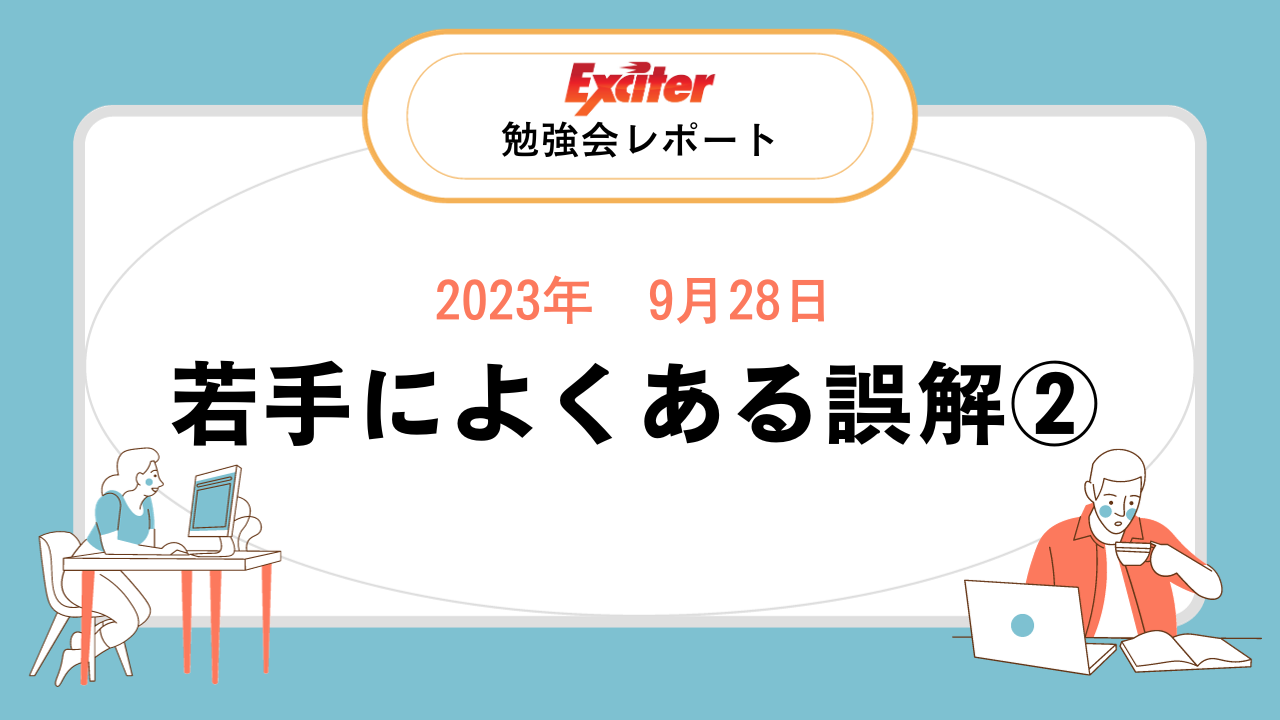


コメント