本レポートは、学生や若手が「長時間労働=悪」という固定的な見方でなく、労働時間に対して多くの視点で考えられるよう実施された勉強会の内容である。
はじめに
近年、働き方改革の一環として長時間労働が問題視され、労働時間の削減が行われている。多くの人は長時間労働と聞くと、悪い風習だ!ブラック企業だ!という印象を持つ。
しかし、長時間労働は必ずしも悪とは言えない。例えば、若手にとって長く働けばその経験の中で能力を身に付け、より早く一人前になれるチャンスでもある。つまり、長時間労働=悪という単純な問題ではないということ。
本レポートでは、労働時間をいろいろな視点から考えることを通じて、労働時間との向き合い方を述べる。
考えてみよう
ある工場でのシミュレーションを通じて、労働時間について考える。
工場の労働環境
- 一人当たりのノルマ:1日で8個(多くの人がクリアできる)
- 労働時間:8時間(+休憩1時間)
つまり、多くの人は1時間で1個作ることができる。
Aさん
- 1個作るのに1.5時間かかる
- 定時=8時間なら6.4個、8個作るには10時間かかる
Q1.Aさんはノルマを達成していないが定時で帰ってよいだろうか?
法律的にはOKだが、ノルマ達成までは帰るべきでないと考える人が多いだろう。
Q2.Aさんは残業代を払われるべき?
Aさんがノルマを達成するには残業が必要だが、他の多くの人は定時内に終わらせているのだから、残業代は払うべきではないと考える人もいるだろう。
Q3.Aさんの給料は下げるべき?
定時内にノルマ達成できる他の人たちとAさんの間にはパフォーマンスに大きな差があるので、Aさんの給料は下げるべきと考える人が多いだろう。
Q4. Q1~3への答えは、自分がAさんだとしても同じ答えになるだろうか。
もし自分がAさんの立場だったら、「ちゃんと働いた分は残業代を払って!自分なりに頑張っているから給料は下げないで!」と思うかもしれない。
つまり、「長く働く=悪、短く働く=善」という単純な問題ではない。労働時間の長さ自体は大事ではなくて、いろいろな視点から考えるべき話題。
労働の原理原則
そもそも、労働とはどんな原理原則によって成り立っているのだろうか。成果・生産性・労働時間の3点で考える。
成果=生産性×労働時間
これは殆どの仕事に当てはまる労働の原理原則である。
まず、生産性について。生産性とは、知識・技術・経験・センスなどを指す。これは人によって、キャリアの長さによって大きく異なる。
次に労働時間について。こちらはシンプルで、同じ成果を上げるためには生産性が低い人は多くの労働時間を必要とする一方、生産性が高い人は短い労働時間で済む。
この原理原則にのっとれば、働き方は「生産性・労働時間」という二つのパラメーターによって決まる。しかし、生産性は一朝一夕で上がるものではないため、生産性が低い人が大きな成果を上げるためには、労働時間を増やすしか手段はない。
労働時間がブレる要因
働き方は生産性と労働時間で決まるが、その労働時間がブレる要因は、①従業員、②会社・業界、③管理職の3つに分かれる。
①従業員
単純に本人の生産性が低いパターン。経験が足りない、能力がないなどの要因により生産性が低いため、他の人よりも労働時間が増える。
②会社・業界
繁忙期や急な欠員、急な発注などで普段より仕事量が増えて労働時間が増える。
③管理職
不適切な人材配置、教育の不足などにより生産性が低くなり労働時間が増える。また、「俺が帰るまでは残れ」という考えを持つ管理職の人格的な側面が要因の場合もある。
原理原則の例外
成果=生産性×労働時間 という原理原則は間違いないが、その例外となるケースもある。
例外1:労働時間=成果÷生産性
自分がやるべき仕事=成果が急に変化して、それに対して自分の生産性を考慮して、結果として最終的に何時間働くかが決まるというケースもある。
例えば、急に割り込みタスクが入ってきてしまったが、現状のタスクも今日中にやらなければならない場合。この場合、自分の生産性を考慮して、両方を終わらせるためにかかる時間が結果として、労働時間になる。
例外2:ひらめき、アイデア系
ひらめきやアイデアが必要な仕事は、時間をかけたからと言ってその分成果が上がるとは限らない。例えば、作詞作曲するアーティストは、1日中歌詞が浮かばない日もあれば、急にひらめくこともある。
労働時間との向き合い方
次に、労働時間をいろいろな視点で考えた上で、向き合い方を考えてみる。
「一人前」と労働時間
どのくらい働いて、何歳になれば一人前になれるのかを考える。まず前提として、一人前になるためには概ね2万時間を必要と仮定する。
①1日8時間、土日祝休みの場合
1年あたりの労働時間・・・8×(365-125)=1920(時間/年)
2万時間に達するまでの年数・・・20000/1920=10.4(年)
②1日10時間、土日祝もある程度出勤した場合
1年あたりの労働時間・・・10×(365-100)=2650(時間/年)
2万時間に達するまでの年数・・・20000/2650=7.6(年)
22歳で入社したとしたら、計算上は①の場合は33~34歳、②の場合は29~30歳くらいで一人前になれる。このように、長く働けばその分だけ一人前になるのは早い。そして、一人前の人はたくさん給料がもらえるため、一人前になるのが早ければ早いほど生涯年収は高くなる。
ブラック企業と世の中の流れ
最近では、社会全体のホワイト化が進んでいるが全員がホワイト企業に入れるわけではないため、一部の人はブラック企業に入る。また、日本人の中には辛いことに耐えることを美徳としている人が多い。
そのため、ブラック企業で自分にとってプラスにならない長時間労働にひたすら耐え続けている人もいる。
しかし、「長時間労働は全て悪」とはいえないものの、「悪い長時間労働」は存在する。
そのため、自分のために長時間労働をしているのか、ブラック企業で悪い長時間労働をさせられているのかをしっかりと見極めることが大事。
どうなりたいか?
自分が将来どうなりたいかを人生単位で考えたうえで、働くことが大事という話。
多くの人が、辛い仕事から逃げたくなる、毎日遅くまで働くことも嫌になる。しかし、毎日が辛いor毎日が楽という0か100かで考えない方がよい。ワークライフバランスは一日単位ではなく、人生単位で成立させるもの。
例えば、20~30歳でたくさん働いて一人前になり、40歳以降で家族をもって短めに働くというバランスのとり方もある。逆に、20~30歳のうちに頑張らず、一人前になれていない40歳がここから頑張って一人前になることは難しい。体力的に長時間労働はできないし、そもそも一人前じゃない40歳を雇ってくれる会社があまりない。
つまり、ワークライフバランスを「今」や「1日単位」という目の前の目線で考えてしまうと、将来のことが見えず後々苦しい人生になる可能性が高い。しかし、人生という長い単位で考えることで、今目の前の辛いことも将来のためと前向きに考えて取り組めるようになり、後に幸せな人生になる可能性も高くなる。
納得感と耐久力
ポイントは、納得感と耐久力を持って働くこと。
納得感について。仕事なので自分が納得できなくてもやるべきだが、納得したうえでやった方がいい。例えば、下積みの頃は低賃金で面白くない仕事ばかりかもしれないが、自分にとってプラスになっている、将来のために必要だと納得したうえで働くことが大事。
耐久力について。暴力は減っているが、説教や詰めなど言葉による暴力は存在する。それはそれで心が辛いが、仕事なのである程度は耐えなければならない。しかし、心は一度壊れてしまったら元に戻らないので、我慢しすぎて心を壊してはいけない。自分の中に基準をもって、耐えられる範囲でうまくやろう。
おわりに
「長時間労働=悪!、短時間労働=正義!」と単純に考えず、様々な視点から考えよう。確かに、生産性の低い人が成果を挙げる、より早く一人前になるためには長く働かなければいけない。
しかし、自分のプラスにならない悪い長時間労働があるのも事実だし、体や心を壊してしまっては元も子もない。自分の将来像・目の前の仕事への納得感・体と心の耐久力など様々な視点から柔軟に考えよう。
感想
今回の勉強会を通じて、自分の将来像を明確にして働くことが重要だと感じた。そうすることで、自分の将来像を実現するために必要な仕事であれば例え辛くても、長時間であっても働くべきだと納得したうえで働くことができ、日々の仕事に前向きに望むことができる。私も将来像を確かに持ったうえで前向きに働けるようにしたい。
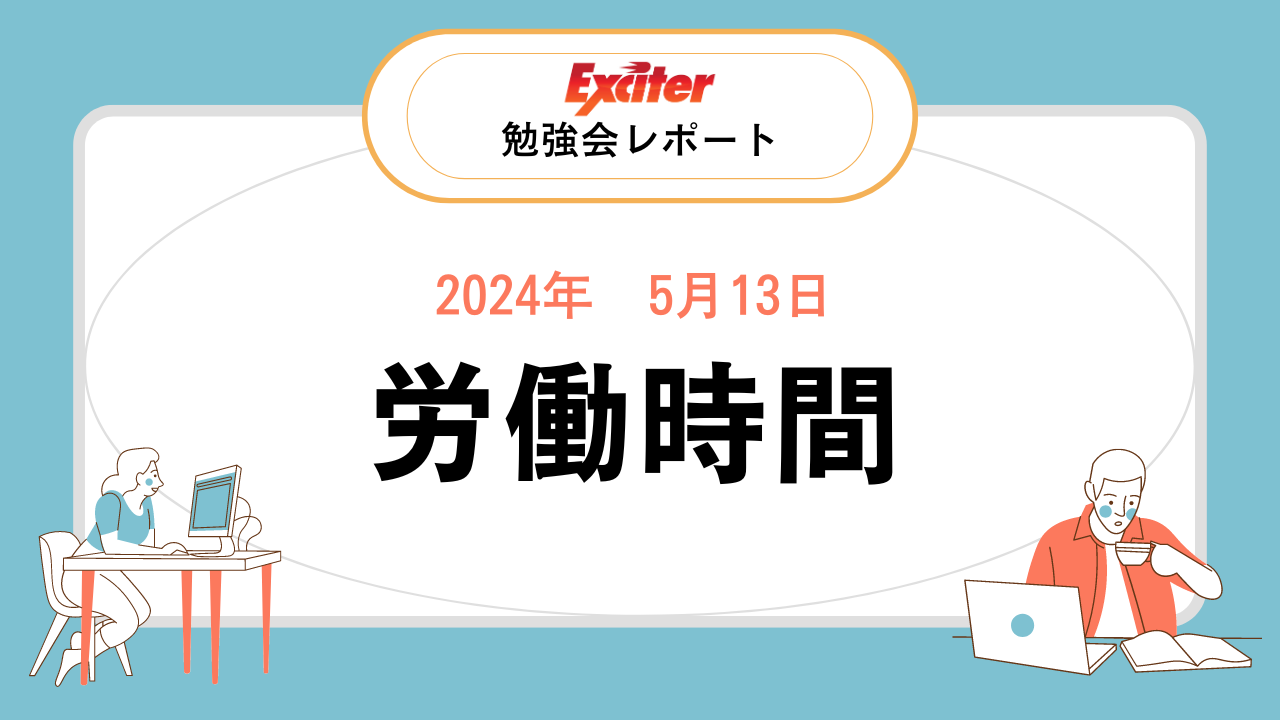


コメント