生きている限り、納得できないこと・理不尽だと感じることはたくさんある。そして、それは平社員、管理職、社長、アスリートからアーティストまで誰にでもある。
しかし、特に注意が必要なのは若手だ。学生のうちは公平に平等に扱われ理不尽なことなんてなかったのに、社会に出たら一番立場は弱いので理不尽なことが多く、そのギャップに苦しむからだ。
だから、若手こそ納得できないこと・理不尽なことに対して理解を深めて、うまい付き合い方を知る必要がある。
なぜ理不尽なことが起きるのか?
結論、される側は嫌だがする側としては非常に都合がいいから起きる。
理不尽なことは、立場の上下がはっきりしている関係性でしか起きない。性別や人種が違うからといって上下がついたりはしないが、仕事における立場の上下は明確にある。
例えば、上司から雑用を指示されたら部下は従わないといけない。客と業者が1つの作業で契約していても、客が追加でもう1つやってと言ったら、ある程度業者は従わないといけない。嫌なら会社を辞めたり客と縁を切ったりするしかないが、会社や客なしで大体の人は生きていけないし、いちいちそんなことをしていたらキリがない。
そもそも、「理不尽なこと=悪」と思うのは自分が理不尽を受ける側だから。もし自分に後輩ができた際に、面倒くさい雑用があったら後輩に振るだろう。もし自分が客だったら、業者をできるだけ安く働かせようとするだろう。
つまり、理不尽はされる側にとっては嫌なことだが、する側にとっては非常に都合がいいため、立場の上下がある以上は存在し続ける。
理不尽とは?
理不尽だと感じる時のキーワードは2つあり、①筋が通っていないこと、②納得感がないこと。
これらのキーワードについて、勘違いしている人が多いため正しく理解しよう。
①筋が通ってないこと
論理的におかしい・因果関係が破綻している場合、理不尽だと感じるが、そもそも全ての場面に通用する論理などなく、立場ごとに様々な論理がある。つまり、「論理がおかしいから理不尽だ!」と感じても、それは単に自分以外の立場の論理を知らないだけという場合も多い。
②納得感がないこと
たとえある程度筋が通っていても、自分の感情的に腹落ちしない、納得できないことはあり理不尽に感じる。なので、もちろん何事も納得できた方がいい。
しかし、そもそも立場が上の人は下の人に納得してもらおうなんて思っていない。ビジネス上のキーパーソンであれば納得するまで説明してくれるかもしれないが、大した仕事もできない若手をわざわざ納得させようと思う人はあまりいない。
例えば、あなたが後輩に事務所の掃除を指示したとする。それに対して後輩が「掃除するなんて納得できません!やりません」と言ってきたらどう思うのだろうか。いちいち掃除の必要性、それを後輩がやる意義などを後輩が納得するまで話して納得してもらおうと思う人は少ないだろう。「いいから黙って掃除しろ」と思うはず。あなたに納得できないことを言ってくる人も同じことを思っている。
なので、「納得したい」という考えはそもそも捨てたほうが楽。
実は理不尽ではないこと
自分が理不尽だと感じて嫌な思いをしたことの中には、実は理不尽でないことも多い。なので、実は理不尽ではないことを知って、いちいち嫌な思いをして消耗することを避けよう。
①自分の好きなタイミングで休みが取れない
自分都合で休憩や休暇が取れないことは理不尽なことではない。例えばランチ営業をする飲食店であれば、お昼時に休憩は取れず客足が少し落ち着いた2,3時あたりに休憩を取る。それを同じ論理で、プロジェクトでトラブルが起きた・納期が近いなどの場合は、自分の都合に合わせて休みを取ることは難しい。ずっと休憩や休みが取れないなら問題だが、仕事の都合を考えず休みたいと言って休みが取れなかったからといって、それは理不尽ではない。
②評価されない・褒められない・地味な仕事
評価される・褒められるような仕事は実力がある人に集中するため、逆に評価されない地味な仕事は実力が低い人が担当することになる。そのため、若手のうちは評価されない地味な仕事が多い。単純に実力がないからそういった仕事しか来ないだけなので、理不尽なことではない。
地味な仕事を指示されたとしても、地味であっても必要な仕事はしっかりやる人間かどうか試されている場合もあるため、信頼を勝ち取るためにもこういう仕事もしっかりとやるべき。
③「自分で考えろ→勝手にやるな」
上司からの指示は抽象的なことが多いため、部下は自ら考えて指示を具体化したうえで作業する。その際に、部下が上司の認識と全く違う方向性で進めしてしまい、作業後に「勝手にやるな!」と怒られ、作業が無意味になることがある。
一見理不尽なように感じるが、若手は自分でやるべき範囲と誰かに頼むべき範囲がわかってないから、怒られる。つまり、単純に実力不足だから怒られているだけで理不尽ではない。
残念ながら、それが身につくまでは続くことになる。
④不要な会議
不要な会議に参加させられると「時間の無駄だ、作業に集中させろ!」と感じるが、上司には実は参加させた目的がある場合もあるため理不尽なこととは言えない。例えば、会議自体に慣れさせること、キーパーソンに顔を覚えてもらうこと、ファシリテーションの方法を学ばせること、議事録を書いてもらうことなど。
逆に、その目的を汲み取ったうえで、議事録を書くなど目的を達成する必要がある。
⑤先輩・上司が無能
会社で関わる先輩社員や上司が、コミュニケーションが下手、作業が遅い、PCについて知らないなど無能だと感じる機会がある。無能だと思っている人から指示されることもあるが、それには従わなければならないことは理不尽ではない。
それは、自分から見たら無能というだけで会社にとって必要な人材である場合もあるから。
例えば、社歴が長いだけの人に思えても、社歴が長いからこそ、会社に関することの隅々まで知っていたり、色々な社内のキーパーソンを動かせる人だったりする。
そもそも、「無能だと思っているその人よりも、自分は立場が低い」という事実は受け止めなければならない。
⑥言い訳するな
なにかミスをして怒られているときに「言い訳するな」と言われてもそれは理不尽ではない。
もちろん、ミスには背景や理由があり、ある程度仕方なかったのかもしれないが、ミスをしたのは自分なので受け入れるしかない。
また、絶対にNGな言い訳「人のせい・忙しい」の2つは避けよう。
「人のせい」について、例えば「僕は違うと思いましたが、~~さんに指示された通りにしました。」なんて言ってはならない。違うと思ったらその時にそういえばよいので、結局は自分のせい。少なくとも、そう思った方が楽。
「忙しい」については、若手よりも暇な人なんていないので、そもそも通用しない。
⑦人格否定
仕事の品質が悪いからといって人格を否定することは理不尽であるように感じる。しかし、仕事の品質はあくまで表面的な部分に過ぎず、その根本はものの考え方・とらえ方や仕事への姿勢という人格や価値観に近い要素である。そのため、仕事の品質を根本的に改善するためには、ある程度人格的な部分まで踏み込んで改善する必要がある。
愉快か不愉快かで言えば当然ながら不愉快なのだが、頭脳労働者が成長するには避けて通ることはできない。
理不尽との付き合い方
社会に出れば理不尽なことはいくらでもあるので、正しい向き合い方を知る必要がある。
特に付加価値の高い仕事は理不尽なことが多い。例えば、高級料理店であれば味はおいしいにもかかわらず、接客がどうの、店の雰囲気がどうのと言われて文句を言われる。しかし、付加価値が高いからこそ要求されるレベルも高いのであって、ある程度は受け入れる必要がある。
しかし、全てを我慢するわけにもいかないので、「受忍限度」という基準を持とう。受忍限度とは、世間一般的にこの程度まで我慢すべき或いはこの程度であれば我慢できるでしょ?とされる範囲のこと。つい、自分が辛い・耐えられないと感じると逃げたくなるが、自分の中の基準だけでなく世間一般的な基準も頭の中に入れよう。そのうえでもしその基準を超えるなら、行動に出ればよいがその範囲内ならば耐えよう。
まとめ
嫌なことがあるとつい「こんなの理不尽だ!理不尽なんてなくなるべきだ!」と感じる。しかし、そもそも立場の上下がある以上は理不尽なことはなくならない。また、自分が理不尽だと思っていたことも、自分の認識の甘さや実力不足が招いたことで、実は理不尽ではないということも多い。なので、嫌なことがあろうと、多少の理不尽があろうと我慢しないといけない。
ただし、すべてを我慢することはできないので、受忍限度の範囲内でうまく理不尽と付き合うことが大事。
感想
私はまだ学生であり普段の生活では公平に扱われるため、理不尽なことに対する理解や耐性がないと感じた。だからこそ、今の段階から感情と論理を切り離すこと・べき論ではなく現実を受け入れることに慣れて、理不尽なこととうまく付き合っていけるようになりたい。
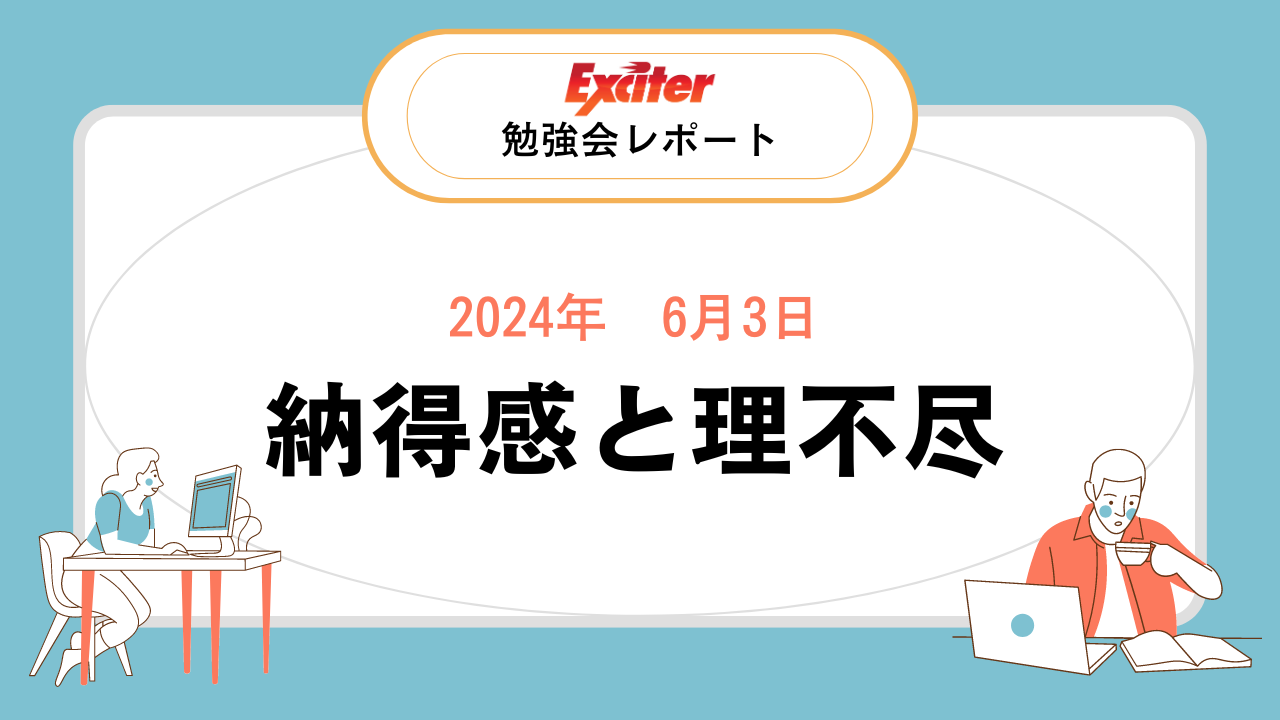


コメント