入社時から取り組んできた応募採用管理関係の作業について、改めて自身が行ってきた作業内容を振り返り、学んだことを踏まえ、感想を記載していく。
作業内容について
応募採用管理の内容と作成物
新規応募者への対応から入社に携わる業務についての内容をまとめ、形にした。
募採用管理は、採用に関する業務(採用フローの確立、採用基準の明確化、応募者への対応~面接設定、engageとAirワークの入力と更新、従業員リストへの反映と週次レポート)、入社に関する業務(入社対応、社員登用フローの確立、社員登用基準の確立)、ビジネスマナーの整理、の3つに分類し作業を行った。
応募採用管理に関する業務を習得すると共に、当社で明確に形にされていなかったフローやマニュアル、およびその他業務に関わる書類等を作成したが、私自身が全て初めて作成したものばかりであったため、それぞれの作成物についてポイントを交えながら記載する。
フロー作成
採用業務(応募者の受付から採否の決定まで)や入社業務(入社手続き)には多くのプロセスが存在し、プロセスの抜け漏れや誤りおよび重複を防ぐために、フローを作成する。
フローの作成により業務全体の流れを分かりやすく把握することができるだけでなく、各業務に必要な作業や書類も明確になる。
フローを作成していく中で、箱(フロー上にてプロセスを表すもの)と箱が繋がらず違和感がある場合や、ごちゃごちゃしていて分かりにくい場合は、①プロセスに抜け漏れもしくは余分なプロセスが生じているか、あるいは②箱の書き方が簡潔に明確にまとめられていない、ことが挙げられる。
①プロセスに抜け漏れもしくは余分なプロセスが生じている
フローを作成する中で、箱と箱がうまく繋げることができない場合、それぞれの箱の前後に実は箱が存在する、もしくは余分な箱が存在していることが考えられる。箱に抜け漏れや誤りがなければ、必要なことだけがまとまったフローになるはずである。
②箱の書き方が簡潔に明確にまとめられていない
フロー上に表われる箱は業務を適切に進めるためのプロセスを表しているものであり、箱のサイズを原則変えてはならない。(ただし、登場人物をまたいで行うプロセスについては変わる場合もある。)箱の大きさを変えてしまうことで、大きな箱は重要であり、小さな箱は重要度が低いと見なされてしまい、プロセスの重要性にばらつきが生じるように見えてしまうため、同一サイズの箱で繋げなければならない。
箱の中身に記載する内容はプロセス毎に違うものの、文言が箱からはみ出てしまうものについては記載内容が簡潔にまとめられていないことを表しており、端的かつ誤解のない表現で記載しなければならない。

マニュアル作成
応募採用や入社に関わる業務マニュアルを作成した。
マニュアルは、初めての人でもスムーズに作業を行うために必要なものであり、誰が見てもそのマニュアルだけで業務がこなせる内容でなければならない。
マニュアルはフローを元に作成するが、フローを作成する必要が無いものに関しても、簡単に仮のフローを作成してからマニュアルを作成することで、内容に抜け漏れや誤りがなく適切なマニュアルを作成することができると感じた。
マニュアルは各項目の詳細な内容を記載するのではなく、業務の手順や使用方法を説明するためのものである。マニュアルを作成する本人だけの目線で作成してしまうと必ず内容に抜け漏れ等が発生してしまうため、どんなに詳細な内容でも自身が初めて行うことを想像しながら作成しなければならない。
基準の確立
採用や社員登用の際、これまでは管理者の判断に委ねて採否を決定していたが、会社の方針とのミスマッチを防ぐことや管理者以外も判断できるようにするためにも、採用や社員登用に関する基準を明確にしなければならない。
基準を設けるにあたり重要なことは、採用についても社員登用についても、そもそもの背景や目的を設定することから始まる。背景や目的があるからこそ、今後会社にとって有益である人材を獲得する必要性を見出すことができる。
基準の詳細については、指折り数えて出した項目では抜け漏れや重複が必ず生じてしまうため、軸の設定が必要である。採用基準や社員登用基準においては、時間軸(これまで、現在、これから)を設定したが、このように軸を設定することで抜け漏れや誤りの無い項目を設定することができる。
その他応募採用管理に必要な書類の作成
採用フローや入社フローを作成する中で、業務に必要な書類や文書を改めて洗い出し、応募から採否に関するもの(面談前アンケート、面談トークシート、週次レポート)や社員登用に関するもの(社員登用評価表)、および入社に関するもの(誓約書や労働条件通知書等の入社書類)を作成した。
面談前アンケート
応募者を面談して評価する際に、履歴書に表われない本音や口頭では話しにくい内容についてまとめたものである。
職種に関係なく、採用基準や足切り基準を元に、そもそも従業員の一員として同じ環境で働くことが困難と思われる人かどうかを見極める判断材料の一つとなるような項目を設定した。
面談トークシート
管理者以外が面談する際、スムーズに面談できるように、採用基準を元に質問内容をまとめたものである。
職種別に作成したが、面談者から本音を引き出しやすいものにしなければならないため、質問内容だけでなく順序性も意識しなければならない。
応募者の人柄もそれぞれのため、その都度質問する内容や順番にも違いが発生するが、面談トークシート自体がまだ数回しか使用できてないため、今後活用していく中で改善点が必要な場合は、その都度改善していかなければならない。
週次レポート
応募者や採用者の情報を管理する雇用者一覧に関するものであり、応募状況を集計し管理者に報告するためのレポートである。
報告に必要な内容(応募者数、対応者数、対応状況、週ごとに行う内容)を簡潔に分かりやすくまとめることが重要である。
また提出時は、記載する内容が無いのか、ただ単に入力漏れなのか、曖昧になってはならないため空欄で提出してはならない。応募に関する業務は応募者にとっても会社にとっても抜け漏れや誤りが生じてはならない業務のため、表やレポートにしても細かな配慮が必要である。
社員登用評価表
社員登用を公平に行うために、職種ごとに社員登用評価表を作成した。
内容は大まかに、当社勤務に最低限必要とされるPCスキルや社会人として最低限の業務姿勢とマナーが身に着いていること、および資格取得に焦点をあて作成した。
評価は管理者を中心に行うが、社員登用においても従業員と会社の間でミスマッチが起こり得るため、こちらが指定する評価項目だけでなく、従業員の本音について聞き出す項目も重要である。評価する側の意向だけでなく、従業員の意向も含めた内容にすることで、互いにミスマッチを防げる内容にしなければならない。
管理ツールの取り扱い
応募者や従業員の管理は、管理ツールを使用している。求人については応募管理ツール(Airワーク、engage)、入社後は勤怠(Freee)やスケジュール(Googleカレンダー)および従業員情報管理(雇用者一覧)を使用するが、どの管理ツールも個人情報に関することであるため、取り扱いには十分に気を付けなければならない。
面談の実施
面談前アンケートと面談トークシートを実際に使用し、面談を実施した。
トークシートを元に面談を行うが、応募者の本音を聞き出すことが重要であるため、質問内容の順番を意識しなければならない。
また、自身が作成したトークシートであるが、実際に使用してみて改善点もその都度見受けられるため、面談から得た情報を集計し、その都度改善していくことも重要である。
面談内容についてその都度の分析が重要であるが、そのためにまずは面談の場数をこなすことで慣れなければならない。
ビジネスマナーまとめ
ビジネスマナーについては、当社学生がまとめたビジネスマナーを元に、更に詳細な内容を追加し、まとめたものを作成した。横軸を初級・中級・上級に分け、縦軸の項目については身だしなみ、コミュニケーション、心構え、その他に分けて表にした。
表の作成において、思い付きで項目を出してしまうと内容に抜け漏れや重複が生じてしまうため、切り口の設定から粒度を意識して内容をかみ砕くことが重要である。
また、表には空欄を作ってはならず、横軸においては隣の内容と比較で来ている内容でなければならない。表の作成においては、ただ言われたことをまとめるのではなく、表にする目的を意識して作成しなければならない。
まとめ
前職でも採用や入社に携わる業務は行ってきたものの、一から考え基準や書類等を作成する作業が初めてであったため、考え方や作成物の作り方など学ぶことが多くあった。
そして形になったものを実際に活用することで、新たに自身の足りていないところが明らかになり、改善していくという作業の繰り返しであったが、全体を通して主観的な感覚で作り上げてしまっている傾向にあり、客観的な見方を身に付けなければならないことにも気付くことができた。
また、採用や入社は人を管理する業務になるため、各管理ツールの取り扱いやコミュニケーションはいい加減にしてはならず、改めて慎重に行う業務であると感じた。
面談においてはトークシートの内容も重要であるが、そもそもIT業界に経験や興味がある応募者が集まるため、面談時に初めて耳にする言葉や意味が不明確な言葉がでてくるが、エンジニア枠でなくても、そもそもシステム会社に勤めているため、自身もIT用語について理解を深める必要がある。
今後もまだ形になっていない作成物や新たな決まり事等を一から考え作成する機会があるが、応募採用管理の業務で学んだことを生かせるよう意識しなければならない。また、応募採用管理は自身の事務・管理の職種として当たり前にこなさなければならない業務であるが、抜け漏れやミスが許されない側面もあるため、今後も身を引き締めて行わなければならないと感じた。
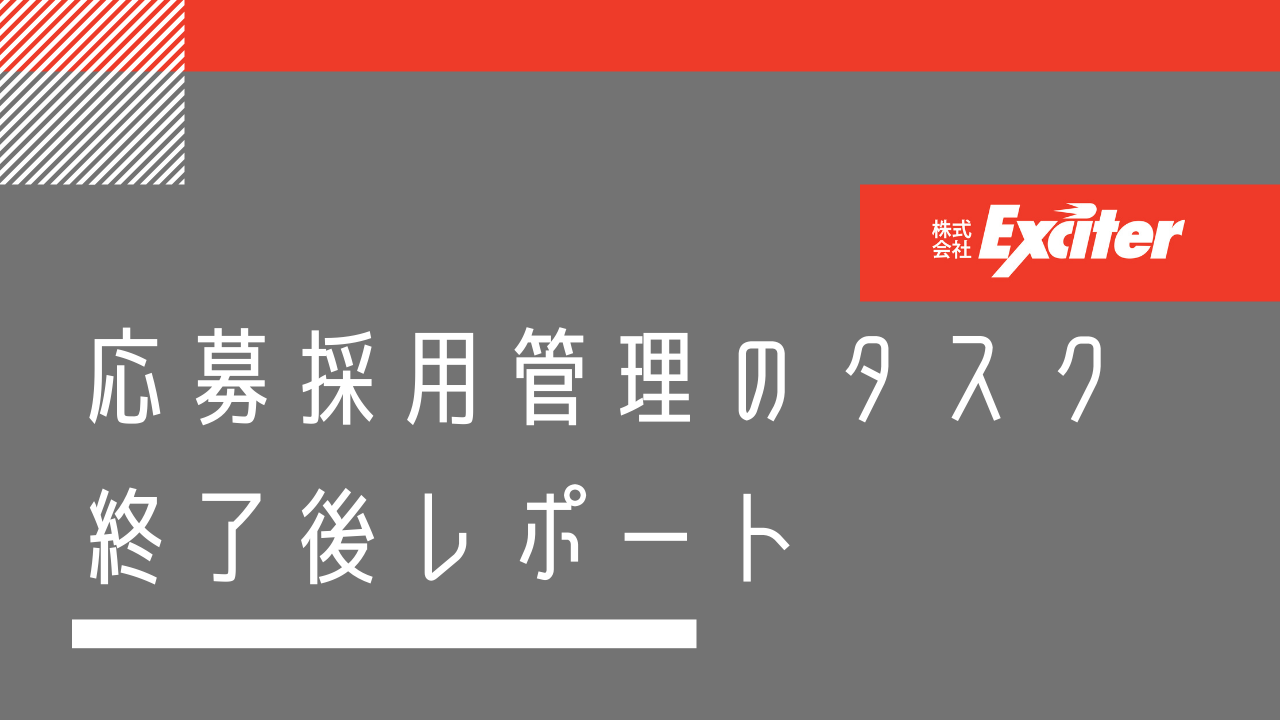

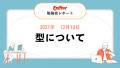
コメント