2022年3月15日に受験したITパスポート試験について、私の体験談と感想について述べる。
現在の会社で働くにあたり取得必須な資格であるため受験した。私は、以前まではIT業界とは程遠い職業で働いていており、ITパスポートという言葉は初めて耳にした試験であったため、ITという言葉だけで抵抗があった。しかし、実際に勉強して受験した印象は、当たり前のように日頃からITに触れている現代人は、一般常識として身に付けておくべき内容が多く、何かの目的として必要か否かに関係なく、取得すべき試験であると感じた。
ITパスポート概要
ITパスポートとは、「IT社会で働く上で必要となるITに関する基礎知識を習得していることを証明する国家試験」である(ITパスポートWEBサイトより抜粋)。ITという言葉だけにフォーカスするのであれば、自分には関係ないと思う人も多く存在するであろうし、私もそうであった。しかし、大多数の職場ではデータ管理やレジ等の業務を通してパソコン・スマートフォンを利用する機会は多く、ITとは全くの無縁とは言えない。
また、ITが幅広く普及する現代において、これから就活を行う学生にも有利な資格の一つとして、学生からの人気も高い資格でもある。
試験概要は以下表の通りである。
| 試験方式 |
|
| 受験費用 | 2022年4月より、7,500円(+支払方法により手数料) |
| 申し込み方法 | ITパスポート専用のWEBサイト(https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/?topbana)から申し込み可能 |
| 試験時間 | 2時間(試験終了次第、途中退出可) |
| 出題内容 | ストラテジ系、マネジメント系、テクノロジ系の3分野 |
| 問題数 | ストラテジ系約35問、マネジメント系約20問、テクノロジ系約45問(各分野の問題数は2~3問程度変動有)の計100問 |
| 合格基準 | 総合評価点1,000点満点中600点以上、かつ、各分野別評価点1,000点満点中300点以上(ストラテジ系、マネジメント系、テクノロジ系それぞれが300点以上を超えていること) |
体験記
勉強方法
テキストと問題集については、下記のものを使用した。
- テキスト
「この1冊で合格! 丸山紀代のITパスポートテキスト&問題集」
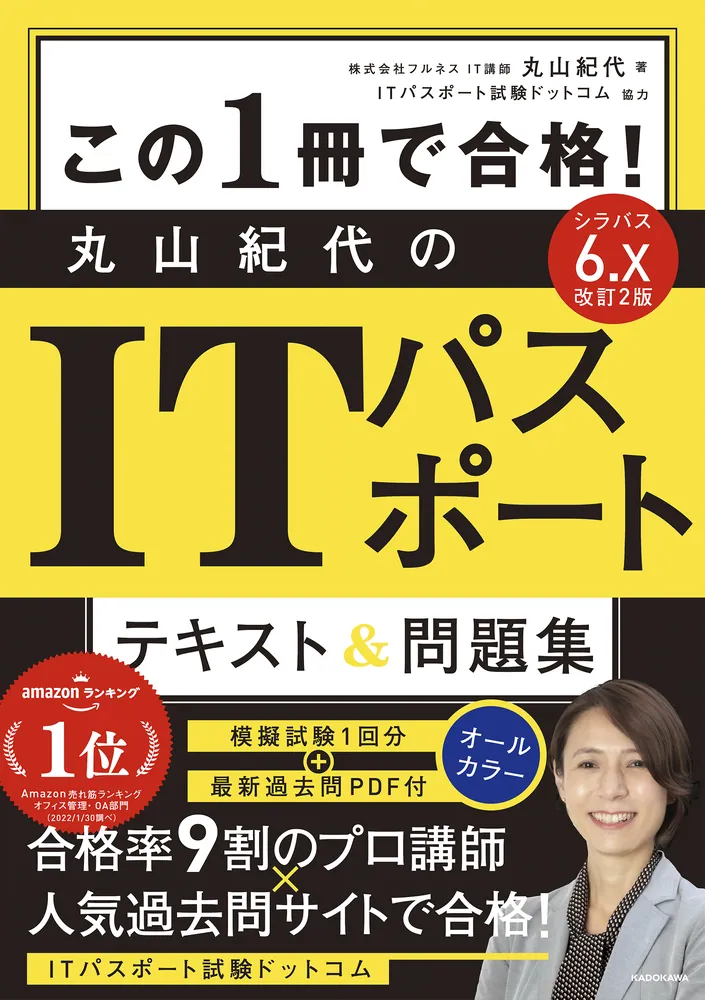
(受験当初はシラバスVer.5.0であったためこちらを使用していた。2022年4月よりシラバスがVer.6.0に改訂されたため、改訂版の使用を推奨する。)
このテキストは、文章による説明とその説明を絵や図でまとめた内容となっており、文字ばかりではないため読みやすく感じた。
- 過去問サイト
「ITパスポート 過去問道場」
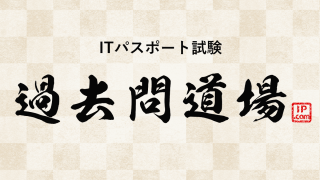
無料かつ手軽であり、問題数も平成21年度~令和3年までトータル2,200問も用意されている(2022年4月現在)。また、出題形式も「試験回を指定して出題」、「分野を指定して出題」、「模擬試験形式で出題」と選択することができ、自身の克服すべき内容に合わせて問題が解けることもこのサイトを利用する大きなメリットである。問題一つ一つに解説があり、テキストだけでは理解が不十分であった内容も、問題を通して理解を深めることができるため、是非オススメしたいサイトである。
勉強は試験の1ヵ月前から始めた。とは言え、正直なところ元々勉強という行為自体が苦手で避けてきたことや、勉強方法もとりあえずテキストを読んで問題集を解くだけといった計画性も無く短絡的にしか考えていなかった。そんな状態であったため、集中力も続かず、明日やろう状態になっていたこともあり、実際の勉強時間は30時間程度であった(今更であるが、そもそもITの知識はほぼ0,勉強も10年以上行っていない、効率的な勉強もまるでできない私には到底足りない時間である)。まともに勉強もできない上に完全に舐めていた自分がいたことはとても情けなく、そしてそもそも私が怠惰な性格であることを認めざるを得ない。
そんな中でも受かりたい一心ではあったため、短期間で合格した人のブログの内容を参考に(そんな時間があるなら勉強に費やすべきであることは今になって反省している)、テキストを1周半まで読み、その後はとにかく過去問サイトに集中した。
ストラテジ系やマネジメント系については、今までの社会人経験や生活から聞き慣れた言葉、なんとなくでも理解できる内容が多かったため、過去問でも正答率は70~80%は取れていた。しかし、足を引っ張っていた分野がテクノロジ系であり、聞いたことのある言葉は多かったが、言葉の意味や内容の理解に苦しんだ。さらに実際の試験ではテクノロジ系が一番多く出題されるため、試験3日前からは8割ほどテクノロジ系の分野に注力した。
また、もう一つ苦しんだものがアルファベットの略語である。「LAN」や「WAN」のように見聞き慣れたものについては、当たり前だが大きな抵抗は無かったものの、とにかく初めて見るアルファベットの略語には最後まで苦しんだ。これについてはとにかく過去問を解く、解説を読み込む、アルファベット一つ一つの単語の意味(「LAN」の場合、L=Local、A=Area、N=Network、つまり限られた範囲のネットワーク)を考えるといった方法により、徐々に正答率を上げることができた。
このような勉強法であったため、参考にもならない内容ではあるが、もし読者が私のようなタイプであるならば勉強法や自身を変えるきっかけになればと思う。(私の場合、勉強法と同時に、怠惰な性格ときちんと向き合い改善策を出し、行うことが何よりも重要と感じている。)
試験当日
あまり行きなれない場所であったため少し早めに自宅を出て、移動中は、予めスクリーンショットしていた過去問サイトの解説を(特に理解しきれていなかったものを中心に)見ていた。そして、試験開始の20分前には会場に到着した。
到着してからは、受付にて予めダウンロードしコピーしていた確認証(受験費用支払い後に届くメールにて確認できる。当日持参必須のため、余裕を持って用意しておくこと。)と身分証を提示し、荷物をロッカーに預け(腕時計は試験室には持ち込めないため、予め外しておくこと)、確認表・注意事項の用紙・メモ用紙・筆記用具を渡され、試験室へと案内された。
試験開始までは確認表を見ながら受験者IDとパスワードを入力し、注意事項やパソコンの操作方法を確認した。
とにかく勉強時間も足らず勉強方法も無理やり頭に詰めるような方法であったため、まずは私にできることと言えば緊張感を持ち、緊張しないメンタルで試験を受けることを予め意識していた(正直なところ、不合格でも、もちろん私が悪いと開き直っていた部分もある)。その為、試験が開始されてもあまり緊張せず、落ち着いて問題と向き合うことができた。問題を解くペース配分も、過去問を解いていたときから「10問を10分以内に解く、悩んでしまったものについては見直しチェックを付けて(実際の試験では見直しチェックを付けられる機能がある)、とにかくペース配分を崩さない」ことを意識していたため、テンポよく問題を解くことができた。そして、問題を解くことは当たり前であるが、過去に受けた秘書検定の経験から、見直しの時間の確保も重要であると学んだため、試験終了までの残り約20分間はひたすら見直しに注力した。
解答後、試験終了時間まで待たずに退室は可能であるが、よほど出来る人でない限りは、試験時間をフルに使って見直しを行うことを推奨する。私のこれまでの経験から、改めて見直すことで、「あれ?なんでこんな回答を選択したのだろう…」という問題がほぼ必ず数問出てくる。その数問の見直しを怠ってしまったことで不合格になる可能性も十分にあるため、過信せずに、きちんと見直しを行うことも合格するための重要な要素の一つである。
結果
試験終了後、すぐに画面上に結果が表示される。結果は言うまでも無く不合格であった(総合評価点515点、ストラテジ系465点/マネジメント系405点/テクノロジ系495点)。各分野の300点以上はクリアできたものの、総合評価点を落としてしまった。各分野が300点以上をクリアしたとしても、必ずしも総合評価点がクリアできる訳ではない。
反省点と改善策
- そもそも私が怠惰な性格である
→まずは必ず勉強する曜日、時間を前以て計画する(水曜日2時間、土日各曜日5時間ずつ)。
- テキストを適当に流し読みしただけであった
→最低でも必ず2周する。次回以降シラバスの変更に伴い、改訂版のテキストを購入する為、1周目はまず大まかな内容を把握するために流し読み。2周目以降は具体的内容を理解するために読み込む。
- そもそも頭に詰め込むだけの勉強法であった
→多少単純記憶の暗記要素はあるものの、複合記憶を意識して語句の意味や内容を関連付ける(アルファベットの略語については、アルファベットを単語に分解し、単語の意味から内容に結びつける)。
感想
今回は弁解の余地なく私の怠惰が顕著に表れてしまった。また、テキストを開いた瞬間からITに対する苦手意識により勝手に抵抗を感じてしまっていた。過去問を解いているときや受験して感じたことは、ずさんな勉強法であったことは反省点として見直さなければならないが、「聞いたことがない」や「知らない」ことについても、どんな内容の試験であっても「考える」ことがそもそもできていれば正解できることも実感した。今までの私は短絡的に「こんなの初めて見聞きしたことだから分からなくて当然」と思ってしまっていたが、見聞きしたことが無いものについても「文章の内容と言葉の意味が結びつくものは何か」を考えることで、苦手であると思い込んでしまったことが少し楽しく感じるようになった。
次回はシラバス改定後の試験であるため、新たな気持ちで臨まなければならない。今回の反省点をムダにせず、自信を持って試験に臨めるよう、勉強に励んでいく。



コメント