個人的に、資料等を作成する上で「粒度」への理解が足らず苦戦している課題の一つである。
ここでは10月08日に行われた「粒度」についての勉強会に参加し、学んだことや感想を記載する。
勉強会内容
「粒度」と「粒度を揃える」
「粒度」とは、文字通り「粒」の大きさや種類等を指す。
資料・文章作成や会話において、粒度が揃わないと相手の混乱を招き、理解を阻害させてしまう要因となる。
そのため、日々思考や考察を繰り返す頭脳労働者は、常に粒度を揃えることを意識しなくてはならない。
では「粒度を揃える」とは具体的にどのようなことであるか。
「粒度を揃える」説明として、料理に例えると分かりやすい。
例えば料理のジャンルを挙げると、「和食・中華・イタリアン・フレンチ」というのは粒度が揃った状態である。
しかし、「和食・中華・イタリアン・ハンバーグ・パスタ」となった場合、料理のジャンルという大まかな粒が基準となっている中に、具体的な料理名であるハンバーグとパスタが入ることに違和感があり、粒度が揃っていない状態となる。
粒度を揃える上で重要であることは、大まかな内容でも詳細な内容でも「揃える」ことである。
種類や大きさや色など何らかの基準で揃えて、バラバラな状態にしないことを意識しなければならない。
何か違和感を覚えた時は粒度が合っていない状態なので、違和感に気付くことができるということも重要なポイントである。
粒度を揃えることの重要性
粒度が揃っていないということは、相手の理解を混乱させ違和感を残してしまうことだけでなく、物事を考える上で起きてはならない抜け漏れや誤りも招いてしまう。
人は物事を考える時に、一番わかりやすい具体的な事柄から入りがちになってしまうが、それこそが抜け漏れや誤りを招いてしまう要因である。
具体的なところから入るのではなく、与えられたテーマに対して大きな概念やレベルをベースとして、そこから徐々に粒度をかみ砕いていくことで抜け漏れや誤りを防ぐことができる。
また、大きな粒度から揃えることができれば、改めて文章の構成を見直す際に必要のない部分を取り除いたり付け足したりすることも可能である。
粒度を揃えるということは、スムーズな理解と抜け漏れや誤りのない情報を相手に伝えるためにも重要なプロセスである。
粒度の揃え方
粒度を揃えるために、まずは一番始めに「アジェンダ」を設定する。更に、アジェンダを設定する上で大切なポイントは、「起承転結」の流れを意識することである。
例えば資料作成の場合、資料にはストーリー性がない。
そのためアジェンダを設定しないまま進めてしまうとただの徒然とした文章になってしまい、内容の順番に混乱が生じ内容や解釈に抜け漏れ誤りが起きてしまう。
わかりやすく内容のある資料を作成するために「起承転結」を意識したアジェンダを設定し、アジェンダ毎に内容の厚みの粒度を揃えることを意識しなければならない。
「フレームに当てはめる」概念
粒度の揃え方として、起承転結という流れを意識したアジェンダの設定が必要であるが、流れは起承転結だけでなく「導入→プロセス→結論」や「結論→内容→補足」といった様々な「フレーム」がある。
フレームは多くの種類が存在する為、一概にどのフレームに当てはめるかは徐々に使い分けていくものであるが、とにかく重要なのは「フレームに当てはめる」という概念を持つことである。
フレームに当てはめるという概念がなければ、具体的な物事しか思い浮かばず、内容や解釈に抜け漏れ誤りが生じてしまう。
抜け漏れ誤りを無くすためにも、常に概念を持つ意識を持ち、自身の思考能力に繋げる努力が必要である。
感想
入社当初から「粒度」について個人的に苦戦していた課題の一つであり、粒度の言葉の意味自体は理解していたものの、その理解を業務に繋げることが出来ずにいた。
今回の勉強会においてまず初めに気付いたことは、粒度という言葉の意味だけを理解していただけで、粒度の揃え方や概念まで考えておらず、結局具体的な事柄を最初から考えてしまっていた。
また、資料作成にあたりなかなか思うように進まなかった時も、何がいけないのか分からず自分の能力や知識不足を理由にしていたが、そもそも自身が作成した内容の違和感に気付くことができず、改めて自分が粒度について理解ができていないことに気付いた。
何か物事を考える時に直接具体的なところを考えてしまっていたので、何事においても考え方のプロセスからきちんと考える必要があると改めて気付く機会となった。
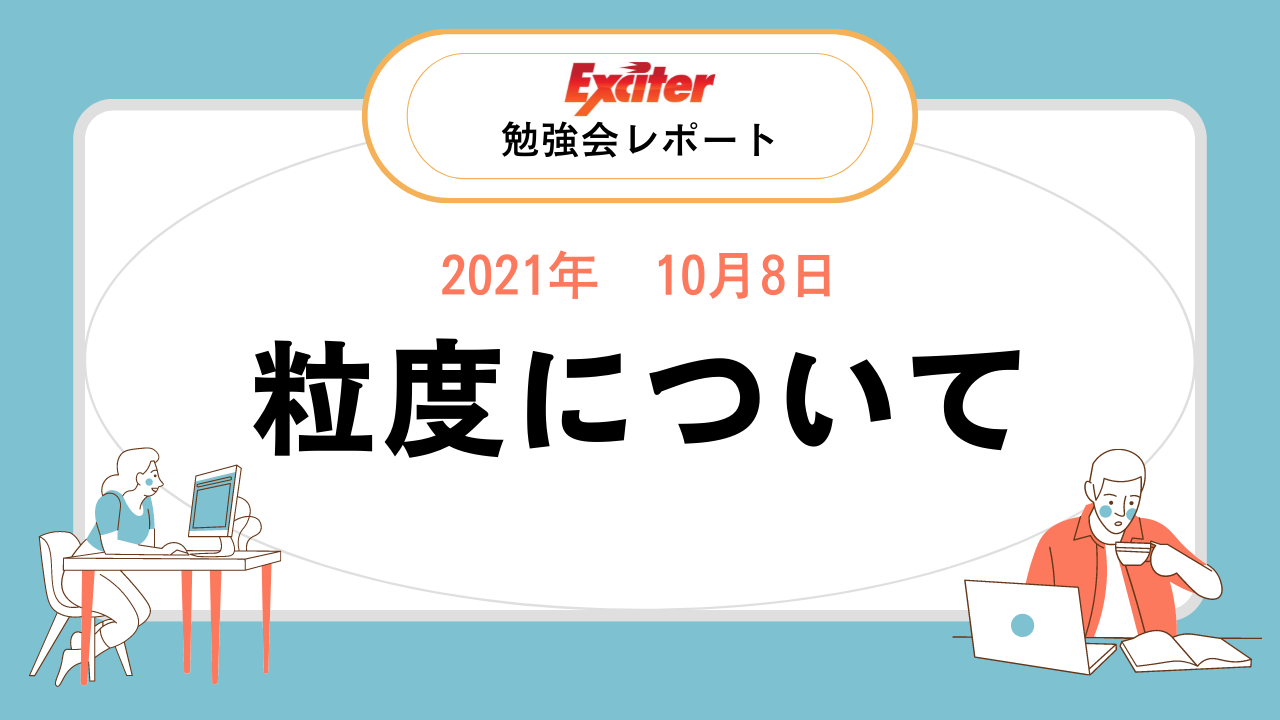
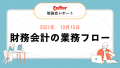
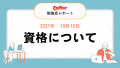
コメント