この記事では、初めて行った36協定の作成を振り返り、自身の反省点や今後同じような公的書類を作成・提出をする際の参考になるものとする。また、私のように初めて36協定を作成する人の参考になると幸いである。
なお、前提として弊社は社長と従業員が直属な関係にある小さな会社の話である。特に弊社のような小さな会社の方向けに偏る内容もあるため、ご了承ください。
36協定を作成することになったきっかけ
従業員が増えたから
36協定は役員には適用されないことが前提としてあるが、弊社はこれまでほぼ社長のみの会社であったため、36協定は必要ではなかった。また、その期間もアルバイトの従業員がいたことはあったものの、アルバイトは残業がなかったため、36協定の作成の優先度は低かった。
しかし、2023年8月から社員が2名増え、また社員は残業が起きるような業務も発生するため、36協定の作成・提出が必須となった。
弊社はシステム屋であり、残業の発生は必須であったから
弊社はシステム屋であり、サービス業であることから、残業は避けられない。そもそも残業を禁止とする会社であれば36協定の作成は必須ではないようだが、弊社では残業が避けられないことから作成・提出しなければならなかった。
作成にあたり取り組んだこと
情報収集
【そもそも36協定とは何か】
そもそも、36協定とは何かというところから情報取集が必要であった。社会人として耳にしたことのある言葉ではあり、残業に関する何か必要なもの、程度の認識でしかおらず、残業するには36協定が必須ということも知らなかった。
【36協定の条件】
まず初めの条件として、役員もしくは役員に相当する管理監督者以外の従業員が対象となる。ここでの注意点は、管理職と管理監督者は違うため、管理職の人は36協定の対象となる。(管理監督者とは、職務内容や権限が経営者と一体的な立場にある人や、他従業員と比較して管理監督者にふさわしい待遇がある人などのことをいう。「部長」や「店長」などは管理職と呼ばれるが、管理職が管理監督者にあたるかどうかは別の話である。)
以上から、役員で構成されている会社は必要ではないが、役員以外にも従業員がいる会社は36協定を作成する必要がある。(ただし、従業員の残業が必ず発生しないのであれば、作成する必要はない。)
36協定の具体的な内容としては、月45時間まで、年間360時間までの残業が通常の上限として定められているが、特別条項付きという、突発的に発生してしまう長時間労働に対応するための協定も存在する。また、特別条項付きでは連続2か月目以降の残業が発生する場合、月平均80時間を超えるような残業をさせてはならない、100時間未満の残業は年6回までしかできないなど、こまかい条件が課せられている。
残業に対して、労働基準法ではそもそも残業がないことを基本スタンスとして定められているため、36協定を結んだから自由に残業OKというわけではない。そのため、他にもこまごまとした条件が定められている。
会社の実体と条件を照らし合わせながら作成するためにも、条件はこまかくきちんと理解しておく必要がある。
【社労士事務所】
36協定の作成・提出と言えば社労士に依頼する会社も多いのではないだろうか。弊社は結果として依頼しないことになったが、最初は依頼も視野に入れていたため社労士事務所の情報収集も行った。
社労士事務所は検索してもキリがない数がヒットする。が、社労士事務所を決めるための情報収集に多くの時間はかけられない。そのためにも、情報収集するポイントは予め絞っておいた方がいい。
私の場合は、所在地と値段とプランに絞って検索した。というのも、多くの件数がヒットする中、真っ先に分かりやすい条件として思い浮かんだからだ。所在地についてはできるだけ会社と同じ区内(欲を言えば徒歩で行ける近所)の方が何か必要な書類や打ち合わせなどがある場合、何かと便利だと考えた。また値段とプランついては、弊社のように小さな会社だと高額の費用は避けたいためだ。
【36協定の作成方法】
36協定の様式は、含まれるべき内容が含まれていれば、必ずこれ、といった決まりはないようだ。ただし、弊社のように社労士に依頼せず自分たちで作成する場合、厚労省から無料でダウンロードできるフォーマットが用意されている。書き方の参考例も用意されているため、自分たちで作成する場合は厚労省の様式を使用するといいかもしれない。
※ただし、会社ごとに記載内容も異なるため、よりこまかい内容を定める必要がある場合は様式の変更か自作することをおススメする。
社労士への依頼検討
【社労士に依頼するかどうか】
社労士に依頼するかどうか、判断基準は会社によって異なると思うが、大きくは値段とプランを前提として検討する会社が多いのではないだろうか。
もちろん社内に専門知識を有する者がいる場合は必要ないかもしれないし、そうでない場合は依頼を前提として考えてしまう。しかしここでいったん考えてみてほしいのは、コスパだ。
私が調べた範囲内(東京都中央区付近)では、顧問契約であれば月3万~5万が相場であり、年間約30万~50万前後の費用がかかることになる。弊社の場合は36協定の作成・提出ぐらいしか社労士に依頼する内容がなかったため、年間にかかる費用を考えるとコスパは悪かった。また、スポットでお願いするとなると社労士事務所の数も限られてくるし、そもそも顧問契約を結ぶことが前提となるところばかりであったため、こちらも却下となった。
36協定以外にも社労士を必要とすることがあればいいと思うが、そうでない限りは弊社のようにできるだけ費用を抑えたいと考える会社は「36協定作成するから社労士だ!」という考えに直結せず、まずは36協定を調べてみて、そこから検討する方がよいのではないかと思う。
【最終的に社労士に依頼しないことになった理由】
厚労省の様式を見たときに、自分たちで作成できそうだと思ったからだ。もちろん専門知識はないため、実際提出したときにどんなポイントで見られるのかも分からない。ただし、申請が通らなかったらその場で指導を受けられるのかもしれないし、その際は修正して提出し直すだけのため、コスパを考えて自分たちで作成・提出することにした。
作成
【仮作成】
①まずは、会社の情報(会社名、所在地など)や現状など確実に分かっていることを埋める
②36協定の条件を考慮した内容を入力(このとき、自身の判断では決められないことも仮入力しておき、社長と確認できるように分かりやすくしておく)
③社長と話すための準備
→弊社の場合、恐い社長にレビューをお願いするため、何がどう分からないのか明確にしておく、分からないところと分かっているところが見やすいような工夫をしておくなど、入念に準備した。優しい恐いに関係なく、レビューしてもらいやすいような準備をしておくことも重要である。
【社長との認識合わせ、内容決定】
①自分が知っている確実な情報を社長に認識してもらう
→社長だからと言ってなんでも知っているわけではない。もちろん知識が豊富な人もいると思うが、大体の場合は「いい感じにやっといて」とか「なんかそんな感じでよろしく」スタンスな場合も多い。(特に弊社のような小さな会社にはありがち。)そのため、社長はこう思う、けど実際にはそうはいかない場合も多いため、まずは社長に確実な情報を認識してもらうことで、話しも進めやすくなる。
②作成担当者と社長がお互いに知っていること・知らないことの認識合わせをする
→レビューをもらっている最中で、互いの認識を把握しておくことも重要である。1から作ろうと思うと、特に知識0な場合、すべての情報を把握することは難しい。実は分かっていなかったことや、曖昧なことが必ず出てくる。36協定のように公的な書類は曖昧にできないため、ここで今一度認識を合わせ、さらに情報収集が必要なことや会社としての考え方を明確にする必要がある。
思い込んでいたこと
【社労士に必ず依頼するものだと思っていた】
専門知識もないので、社労士に依頼する方法がベストなことが多いかもしれないが、決して社労士に依頼しなければならないものではない。社労士を検討する前に36協定について知識を知っておくことが大切なため、36協定すなわち社労士、という考えはいったん置いておく方がいいと思う。
ただし、社労士に真っ先にお願いするという考え方がダメなわけではなく、お金に余裕がある会社やそもそも社労士を必要としている会社であれば真っ先に社労士を探したほうがいい。
【変形労働時間制は、フレックスタイムのようなものだと考えていた】
次項でも述べるが、変形労働制はフレックスタイムのようなものだと思い込んでいた。よくよく調べてみると違うことが分かり、変形労働制は別で協定を結ぶようだ。
会社にとって大切な協定なため、思い込みで進めてしまうと会社にとって不利益になったり、スムーズに作成・提出ができず無駄な人件費を使ってしまうことにもなりかねないため、少しでも疑問があったり断言して答えられないことがある場合は、必ずきちんと理解しよう。
よく分からなかったこと
【変形労働時間制】
年間の月事や四季ごとに、閑散期・繁忙期が明確にわかっているような業種・業態に対して、柔軟な働き方ができるようにする制度。
例えば、年賀状シーズンになると忙しくなるような印刷会社や郵便局などが分かりやすい。このような会社は冬に忙しく恐らく残業は避けられないため、冬は所定労働時間が長く、その代わりにシーズンが過ぎたら所定労働時間を短くして、年間の労働時間を調整することができる。
弊社としての考え方
弊社は規模が小さい少数精鋭のシステム屋である。そのため、部署や担当はこまかく分かれておらず、1人が複数の業務に従事しているため、業務によって細かく残業の上限時間を設定することは難しく、「その客先毎での対応」というざっくりした事由であることが多い。
また、システム屋は年間の四季や月毎に閑散期・繁忙期が決まっておらず、プロジェクト先の都合や予期せぬトラブルによって繁忙期が決まるため、変形労働制を採用することも難しい。
システム屋は自分たちの都合ではなくプロジェクト先の都合や突発的事由で残業が発生することも多いため、36協定の範囲内で突発的に起きる残業時間の設定は上限に設定した。しかしその分、残業に対するケアとしては連休などの待遇面でカバーできたらいいと考えている。
感想
想像したよりも難しかった。厚労省のフォーマットもあるし、参考例もあるから、社労士は頼らなくてもイケそうだなと思っていた。しかし、厚労省の参考例もほんの一例に過ぎず、また説明も分かりづらかったので、具体的にどんなときにどんな残業が発生するのか業態・業種ごとに違うとき、実際にはどのように記載するのか分かりづらかった。
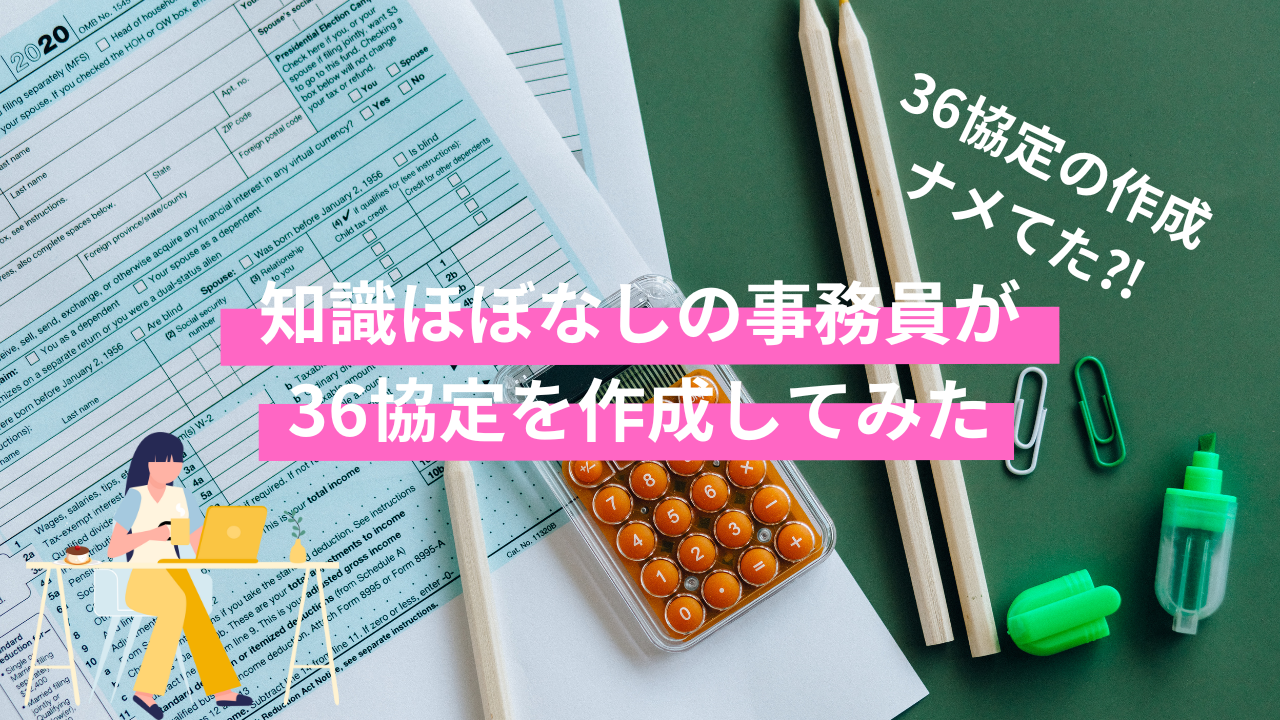


コメント