当レポートでは一般的な企業の組織の構成、およびその役割に触れ、組織の全体像について理解を深めることを目的として作成しています。
そのため、企業ごとの部門の有無や名称、担う役割は企業によって異なります。
また、部門ごとの業務を詳細に表すものではありません。
組織とは
企業における組織とは、企業が利益を創出し維持・発展するにあたり、その役割を分担する単位を指します。
当レポートでは、役割を分担する単位を部門と呼びます。
組織を理解する目的
基幹業務システムは、その名の通り導入先の基幹業務を取り扱うシステムであるため、業務の理解は必須となります。
そのためには、業務を行う者がどのような役割を担い、どのような作業を行っていくかを理解する必要があり、それによって業務間や組織間のつながりについてもイメージを深めることができるためです。
一般的な企業の組織
一般的には、企業の最上位には役員会・取締役会があり、その下に業務系の部門と管理系の部門という構成が多いため、それを前提として説明します。
役員会・取締役会
役員会・取締役会:企業としての経営意思の決定を行う最上位の組織です。
業務の内容:監督(企業自らが決定した意思決定に沿って適切に業務が行われているか)、決定(経営や業務遂行に関わる意思決定)、監査(経営が決められた通りの方向に進んでいるか)
業務系の部門
業務系の部門は、本業にまつわる業務を行う組織であり、営業部門、製造部門、調達部門があります。
営業部門:売上を生み出す組織。各部門が担う役割に優劣はないものの、企業の目的であり従業員の給与の源泉である利益の創出を行うため、特に重要な組織であると言えます。
業務の内容としては、営業活動、受注、モノやサービスのデリバリー、顧客への請求があります。
製造部門:販売するモノ(製品)を製造する組織。モノの製造・生産管理(どれくらいモノを製造するか管理)・品質管理(製造したモノの品質を管理)などを行います。
調達部門:モノやサービスを外部から調達する組織。仕入先への見積依頼、他部門からの購買依頼の受け付け、社外への発注などを行います。
管理系の部門
管理系の部門は、企業の本業に関わる業務ではなく、企業を維持・発展させるための業務を行う組織です。
直接的な利益貢献はないものの、企業活動においては無くてはならない縁の下の力持ち的な存在であり、経理部門、人事部門、総務部門、IT部門があります。
経理部門:会計にまつわる業務の一切を行う組織であり、外部への報告を目的とする財務会計、経営管理に特化した管理会計、キャッシュの過不足を管理し資金調達を行う資金管理などを行います。
人事部門:従業員にまつわる業務の一切を行う、全組織のヒトを管理する組織です。
従業員管理(採用、入社手続、退社手続、トラブル対応)・人事評価・給与計算などを行います。
総務部門:企業活動が適切に行えるよう各組織を補佐する役割を担う組織です。
備品管理、オフィスの管理、什器管理などを行い、各組織の業務から漏れてしまいがちが業務を行います。
IT部門:情報技術に関わる全般を担う、近年においては必要不可欠な組織です。
各種システム、ハードウェア、ソフトウェア、IT資産管理(システムなど固定資産の管理を含む)などにまるわる企画・導入・保守・運用を行います。
- ITによって実現できる領域は非常に幅広いため様々な部門に関与します
役職
指揮命令系統を明確化し、担う責任を切り分けるため、役職を定めます。
役職の定めには、会社法という法律に基づく役職と、企業が任意に定める役職があります。
法律上の役職:代表取締役、取締役、監査役
- 法律上は役員と従業員という立場に分かれ、役職は役員にのみ存在します。
- 株式会社と合同会社など、企業の形態により名称は異なります。
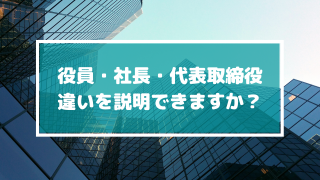
企業が任意に定める役職:社長・CEO・CFO・CIO・副社長・部長・課長・主任・チーフ
- 企業は、法律によらず任意に役職を定めることができます。
- そのため、同じ役職であっても、企業によって上下関係が異なる場合があります。
まとめ
企業は維持、発展を目指し、部門という単位で役割を担い日々の業務を行っています。
組織の在り方は企業によって異なりますが、一般的な企業においてはこのように構成されています。
冒頭で、良いシステムを構築するためには業務と組織の全体像を理解することが不可欠であると記述しました。
特に、我々のようにSAP(基幹業務システム)を扱う者にとっては、企業の全体像を理解することは大切です。
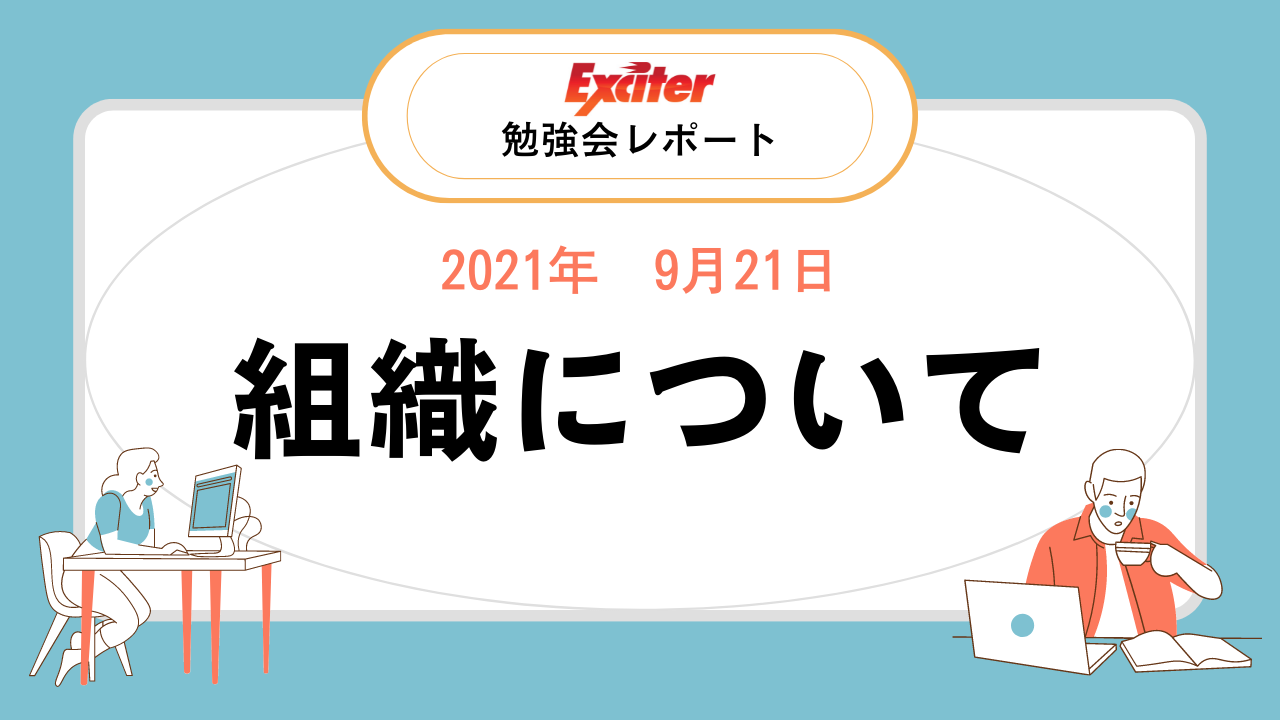


コメント