このレポートは9/24と9/28に行われた勉強会「在庫管理の代表的なフロー」についてのまとめと感想である。
今回は「入荷指示」「出荷指示」「棚卸」「在庫移動」「廃棄」について。
在庫管理おさらい
在庫管理とは、原料・半製品・仕掛品・製品など「在庫」として分類されるモノに対して適切な管理をいう。
その業務には、入荷指示・出荷指示・棚卸・在庫移動・廃棄などが含まれる。
この在庫管理によって生産・販売・購買の業務へとスムーズにつなげ、さらに売り上げや販売目標設定などの会計の業務に関係する。
また在庫というのは会社の資産・資源にあたるため、適切に管理することが重要である。
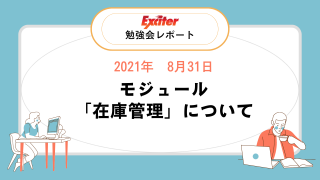
入荷指示
入荷とは在庫を管理している倉庫に原料・製品など何かしらのモノが届くと指示が入り、物を受け取ること。
トリガーは出荷元。出荷元が発注・在庫移動・返品などの依頼を受けたことにより発生する。
出荷元の業務発生と同時に担当者にも入荷が発生し、入荷先に伝える。
入荷先は担当者からの指示の内容を確認し、出荷元から送られてきたものを受領し、担当者からの指示と差異がないかの確認のため検品・検収を行い、間違いがなければ正しく受領したことを担当者に伝える。
担当者は受け取った入荷連絡をもとに、請求や返金処理・販売などの後続業務に移行する。
出荷指示
出荷とはモノやサービスのデリバリーを指す。その工程には様々な業務が存在する。
出荷指示のトリガーは担当者の先行業務。
顧客からのオーダーに対する出荷や、仕入れた在庫が不良品だった場合の返品出荷、在庫移動など内容は様々。その内容を元に出荷元に対して出荷指示を出し、その内容を確認。
その後ピッキング、パッキング、積載、出庫、出荷通知とつながる。
通知を受けた担当者は内容を確認し後続業務へと移行する。
入荷先は届けられたモノがあっているかの検品・検収を行う。
その後続業務は先行業務の内容により、顧客からのオーダーであれば請求、返品出荷であれば返金請求、在庫移動であれば入荷となる。
棚卸
棚卸とは倉庫や保管場所にある原料や製品などの在庫に対して、本来あるべき帳簿上の数量と実際の数量が合致しているか現状確認を行い、是正を行うこと。
目的は所持している在庫を正確に把握するためだが、その原因分析と対応も併せて行うことにより統制を強化し不正の防止を図ることもある。
さらに在庫は現金から形を変えた会社の資産にあたるため、決算上も必要な業務である。
棚卸は期日の到来がトリガーとなり、年次・半期・四半期・月毎と定めたタイミングで定期的に行う。
回数や頻度は会社によって様々。
業務の際は帳簿在庫(システム在庫)を元に行われる。
帳簿在庫というのは本来あるべき在庫の個数が記録されたもの。
帳簿に対して実体の個数を数え、間違いがないかを確認する。
今回のフローでは倉庫が行っているが、担当者や営業部門、経理部門が行う場合もある。倉
庫からの棚卸結果をもとに、担当者は報告書を作成する。
この業務も、経理部門がやる場合がある。
報告書には棚卸実施日・原料や製品の名称・コード・数量などを記録する。ま
た帳簿と実際の在庫の数にずれがあった場合は原因を記録し、承認に入る。
上長の承認が得られなければ再度棚卸や原因究明を行い、承認を得られたのち、帳簿に反映し棚卸の業務は終了となる。
*在庫の数が合わないというのは、帳簿の記録が間違っているか、実体する在庫の数が間違っているかのどちらか。
在庫移動
在庫移動とは倉庫間で製品などの移動を行うこと。
トリガーは担当者のもとで発生した移動事由。
倉庫の在庫が十分に確保できないときや、出荷の多い倉庫に在庫を移動させるなど理由は様々。
その後、移動元に対し出荷指示を出し、移動元はその指示を元に移動先に対し入荷指示を出す。
移動元は指示を受けたモノを出荷するために、ピッキング、パッキング、積載、出庫と出荷のための処理を行い、出庫報告をする。
移動元はモノを受け取ったのち担当者へ報告。
担当者は移動元の出庫報告、移動先からの入庫報告を確認し、在庫移動の業務終了となる。
*入荷指示は移動元が行っているが、担当者が行う場合もある。自社保有の倉庫でない、業務として担当者が行うなど、理由は様々。
廃棄
廃棄業者に依頼し、在庫として持てなくなったモノを処分してもらうこと。
担当者のもとで発生した廃棄事由(破損・汚損・不良品・製造過程でのミス・人体に影響のある有害物質の処理など)がトリガーとなる。
廃棄は隠ぺいや横流しなどの不正につながる可能性もあるため承認が必要。
上長の判断により在庫としての価値がまだ残っている場合や、廃棄に経費を掛けられないなどの理由によって承認が下りないこともあり、その場合は廃棄業務終了(延期)となる。
承認が下りた場合は、廃棄業者に見積もりを依頼、受領したのち廃棄のための手続きへ移行する。
この手続きには、責任もって廃棄業者が処分するという契約の意味も含まれる。
手続き終了後、廃棄業者が倉庫から廃棄品回収し、廃棄を行う。
この時点で保有していた在庫は失われているため、担当者は出庫処理を行い帳簿の数を合わせる。
廃棄を行った業者は請求書を発行し、担当者は支払いフローに移行していく。
廃棄と不正防止
担当者が価値ある在庫に対し廃棄処理を行い不正な横流しや横領をする場合や、業者が回収した廃棄品を廃棄せずに不正に利用するなどの理由がある。
上長の承認が必要であるのは在庫の市場価値を改めて選定し正しいかどうか確認するためや、業者に責任もって廃棄を行ってもらうため契約や廃棄証明の取り交わしを行う。
商品廃棄損
商品を廃棄した際の損失額。在庫減らすことで費用が発生してしまい利益が減ること。
まとめ
在庫管理という業務がモノの動きについてであるため、イメージがしやすいことから、より業務の本質というものを理解しやすくなると感じた。
今回のフローはあくまで一例であり、例えば登場人物に変化があった場合に処理がどこで行われるのか、追加処理や、次につながる業務が何であるのかなど、色々なパターンを考えながら取り組むことが大切であると思う。
入荷指示や出荷指示の先行業務も発注・在庫移動・返品など様々な理由が存在するし、棚卸も流れは同じでも業務を担当する人が異なる場合にどのような仮説を立てることができるのか、コンサルタントとしてどのような思考を持ち、振舞うのかが大事であり、今回の業務フローをただ覚えるのではなく、基本的な流れとともにさらに何が必要なのかなど考えられるようになることが重要だと思われる。



コメント