自分が小学生時代にサッカーを始めたことやサッカーをやっていて成長したことや学んだことなどを体験記として記したものです。
自分が小学生2年生の頃は2006年で今から15年前の話になりますので、多少記憶が薄れている部分がありますが、記憶の範囲内で紹介していきます。
サッカーを始めたきっかけ
自分が小学2年生の時、大阪の地元に小学生対象のサッカークラブが出来た際に、「友達がサッカークラブに入ってサッカーをやるみたいだから一緒にサッカーをやってみないか?」と親から言われたことがきっかけでサッカーを始めました。
主な活動内容
平日は全学年、水・金曜日放課後の約1時間の練習があり、土日祝は学年ごとに活動内容が変わり、学年が上がるにつれて試合や大会の頻度が上がります。
例えば1,2,3年生は練習、4,5,6年生は試合に行くなど学年ごとにその時の活動内容が変わってきます。
もちろん1,2,3年生の試合が無い訳ではなく、その学年のみの試合なども開催されることもありました。
活動場所は練習を基本的に自分たちの通っていた小学校のグラウンドを使わせていただき、試合や大会などは遠方の公共グラウンドで行なったり、自チーム開催のものであれば、近隣のグラウンドで行われたりすることもありました。
下記の表は学年ごとの週間スケジュール例です。(空白部は休みの週です)
あくまで週のスケジュールの一例なので暦によって変動はあります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1年 | 小学校での練習(16:30~17:40) | 小学校での練習(16:50~18:00) | 小学校でのミニゲームデー(自由参加の試合形式での練習9:00~10:30) | ||||
| 2年 | 小学校での練習(16:30~17:40) | 小学校での練習(16:50~18:00) | 小学校でのミニゲームデー(自由参加の試合形式での練習9:00~10:30) | ||||
| 3年 | 小学校での練習(16:30~17:40) | 小学校での練習(16:50~18:00) | 自チーム開催の交流試合 | 小学校でのミニゲームデー(自由参加の試合形式での練習9:00~10:30) | |||
| 4年 | 小学校での練習(16:30~17:40) | 小学校での練習(16:50~18:00) | 自チーム開催の交流試合 | 小学校でのミニゲームデー(自由参加の試合形式での練習9:00~10:30) | |||
| 5年 | 小学校での練習(16:30~17:40) | 小学校での練習(16:50~18:00) | 自チーム開催の交流試合 | 交流試合(大会相手との練習試合etc.) | |||
| 6年 | 小学校での練習(16:30~17:40) | 小学校での練習(16:50~18:00) | 自チーム開催の交流試合 | 大会(〇〇カップ予選、××リーグ etc.) |
特別な活動内容
合宿
自分の所属していたクラブチームでは夏休みや冬休みなどの長期休暇に入ったタイミングで合宿としてチーム全体で遠方へ泊まりがけの練習を毎年行なっていました。
毎回の合宿では、コーチ陣が練習風景や遊んでいる風景を写真や動画で撮ったものを編集し、DVDにして合宿日の翌週に渡してくれました。
いつもそれを親と見るのがとても楽しみでした。
合宿では集団行動についても教わりました。
チームメンバーと数日を過ごすことで団結力が深まりよりいっそうチームとしての繋がりが強くなっていったように思えます。
合宿を通して親がいない環境で生活をするので、自己管理能力や基本的な人間力を培う場としてもとても効果のあるものだと思いました。
何十名かで合宿に向かうので、合宿所についた後に部屋ごとに人数を振り割られるのですが、そこで行われる部屋のメンバー分けの時が毎回誰となるか分からない楽しさがあって面白かったです。
同学年のみで部屋に固まるのではなく、他学年とも一緒になるように振り割られていました。
その部屋のメンバーで3食の食事を行ったり、朝のランニングメニューなどを一緒に行ったりなど、低学年は高学年を見本にして、高学年は低学年の見本になるように行動しなくてはいけないので、ある程度自律的に学んでいける環境を整えられていました。
クリスマスサッカー
クリスマスの時期になると毎年クラブがイベントを開催し、特別なプレゼントがもらえるミニゲーム大会(サッカーの練習に遊び要素やおもしろ要素を加えたようなもの)や、選手全員が各自プレゼント(基本的には駄菓子などの詰め合わせ)を用意し、それらを大きな袋に入れて行うプレゼント交換会など選手が楽しめるような企画を行っていました。
サッカー歴の振り返り

4年生:サッカーが嫌になる
中学年の4年生になると良い評価をもらっている選手は高学年の練習や試合に入ることでき、逆に良い評価をもらえていない選手は低学年や中学年の練習や試合に行くことになり、そもそも高学年とは一緒に行動をできなくなります。
自分は後者の中の一人でした。
同期のメンバーが高学年に混じってサッカーをしているのに自分は混じれていないことにモヤモヤを感じていたことに加え、コーチからの厳しい指導により、練習などに行くことに憂鬱な感情になってしまい、数週間ほど、サッカーに向き合うことが嫌になった時期がありました。
その当時、気持ちを親にぶつけたところ「嫌なら行かなくていい」というようなことを言われ、その言葉に甘え、練習を何度か休んでいました。
自分は親に怒られると思っていたのですが、親はその気持ちを許容して否定もせずただ見守っていてくれました。
自分が自主的に行動を起こせるように促してくれていたおかげで、その後はサッカーを嫌にならずに続けることができました。
その時に怒られていたら自分はサッカーを辞めていた可能性を考えると、親の行動には感謝しています。
5,6年:急激な成長期
自分は5、6年の時に急激な成長期で身長が1年で10センチ以上伸びていました。
その反面、サッカーをしていく上でも影響があり、急激な成長期の最中は体がうまくコントロールできず、サッカーを十分にプレーできませんでした。
過去の経験をもとに調べてみたところ、この現象は『クラムジー』と呼ばれるものだということがわかりました。簡
単に説明すると、体の急激な成長に脳が追いつけず、体のコントロールがうまくできなくなるというものです。
この時期は夜も眠れなくなるぐらいに体の節々に慢性的な痛みが続いていたのをよく覚えています。
特に自分は腰の痛みがひどかったです。
湿布やエアーサロンパスなどを使用しても全く効かないので、その時期はずっと痛い痛いと苦しみながらながら寝ていました。
その時期は夜眠っている時によく『高所から落ちる夢』というものを見ることがあったのですが、高所から落ちる夢というのは、寝ている間に身長が伸びていると教えられていたのですが、実際に調べてみたところそのような証拠はありませんでした。
ただし、そう言った夢を見た時は心と体のバランスがまだ不安定な状態である可能性があるそうです。成長期は身体が成長しているのに脳はその成長に追いついていないということに繋がっているようにも思えるので、この夢と成長期の関係は直接的でなくとも何か繋がりはありそうです。
そういう夢を見るくらいに心身共にストレス感じていたのだと思います。
6年生:地区大会での優勝経験
2年生で入った自分が6年生になった時、クラブとしては設立5年目となっていました。
それまでたくさんの勝利した試合はあったものの、歴代の先輩方の年代も含め、公式な大会で優勝したことがまだありませんでした。
地区6年生大会で自分たちが戦っていたトーナメントで決勝まで勝ち上がり、最後の試合を勝てば優勝というところで強豪とされていたチームと対戦しその試合を1点差で勝利し、優勝を納めることができました。
その時のチーム一丸となって戦っていた空気感や最後まで気を抜けない緊張感が今でも忘れられません。
コーチ陣としても、選手たちにしてもその優勝がクラブ初タイトルであったので、その時は本当に嬉しかったです。
サッカーを通じて得たもの

同期のメンバー
同期のメンバーはクラブ設立された当初は自分の通っていた小学校の5人だったのですが、徐々に同じ小学校のメンバーや近隣の小学校からのメンバーも加わり、最終的な人数は15人になりました。
チームメンバーは学校でもよく校内で集まって遊んだり、自分たちでお昼の休憩時間などに自主的にサッカーの戦術についてミーティングをしたり、時には、練習のない平日の放課後に何人かで集まってサッカーの練習をしていたくらいに仲が良かったです。
なので、サッカーを通してできた友達は今も繋がりのあるメンバーは多いです。
卒団後の中学生時は、自分たちのクラブチームには中学生チームがまだ出来上がってなかったため、他のクラブチームに加入するメンバーや、中学校の部活としてサッカーを続けるメンバーが多かったです。
今は自分たちのクラブは中学生チームができて活動しているのですが、もし過去に中学生チームがあれば、同期のメンバーと中学生になっても一緒にサッカーを続けたかったです。
公共交通機関での移動マナー
試合当日は移動手段の一つとして、公共交通機関を使うことが多かったのですが、そこでは電車内でのマナーやバス内でのマナーを教わりました。
例えば、サッカーをしに行くので、各々がある程度大きな荷物を持っていることになります。
その荷物を身につけたままでいると車内で他のお客さんの邪魔になります。
なので、車内では荷物を身につけずに足元に置くことなどをして邪魔にならないようにと教わってきました。
さらに小学生の集団組織となると、車内で周りを気にせず喋ってしまう可能性があります。
そういうことがないようにコーチから指導を受けていました。そ
ういった周りの人に配慮して行動するということを教わるなど、今後の社会に対しても通ずるマナーを知ることができました。
実際に中学生になった人であってもこういう行動を取れる人は多くはないので、公共マナーを小学生の内から学んだことで、その後生きていく中で重要な糧になりました。
小学生サッカーにおいてのメンタル的成長
小学生の自分の性格はとにかくマイペースでした。
クラブのコーチには「その性格は自分の良い部分だ。」と言われていました。
ただその性格における影響は大きく、団体競技であるサッカーにおいて自分のペースだけでの行動は致命的でした。
パスをすることに相手がいるようにサッカーではマイペースにプレーをすると相手にも影響が出てしまい、失敗が続く一方でした。
そこで自分が学んだことは他人のペースを知り、そのペースに合わせるということです。
そこで起こった成長はサッカーをする上での大きな成長となりました。
もちろんサッカー外においても同じく、他人と会話をする、他人と行動するなど、他人に気を配って行動することが少しはできるようになり、サッカー内外での成長がありました。
小学生時におけるサッカーと勉強の両立について
週4日でサッカーをしていく中で、自分は小学校の勉強に関しては基本的な内容のものが多く、授業を聞き、宿題をやることで、ある程度の成績が取れていました。
なので、小学生時代のサッカーと勉強の両立はあまり苦では無かったです。
練習の厳しさは?
4年生以降の練習は本当に厳しいものでした。
当時体罰などの行為があまり表立って問題視されて無かった時期でしたので、体罰に当たるようなことで指導をされていた時もありました。
例えば、ミスをするとコーチが紐付きのホイッスルやバインダーで頭を叩きつける、身体的にダメージが起こるようなことで指導されていました。
今そのような指導をすると、とてつもなく問題になりますが、そのような指導があったからこそ、チームとして強くなれたのだと思います。
小学生時代でのサッカー経験のまとめ

2年生から6年生までやり抜くことができたという経験はその後の何があっても諦めない心や途中で投げ出さない心の糧となったような気がします。
入団から卒団までを経験し、何かを達成するという気持ちを体験できたことはとても素晴らしいことだと知ることができました。
その後の人生において小学校でサッカーをしていたことは他のサッカーなどの団体競技をしていない学生に比べると、社会的なマナーや礼儀などのアドバンテージを持って中学生に上がれたことは大きな経験だと思いました。
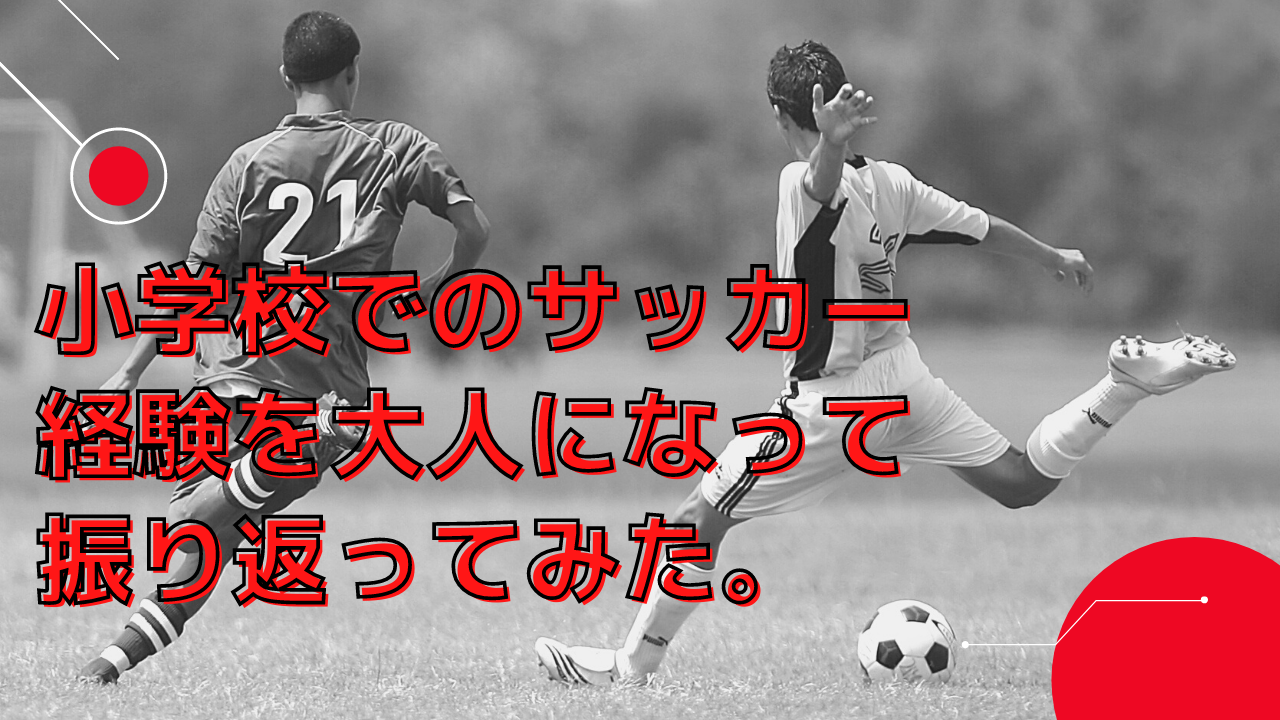
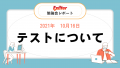

コメント