この記事は高校生の時に2回、大学生の時に1回、ホストファミリーを経験した私が、その楽しさや大変さをお伝えするものです。
ホストファミリーをやってみようか悩んでいる人はもちろん、初めて「ホストファミリー」という言葉を聞いたという人にも楽しんで読んでいただける内容になっています。
ホストファミリーとは
まず、主に留学生が留学先の一般家庭で、その家族の一員として生活する仕組みのことを「ホームステイ」と言います。
そして、ホームステイにおいて、留学生を受け入れる側の家庭のことを「ホストファミリー」と呼びます。
ホームステイでは留学生をお客様として扱うのでなく、家族の1人のように接するのが特徴です。
ステイ期間は数日間から長いものだと年単位まで様々です。
ホームステイによって留学生側は留学先の文化を学んだり、安心して生活を送ることが出来ます。
また、生活費が安くなる場合もあります。
受け入れる側のホストファミリーには、異文化を学べたり、語学の練習ができるというメリットがあります。
ホストファミリーになるには?
ホストファミリーになる方法は大きく分けて2つあります。
学校での募集に応募する
私の場合は、自分が通っていた高校経由で2回、他大学の経由で1回でした。
現役学生の方でしたら、まずは自分の学校でホストファミリーを募集していないか調べてみるのがオススメです。
また、一般からホストファミリーを募集している大学や日本語学校などもあるので、近所の大学などでそのような取り組みがないか調べてみても良いかもしれません。
ホストファミリー仲介組織に応募する
学校以外にもホストファミリーを募集、仲介している組織はあります。
「ホストファミリー 募集」で検索をしてみると、多くのサイトがあります。
例えば以下のような仲介組織があります。
その他
他にも、稀にSNSなどで個人的にホストファミリーを探している留学生がいる場合があります。
これはあくまで私の意見ですが、仲介などが全く無い場合、トラブルが発生した時に問題が大きくなる恐れがあるため、留学生の身元を証明し、トラブルなどの際はきちんと対応してくれる組織を利用することがオススメです。
また、前述のホストファミリー仲介組織を利用する場合も、問題が発生した際の対応が定められているかを確認し、安心して受け入れられるところを選ぶと良いでしょう、
ホストファミリーの条件

ホストファミリーになるための条件は、仲介組織や留学生の属性などにより様々です。
主にどのような条件があるかをご紹介します。
家族構成
条件がある場合は、子どもの有無、子どもの年齢、性別が条件となることが多いです。
もちろんホストファミリーになるためだけに家族構成は変えられないと思うので、これに関しては、自身の家族構成に合った募集を見つけることで対応しましょう。
また、私は3回のホストファミリー経験で一度だけ両親のバックグラウンドチェック(犯罪歴確認)を受けたことがあります。
あまり良い気はしないかもしれませんが、留学生の安全担保のためですので、求められたら快く受けることをオススメします。
部屋について
部屋については、1人部屋が条件になっている場合もあれば、同性との同室は可能な場合もあります。
私はこれまで同性の留学生を3人受け入れていて、そのうち2回は私と同室で過ごしてもらいました。
数ヶ月などステイ期間が長い場合は1人部屋が条件になることが多いと思います。
つまり、長期でなければ、1人部屋を用意できなくてもホストファミリーになれる可能性は大いにあります。
家の立地
ホームステイする留学生は、日本で学校に通う予定だったり、何かしらのプログラムに参加する場合が多いため、通う学校やプログラムが行われる会場へアクセスが良いことが条件になることが多いです。
そのため、ホストファミリーの募集を探す時は、近隣に大学などがあれば、まずはそちらを確認しみると良いと思います。
食事
次に食事ですが、朝夜はホストファミリー側で用意する場合が多いと思います。
ただ、ホームステイの留学生はあくまで家族の一員ですので、日常通りの食事で問題ありません。
一方で、日本の家庭料理が口に合わない可能性はあることを心に留めておく必要はあるでしょう。
また、宗教的な理由、アレルギーなどで食事に制限がある留学生もいます。
以前私が受け入れた留学生の1人に、ペスカタリアン(魚介類は食べる菜食主義者)の子がいました。
こういった制限は募集条件にも書いてあるはずですので、それを見て対応が可能そうか検討しましょう。
何も記載がなくても、食事に関する制限は負担が大きめなので、事前に確認しておくと安心です。
言語
留学生ということで、日本語が不自由、または全く話せない学生もいます。
そのため、ホストファミリーにも、留学生の母国語や英語の能力が求められることがあります。
留学生の母国語が英語でなくても、英語でコミュニケーション可能という学生は比較的多いでしょう。
また、募集の条件になくても、毎回のコミュニケーションで翻訳機が必要となるとストレスがかかります。
ですので、ネイティブレベルのペラペラである必要はなくとも、日常の会話が出来るぐらいの英語力を身につけておくと自信をもってホストファミリーに臨めるでしょう。
実際私が初めてホストファミリーをしたのは高校1年生の時で、英語がペラペラには程遠かったですが、同年代の留学生の子と、とても楽しい時間を過ごせたので、過度に心配する必要はないと思います。
家庭のルール
家庭のルールが募集の条件になることはあまり無いかもしれませんが、重要なルールは事前に伝えると、留学生側も安心しますし、トラブルを防げると思います。
例えば門限や、夜の騒音、友達を家に呼ぶことの禁止などがあります。
日本人にとっては当たり前のことでも、文化による違いがあるので、言語化して伝えることが大切です。
ホストファミリーとお金

ホストファミリーをする際の金銭面について、大きく分けて3パターンあります。
まずは、受け入れに際する留学生の食費や滞在費として、お金が支給されるパターンです。
額は、気持ち程度の少額であることも、十分すぎる額のこともありますが、もちろんお金を稼ぐ目的でホストファミリーをするのは推奨されません。
私のこれまでのホストファミリー経験3回のうち1回では支給がありました。
次に、全くお金の支給はないパターンです。
私のこれまでのホストファミリー経験3回のうち、あとの2回はこのパターンで、完全ボランティアでした。
最後に、ホストファミリー側が仲介組織にお金を払って、受け入れるというプログラムもあります。
募集サイトにホストファミリー登録を行う際に、登録料いくらという場合もあります。
これらのパターンに加え、どこまでホストファミリー側がお金を出すかは事前に確認しておく必要があります。
例えば食費についても、用意できずに1人で外食してもらう時はお金を渡すか、一緒に出かける際の費用は払うべきかなどです。
楽しい話ではないかもしれませんが、金銭面はトラブルやストレスにもつながりやすいので、きちんと決めておくと安心だと思います。
私のホストファミリー歴
私はこれまで、高校1年生の時にアメリカ人の女の子、高校3年生の時にフランス人の女の子、大学2年生の時にクロアチア人の女の子を受け入れています。
いずれも同年代(自分と歳の差0〜2歳)で、期間は10日〜2週間程度です。
また、自分が大学生の時に、高校生の妹を中心にアメリカ人の女の子を受け入れたこともありました。
やはり一度経験すると、家族も様子がわかって受け入れのハードルが下がったような気がします。
最初に受け入れる時は、自分も家族もドキドキでした。
ホストファミリー生活はどんな感じ?

高校生の時、大学生の時共通で、家の中では「自分の家だと思ってくつろいでね。冷蔵庫の飲み物や、棚のスナックは自由に食べていいよ。」と伝えていました。
特に家を留守にすることはなかったので、家の鍵は渡していません。
洗濯物は、家族とは別に、留学生の子と私の分で洗濯して、2人の部屋に干していました。
普段はリビングに干しているのですが、さすがに異性である父の目に付く所に、下着などを干すのは嫌かなと思っての配慮です。
高校生の時
高校生の時は、私の通う高校にプログラムで来ていたので、平日は電車で一緒に高校に行って、帰りも一緒に帰っていました。
私はバドミントン部に所属していたのですが、ホストファミリー期間は部活を休むこともありました。
そして週末は、一緒に観光地を巡ったりしました。
留学生も高校生だったので、基本的に1人での外出は禁止で、私か、他の家族との行動です。
高校の友達と一緒に出かけることもありました。
1回目の受け入れの際は、経費としてお金を受け取っていたので、外食の時や、観光地の入場料なども全てこちらで払っていました。
2回目の時は、お金を受給していませんでしたが、特にすごくお金がかかるような場所には行かなかったので、基本的にはこちらで負担していました。
もし本人が入場料の高いテーマパークなどに行きたがったら、「入場料は〇〇円で、自分で払ってもらうけど大丈夫?」という感じで確認していたと思います。
食事は、朝夕は家で家族と食べて、昼は私と学食で食べたり、コンビニで買ったりしていました。
もちろん外食することもありました。
1人は日本食も割と得意で、困ることはほとんどありませんでしたが、もう1人は前述したペスカタリアンだったので少し工夫が必要でした。
部屋は私と同室で、消灯時間も私に合わせてもらっていました。
もちろん「この時間でいい?」と確認はしていますし、電気を消した中でスマホをいじったりは出来る状況でした。
大学生の時
大学生の時は、他大学のプログラムに参加している留学生の受け入れだったのでプログラムに参加する日と、ホストファミリーと過ごす日のスケジュールが事前に決められている形でした。
プログラムの日には、その大学の担当学生がステイしている私の家の最寄駅まで迎えに来てくれて、帰りも送ってくれたので、基本的に私は最寄り駅まで一緒に行くだけでした。
プログラムの無い日は、私や家族と出かけたり、他の留学生も一緒に観光したりして過ごしました。
高校生の時は毎日学校でも家でも一緒だったので、それと比べるとかなり自立度が高かった印象です。
基本的には運営大学の担当学生がついてくれていて、私ともやりとりしていたので、あまり不安などはありませんでした。
部屋は普段家族が使っている部屋をその期間だけ空けて、1人部屋を用意しました。
ホストファミリーの際に気をつけていたこと

ここからは、私がホストファミリーをした際に意識していたことや、気をつけていたことです。
留学生の受け入れに「これが正解」というのは無いと思いますが、参考になればと思います。
事前のやりとり
まずは、事前のやりとりをきちんと行うことです。
受けれいる側にも不安はありますが、外国で知らない人の家に住む留学生はもっと不安です。
日本の気温や物価など必要な情報を伝えるのはもちろん、趣味の話や、日々の出来事についてなどのメッセージのやりとりも、多めにしていました。
事前にビデオ通話をしたこともあります。
このやりとりで、留学生の子が日本のどんなものに興味をもっているかや食の好みなどがわかるとこちら側の計画にも役立つので、聞いておくのがオススメです。
家族の一員だけどやっぱりゲスト
特に2週間程度の留学生受け入れで難しいのが、どこまでゲスト扱いするかということです。
もちろん家族の一員として接する姿勢は大切ですが、やはり留学生側も他人の家庭で急にリラックスして振る舞えるわけではありませんので、遠慮しないように配慮はしていました。
例えば、「お菓子いる?」とか「無理して食べなくていいからね!」というのは積極的に言うようにしていました。
一方で、留学生の子が料理やお皿洗いをしてくれると言った時は、断らずやってもらっていましたし、部屋の掃除などは手伝ってもらっていました。
お互いに気持ちよく過ごせる加減を見つけることが大切だと思います。
また、ウェルカムパーティをしたり、週末の計画を立てたり、日本のお菓子を色々買っておいたり、食事を工夫したりと、喜んでもらえるように色々な準備はしました。
もちろん無理をする必要はありませんので、ホストファミリー側も楽しみながら過ごせることが重要だと思います。
プライベートの確保
日々一緒に過ごす中でも、やはり1人の時間は必要だと思うので、プライベートの確保には配慮していました。
高校生の時は私と同室だったので、例えば食後に私がリビングで過ごす時でも「戻りたかったら部屋に戻っていいからね」などと伝えるようにしていましたし、そういう時は私は意識的にリビングで過ごして、留学生の子が1人の時間を過ごせるようにしていました。
もちろん部屋に入る時はノックをして、返事があってから入ります。
また、私の家のお風呂には鍵がなかったので、「使用中」的なかけ札を作っておいて、安心してお風呂を使えるようにしていました。
丁寧な説明
最初に家に来た時は、色々なことを丁寧に説明しました。
入ってはいけない部屋、自由に食べてよいもの、トイレの流し方、お風呂のシャンプーやボディーソープ、洗濯のこと、コンセントの位置、電気の消し方、Wifiのパスワードなどです。
何を説明するかは、事前にリストを作っておきました。
初めての異国の家庭でわからないことがたくさんあるので、わかりそうなことでも一応説明するようにしていました。
たくさん話す
これは当たり前のことかもしれませんが、とにかくたくさんコミュニケーションをとるようにしていました。
自分の語学力で表現しきれないこともありましたが、わからない単語は調べたりして、諦めずに伝えることを意識していました。
日本に関してよく聞かれることなどは、事前にどうやって説明するか考えておいたりするのも有効です。
また、英語が堪能でない家族とも仲良くなれるように、自分が間に入って訳したり、留学生の子に日本語を教えたりもしました。
ホストファミリーをやってよかったこと

ホストファミリーをやってよかったと思うことはたくさんありますが、その中でも大きなものを3つお伝えします。
家族が増えた
ホストファミリーをすると、留学生と寝食を共にし、その期間の長い時間を一緒に過ごすこととなります。
その感覚は友達というよりも、家族に近い感じです。
家族は言い過ぎだとしても、仲の良いいとこぐらいの距離感になります。
受け入れ期間中はもちろん、その子が帰国してからもやりとりは続き、私が逆に受け入れた留学生の国に旅行し、その子の家にホームステイしたことも2回あります。
また、一度帰国してから、今度はプログラムでなくプライベートで家に遊びに来てくれた子もいました。
特に私が受け入れたのは、同年代、同性の留学生たちだったので、嬉しいことも悲しいことも共有できる姉妹が出来ました。
異文化を学べる
生活や会話を通じて、受け入れている留学生の子の国の文化を学ぶことも出来ます。
例えばアメリカ人の子を受け入れて「ペスカタリアン」という食生活を知ったり、フランス人の子から、良いものを長く使う精神を学んだり、クロアチア人の子の明るいオープンさに驚かされたりしました。
その結果、その子の国に興味を持って、旅行に行くこともしばしば。
行かなくても日本で異文化体験が出来るのは、ホストファミリーの大きなメリットだと思います。
自分が日本のことを学ぶ機会にもなった
留学生の子に聞かれたり、一緒に日本の代表的な観光地に行ったりすることで、私自身も日本のことを学び、そして日本がもっと大好きになりました。
聞かれることは伝統文化や食文化のことから、ポップカルチャーについてまで色々ですが、聞かれてすぐには答えられないことも少なくはありませんでした。
例えば、皇居の前を車で通った時に「日本人は天皇のことをどう思っているの?」と聞かれたことがあります。
また、受け入れた留学生から歌舞伎を見に行きたいと言われて、私も初めて歌舞伎を見に行きました。
それ以外でも普段の生活では中々しないことを経験できました。
語学力が上がった
私がこれまで受け入れた子たちは、日本語は全く出来ないか、超初級ぐらいだったので、基本的に英語で会話していました。
毎日朝から晩まで英語を話していることなんて普段はないので、英会話力は飛躍的に上がりました。
また、何か説明する時に表現できないことがあると調べていたので、ボキャブラリーも増えました。
それに加えて、英語でのコミュニケーションという点で、私にとって忘れられないことがあります。
高校生でホストファミリーになった時は、まだ英語力も未熟で、留学生の子が言っていることを100%理解出来ていないことは頻繁にありました。
そんな時私は、何度も説明させるのは申し訳ないと思って、流してしまっていました。
そうしていたらある日、留学生の子から「今私が何言ったかわかってないでしょ!」と言われてしまいました。
よく考えてみれば、相手は伝えたくてしゃべっているわけですから、わからないのにわかったフリなんてするのは、とても失礼なことです。
その時から私は反省して、わからない時は、「これってどういう意味?」「あなたが言いたいのってこういうこと?」とか「聞き取れなかったからもう一回ゆっくり言って」など伝えるようになりました。
この「わからなければ聞く」というの、当たり前のようでありながら難しいことを、高校生で学べたのは、とてもありがたいことでした。
また、このような理解出来なかったり、自分が伝えられなかったという経験が、その後の英語学習のモチベーションにもつながり、大学生になった今では、ほとんど不自由なく英語で会話できるようになりました。
ホストファミリーの大変だったこと

私はホストファミリーをして後悔したことはありませんし、受け入れの準備などについてもあまり苦には感じていませんでした。
しかし、やはり大変だと思うことはあったので、2つご紹介していきます。
常に一緒である
特に高校生の時の受け入れでは、約2週間、ほとんどずっと一緒に過ごしていました。
家族であってもそこまでずっと一緒なことはあまりないですし、やはり家族とは違う遠慮や気遣いがあるので、少し疲れることはありました。
そういう時は家族や友達と過ごしてもらって、自分も少し1人の時間をとれるようにしていました。
自分の予定が入れられない
1つ目の内容と関連して、受け入れ期間中はあまり自分の予定を入れられません。
もちろんせっかく留学生が来てくれているんだから、一緒に過ごしたいとこちらも思っているので、他の予定が入れられないことにイラついたりはありませんが、例えば勉強する時間がいつもより減ってしまったり、バイトや部活を休んだりすることに葛藤はありました。
私の場合、どうしても外せない予定の時は、主に家族が一緒に過ごしてくれていました。
最後に
ここまでご紹介した通り、ホストファミリーは私にとって忘れられない、また自分に大きな影響を与えてくれた経験でした。
機会があればまたやりたいなとも思っています。
そして、最後にお伝えしたいのは、ホスト”ファミリー”ですので、家族全員の協力、そして、全員が気持ちよく楽しく過ごせることが最重要です。
ホストファミリーに挑戦してみたいという人は、家族とたくさん相談して、実りのあるホストファミリー生活を送ってください。
新しいことに挑戦するのが大好き!インターン・資格・留学・英語などの記事を書いています。


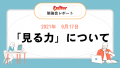
コメント