SAPで扱うデータは主に3種類ある。
➀パラメータ設定:システムの振る舞いを決めるデータ。
例:組織コード、取引区分、画面項目など
②マスタデータ:頻繁に使用するデータに特定のコードを振ったもの。入力ミス・表記ゆれを防ぐ、入力の手間を省くために必要。
例:商品、取引先データなど
③トランザクションデータ:取引の記録であり、SAPにおいて最重要のデータ。日々発生するすべての受発注などがトランザクションデータとして記録される。
例:出荷、発注など
最重要のトランザクションデータは、パラメータ設定やマスタデータを参照してそこに設定されているデータに基づいて記録される。そのため、トランザクションデータを正確に記録するためには3つのデータすべてが適切に運用される必要がある。
パラメータ設定
パラメータ設定とは
導入企業に最適なシステムの振る舞いを決めること。振る舞いとは、データ処理の方法やデータ保持の形式、必須のデータ項目など様々なシステムの処理のこと。
国や企業ごとに様々な違いがあるため、その違いに対応するために振る舞いを設定する必要がある。
例えば、国が違えば税制など法律が違う。また、業種ごとに業務が違うだけでなく、業種が一緒でも企業ごとに業務の流れが違うこともある。
そのため、SAPでは導入する企業の国や業務の内容に応じて、パラメータ設定を行うことにより対応している。
例えば、税制について日本では消費税率は10%だが、フランスでは20%、スウェーデンでは25%と異なる。SAPでは導入企業の国を事前にパラメータ設定することにより、その国の消費税率に従って処理することが可能となる。
また、業務については、同じEC事業者であっても自社倉庫内に在庫を抱えるamazonと、自社倉庫を持たない楽天市場では業務の流れが異なる。
Amazonの場合、客が商品を購入→倉庫に通知→倉庫からピックアップ→発送 だが
楽天の場合、客が商品を購入→出品者に連絡→出品者が発送 となる。
そのため、SAPでは特定の業務の有無や流れ、その他細かく設定項目を設けており、パラメータ設定を行うことであらゆる業務に対応できる。
パラメータ設定の種類
➀組織コード
SAPを導入する会社の組織情報。自社内の様々なグループ会社や組織をSAP上にマッピングすることで、データを分析・管理する切り口になる。
例えば、会社コードを振ることで、そのコードを振った会社ごとに財務諸表の作成が可能になる。
②アクティベート
ある機能を使うか、使わないかを決めるパラメータ設定のこと。
例えば、日本の法律上は必要な機能をオンにする、商社の業務に必要なそれぞれの機能をオンにする、など。
③チューニング
導入企業の業務に合わせて、機能を調整するパラメータ設定。SAPには土台となるようなデフォルトのパラメータ設定がされているが、すべてそのまま使えるというケースはあまりない。
例えば、SAPの初期設定上は任意入力だが、その会社にとっては非常に重要な事項なので必須入力にしたいなど。
そのため、その会社の業務にとって最適な形に機能を調整しなければならない。
パラメータ設定の方法
定義する
どのようにシステムが振舞うかを決める。
ただ登録すればいいのではなく、その設定がどのような基準で設けられているのか、何が起きたらどう追加・削除するのかまで整理したうえで、設定する必要がある。
紐づける
一つのパラメータ設定を定義しただけではうまく動作せず、複数のパラメータ設定が互いにどのような関係性なのか定義しなければならない場合もある。
例えば、物流拠点が群馬にあるとして、それを北関東支社、南関東支社は使うが、東海支社は使わないという設定がしたい場合、物流拠点と各支社のそれぞれのパラメータ設定を紐づけないと動作しない。
順序に則る
依存関係がある設定があり、事前に他のパラメータ設定をしておかなければ、そもそも設定できないようなパラメータが多くある。
マスタデータ
マスタデータとは
頻繁に使用するデータに特定のコードを振ったもので、データ処理をする上での基礎的なデータ。
入力ミス・表記ゆれ・手間の削減を行い、正確に・迅速にデータを記録するために設定する。無くてもシステムを動かそうと思えばできなくはないが、ミスが多発する上に手間もかかる。
例えば、ユニクロが扱う商品を管理するマスタデータがあるとする。
| コード | 商品名 | サイズ | 価格 | … |
| A001 | エアリズム | M | 1000 | … |
| A002 | エアリズム | L | 1200 | … |
| A010 | エアリズムコットン | M | 1500 | … |
| A011 | エアリズムコットン | L | 1700 | … |
もしマスタデータがなくすべて手入力する場合、エアリズムコットンが売れたら「白インナー」と記録する人もいれば、「エアリズムコットン」、「エアリズムコットン M 」などと記録する人もいるかもしれない。たとえ名前のルールなどを厳格に決めても、タイピングミスなどで表記ゆれが発生する。また、1日500着売れた場合、それらをすべて手入力するのは膨大な時間がかかる。
そのような事態を防ぐために、頻繁に使用するデータに特定のコードを振ってマスタデータとして管理している。
マスタデータとパラメータ設定の関わり
パラメータ設定で定義したものをマスタデータに割り当てることで振る舞いを制御する。
具体例として、トヨタがSAPを導入するとした場合、モノやサービスを管理する品目マスタを例に説明する。
事前に、品目タイプというパラメータ設定を下記表のよう設定する。
(それぞれの品目タイプに製造業務や発注業務の有無を設定している。)
| 品目タイプ | 製造業務 | 発注業務 | 在庫保持業務 |
| 製品 | 有 | 無 | 有 |
| 商品 | 無 | 有 | 有 |
| サービス | 無 | 無 | 無 |
製品は自社で製造するものなので、製造し、在庫管理は行うが、他社からの発注は該当しない。
商品は自社で製造せず他社から仕入れるものなので、発注や在庫保管理は行うが、製造はしない。
サービスは、無形なのですべてできない。
そのうえで、品目マスタは以下のように設定する。
<品目マスタ>
| 品目名 | 品目タイプ | ・・・ |
| レクサス | 製品 | ・・・ |
| カーナビ | 商品 | ・・・ |
| 修理サービス | サービス | ・・・ |
この場合、レクサスの「発注」が来たらエラーになる。なぜなら、品目タイプが製品なのにも関わらず発注処理が起きているためである。同じく、修理サービスは製造・発注・在庫保持すべてできない。
品目マスタに品目タイプとしてパラメータ設定したものを割り当てることにより、システムの振る舞いを決めている。そのため、事前に品目タイプを設定しておかなければ、品目マスタは登録できない。
マスタデータの種類
マスタデータは大きく分けると2種類ある。
- 共通マスタ
- モジュールに関係ないマスタ 例:ユーザーマスタ
- モジュールにまたがるマスタ 例:品目マスタ
- モジュール別マスタ
- そのモジュールでしか使用できないマスタ
また、マスタデータの多くはパラメータ設定やマスタ同士などほかのデータと依存関係にある。例えば、商品価格は、取引先と品目により異なるとする。その場合、取引先マスタと、品目マスタがないと、価格が決まらないため依存関係にある。
トランザクションデータ
トランザクションデータとは
日々の受発注や生産などの取引データ。
このデータを記録するために、企業はシステムを導入していると言えるほど最重要なデータ。
データは主に2種類に分かれる。
➀会計データ:仕訳などのデータ。基本的には実績値。
②ロジスティクスデータ:受発注、生産、在庫などのデータ。実績だけでなく、将来発生することも含む。
このデータで日々の取引を記録しておくことにより、抜けもれなく正確な財務諸表など決算資料を作成できる。それだけでなく、受注量に合わせて適切な発注を行うため、データ分析によりビジネスの方針を決めることもできる。そのため、抜けもれなく正確なトランザクションデータを記録することが不可欠となる。
トランザクションデータは最重要なデータではあるが、マスタデータやパラメータ設定を参照して記録されるため、マスタデータ、パラメータ設定も同じく重要であることは忘れてはならない。
おわりに
「パラメータ、マスタデータ、トランザクションデータ」はSAP関連の本を読むといたるところに出てくるが、初学者にとってわかりやすい概念的な説明はあまりなかった。そのため、私も違いや関係性を理解できておらず、SAPの本を読んでもあまり腹落ちしないことも多かった。しかし、この勉強会を経て完璧ではないものの、SAPで扱うこの3つのデータの基礎中の基礎が理解できた。
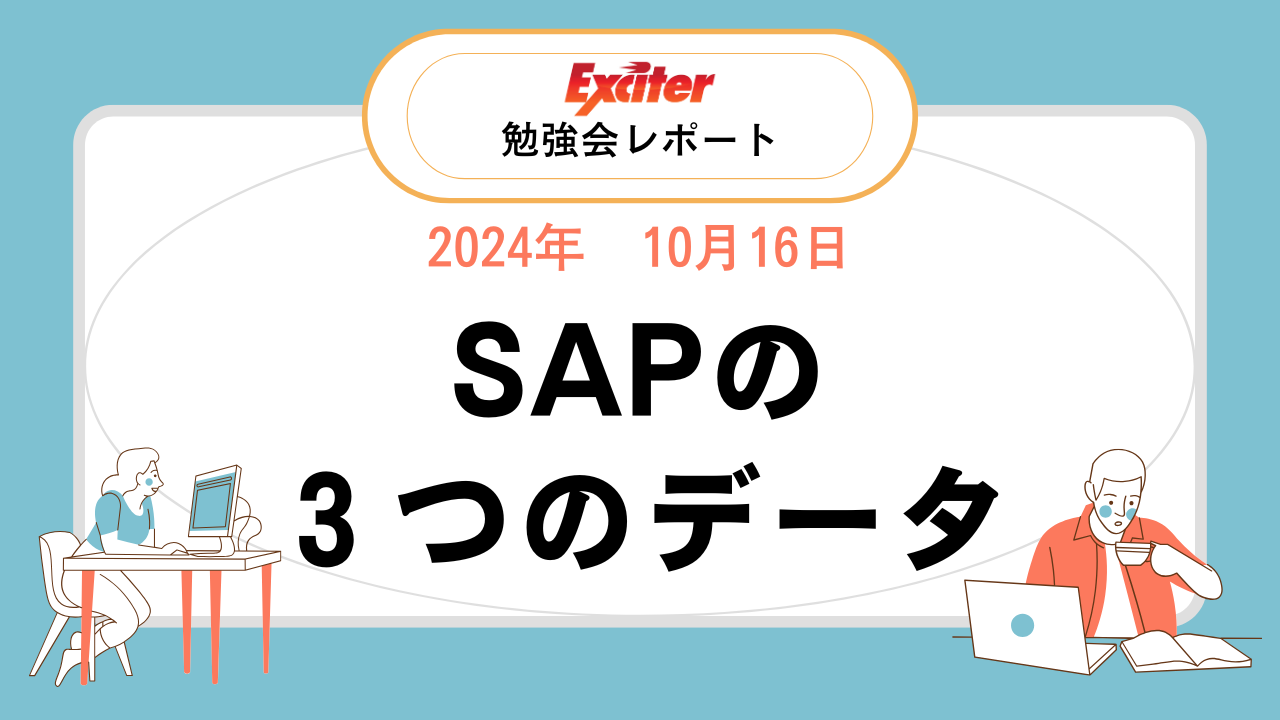


コメント