この記事では、文系大学生の私が「応用情報技術者試験」を受験した際の勉強方法やスケジュールなどについて紹介します。
応用情報技術者試験の概要や試験内容はこちら↓
http://exciter.bz/staffblog/daiki_oyojohogijutusyasiken_gaiyohen/
今回の記事では、上記の記事を見たことを前提にしているので、まだ見ていない人はぜひご覧ください。
結果
- 午前試験:78点
- 午後試験:65点
午後試験については勉強期間が短かったですが、ギリギリ合格点まで届きました。設問ごとに自己採点した結果、得点源として集中的に勉強した分野は8割、あまり勉強せず半分運頼みの分野は4~5割程度の正答率でしっかり戦略がはまりなんとか合格できました。
午後試験の分野選択
応用情報の鬼門と言われる午後試験において、分野選択は非常に重要です。
まず、試験形式の説明をしたのちに、私がどのように考えて分野を選択したのか紹介します。
試験形式
午後試験は、必答のセキュリティに加えて、その他10問から4問を選択し合計5問解きます。各設問20点、合計100点で構成されています。問題分野は以下の通りです。

出典:https://www.ipa.go.jp/shiken/syllabus/gaiyou.html
各分野の特徴
午後試験の各分野を「必要な勉強時間・得点の安定度」という軸でグループ分けすると以下の3つに分けられます。同じグループ内では、左から順に勉強時間が少ない順に並んでいます。
A)勉強時間が少なくて済むけど、得点が安定しない
⇒システム監査、プロジェクトマネジメント、経営戦略、サービスマネジメント
B)勉強時間が多く必要だけど、得点は安定する
⇒データベース、セキュリティ、ネットワーク、プログラミング(未経験の場合)、情報システム開発、システムアーキテクチャ
C)勉強時間は少なくて済むし、得点も安定する
⇒組込みシステム、プログラミング(ただし開発経験者の場合に限る)
Aは誰でもある程度得点できるけど、得点のばらつきが大きい分野です。午前試験を解ける知識があれば解けるため勉強時間は少なくて済みます。しかし、問題の文章量が多く、記述問題も多いため国語力がないといくら知識をつけても高得点は取れませんし、微妙な言葉選びが違って不正解になることもあるため得点が安定しづらいです。
Bは知識さえ身に付ければ高得点が安定して取れる分野です。午後試験対策として新たに必要な知識が多いので、勉強時間が必要です。しかし、文章量もAと比較すると少なく、記号や数字で回答する問題が多いので、知識をつければ高得点を安定して取れます。
中でもデータベースとネットワークはおすすめです。データベースに関しては、出題傾向がほぼ毎年一緒なので、慣れてしまえば高得点を取りやすいです。ネットワークに関しては、必答のセキュリティがネットワークに関連する問題が多いため、ネットワークを勉強することでセキュリティの得点を挙げることにもつながるためお勧めです。
Cは新たな知識を身に付けなくても高得点が取れる超おすすめ分野です。ただし、プログラミングについては実際にコードを書いた経験がある人に限ります。未経験の人の場合、プログラミングはBに属すると思ってください。
分野選択の方法
以上の各分野の特徴を踏まえて、おすすめの分野選択方法を解説します。以下の流れに沿って選択することを個人的にはお勧めします。
前提として、資格取得だけのために全く興味がない分野を勉強するのは勿体ないですし、勉強の意欲もなくなるのでお勧めしません。先ほどは分野ごとの難易度について解説しましたが、全体を通して全く高得点がとれないほど難易度の高い分野はないため、少し難易度が高いからと言って興味のある分野を捨てる必要は全くありません。
そのため、まずは勉強したいと思う分野から選択しましょう。
- 勉強したいと思う分野
- 得意な分野(勉強したことがある/業務で関わっている):新たに勉強するべき量が少なく、高得点が取りやすいため
- Cの分野
- 勉強時間と国語力によって選択
- 勉強時間に余裕がある→B
- 国語力に自信があるor勉強時間に余裕がない→A
- AorBの左から順に選択する
私の分野選択
私は2週間勉強すれば十分合格できると舐め切っていたため、本番2週間前まで勉強をサボっていました。しかし、いざふたを開けてみると、本来は2~3か月程度の対策が必要な試験ということに気づきました。
そのため、2週間しか時間がない私のプランは、「得点源分野で7,8割取れるようにしっかりと勉強し、残りの2分野にはあまり時間をかけず当日5割程度まで上振れすることを祈る」というものになりました。
実際に私が選択した分野は、セキュリティ、データベース、組込みシステム、プロジェクトマネジメント、サービスマネジメントです。
その中で得点源分野は、セキュリティ・データベース・組込みシステムです。
勉強方法
午前対策
過去問道場というサイトを使って過去問をひたすら解きます。

というのも、応用情報の午前問題は、半分程度過去問から出題されるため、過去問対策をしっかりやっておけば、合格ラインの6割を超えることは比較的難しくありません。
私が行った勉強方法は、1分野ずつインプットとアウトプットを繰り返す方法です。具体的には、過去問道場の分野ごとの問題を一覧表示できる機能を使います。この機能を使って、大体平成27年度までの問題を解いていました。これは個人的な体感ですが、平成27年くらいまでさかのぼれば、問題パターンを7~8割程度は網羅できます。

出典:https://www.ap-siken.com/apkakomon.php
午後対策
勉強方法は、「応用情報技術者 合格教本」で不足している知識を補いながらiTECが出している「応用情報技術者 午後問題の重点対策」で解法を身に付け、その後に過去問で演習するという方法です。過去問は全部で15回分解きました。

得点源分野であるセキュリティ・データベース・組込みシステムに関しては、合格教本で深く知識を身に付けるとともに、iTECの重点対策でしっかり解答を再現できるように2周しました。その他のプロジェクトマネジメント・サービスマネジメントは、iTECの重点対策で1周解いただけです。その後、過去問演習を行いました。
ただし、データベースに関してはSQLというプログラミング言語のようなものを回答に書く必要があるため、SQLの本を1周勉強しました。

午後の勉強法のポイントは、とにかく多く解くとことと本番と同じように解くことです。
多くの過去問に触れることで、問題と解答のパターンを自分の中に蓄積できます。このパターンをたくさん蓄積できれば、本番問題を解く際も、「問題文のここに根拠がありそう!」とか「こういう回答が求められているだろう」等の想像ができて、私の場合は素早く正しい答えに辿り着けました。
また、本番と同じように時間を測って5分野一気に解くことをお勧めします。なぜなら、試験の150分間、つまり2時間半集中し続けることは、隙あらばYouTubeやSNSを見るスマホ中毒の現代人にとってほぼ不可能です。また、暗記が多くあまり思考がいらない午前試験と比べて、午後試験は2時間半ずっと深い思考が求められる試験なので、非常に脳への負担が大きく疲れます。
私も当初は、20分かけて1分野の問題を解いた後にすぐにスマホを見て休憩したくなりましたが、本番にはそんな休憩時間はなく2時間半ぶっ通しです。だからこそ、本番前から2時間半集中力が続くように訓練しなければ確実に試験中に集中が切れて落ちます。
過去問の年度については、最新の問題傾向をつかむためにもなるべく新しいものを解くことをお勧めします。
勉強時間とスケジュール
私は試験の約2週間前から勉強を始め、合計80時間ほど勉強しました。2週間を3つの期間に分けて、計画を立てました。スケジュールは以下の通りです。

【第1期】
この期間では、午後対策の基礎固めをしました。具体的には、私が午後試験で選択した分野と関連する午前試験の過去問とSQLの本と、iTECの重点対策を取り組みました。
【第2期】
午前対策として残りの分野を1日2,3分野勉強し、午後対策として過去問を1日2回分解きました。
【第3期】
この期間は午前対策として1日2分野、午後対策として過去問を一日で3回分解きました。1日3回過去問を解くことはかなり体力的にきつかったですが、試験形式に慣れることができました。その結果、本来は1回150分で解けばよい問題の量を大体100分程度で解けるようになりました。
計画した分を勉強できなかった日もあるため、午後対策としては合計15回分の過去問を解きました。
受験当日の注意点
以下ではあまり知られていませんが、受験してみて感じた当日に注意するべきポイントを説明します。
受験票にある注意事項をちゃんと見よう
受験票には、食堂や駐輪場の有無などが試験会場における注意事項として書いてあります。ここを必ずチェックしましょう。私が受けた試験会場の注意事項には駐輪不可と書いてあったのですが、それを見ずに自転車で来た人が警備員の人に「ここでは駐輪できないから駅に駐輪してから来てください」と言われていました。
午前試験の退出時間を決めておこう
以下が当日の通常のスケジュールとおすすめのスケジュールです。

出典:https://www.ipa.go.jp/shiken/syllabus/gaiyou.html
私は前日に気づいたのですが、試験の前に説明が20分間あります。そのため緑枠で囲った部分は必ず着席している必要があり、試験教室への移動にも多少時間がかかるので、実際に休憩できる時間は40分もありません。
しかし、試験時間中に退出できるため、早めに退出して余裕をもって休憩できるように計画しておきましょう。私は11:30に退出して、70分間も休憩でき、午後に向けて集中力をかなり回復できました。
ちなみに、最後の10分間は退出できない、つまり11:50以降は退出できないので、注意してください。
お昼ご飯は朝に用意しよう
お昼ご飯は朝の段階で用意しておくことをお勧めします。というのも、試験会場にもよりますが近くにコンビニがないケースもあります。また、コンビニがあったとしても混み合いますし、休憩時間の40分のうち移動と買い物で10分程度取られてしまうのは痛いです。そのため、弁当を持っていくか朝試験会場に行く前に買うことをお勧めします。
後悔したこと
もっと早く取り組み始めるべきだったと後悔しています。私はすでに基本情報を持っていたため、「応用情報なんて、基本情報が少し難しくなったくらいの試験だろう」と舐めきっていて、試験前2週間まで何も対策していませんでした。しかし、実際に参考書を開いてみて、難易度の高さに驚きました。また、合格率も23%程度の難関試験ということをその時に初めて知りました。
そのため、基本情報をすでに持っている人、ITの知識に自信がある人も前もって、過去問をみて難易度を正確に判断したうえで、勉強計画を練ることをお勧めします。
感想
ITを広範囲に勉強するきっかけになった点で受験して良かったと思っています。近年、システムのセキュリティは重要性が高まっていますが、私はセキュリティには全く興味がないので自主的に勉強はしなかったと思います。しかし、資格勉強という形で無理やり勉強したので基礎的な要素は網羅的に学べましたし、案外面白かったです。

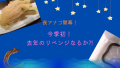

コメント