この記事では、応用情報技術者試験の概要や試験内容について紹介します。
文系大学生の私が「応用情報技術者試験」を受験した際の勉強方法やスケジュールなどについては、後日紹介します。
受験した理由
理由は2つあります。
1つ目に、応用情報という難易度の高い資格に合格することで「選ばれる新人」になりたかったからです。
私は現在大学4年生で就活を終えています。私の内定先は社員が社内にある各プロジェクトに参加するプロジェクト型の組織であるため、新人は研修を終えると各プロジェクトに配属されます。しかし、社員の方曰くどのプロジェクトからも声がかからずいわゆる“余りモノ”になる新人が稀にいるそうです。
人事の方曰く、どの新人を取るかは経歴書・研修時の評価などの資料を基に、人事ではなく各プロジェクトのメンバーが決めているケースが多いそうです。また、経歴書の資格欄はかなり見られており、IT系の資格の中では基本情報は多くの人が取得しますが、応用情報を取る人は少ないそうです。
そのため、応用情報を資格欄のアピールポイントの一つにしたいと思い受験しました。
2つ目に、単純にITが好きでより深い知識の勉強をしたかったからです。
私は基本情報を取得済みなのですが、基本情報ではその名の通り基本的な知識しか出題されないため、より深い・応用的なITに関する勉強をしたくて受験しました。
試験概要
応用情報技術者試験は、ITエンジニアへの登竜門といわれる基本情報の上位に位置づけられている国家試験です。

出典:https://www.ipa.go.jp/shiken/kubun/list.html
試験の基本的な情報は以下の通りです。
- 4月と10月の年に2回のみ開催され、各回約35,000人が受験
毎月開催の試験と比べてチャンスが少ないです。
- 受験費用は7,500円
- 受験者の平均年齢は28~9歳
おそらく主な受験層は中堅エンジニアなので、学生・若手にはややハードルが高いです。
- 合格率は約23%
超難関ではありませんが、十分な対策をしないと合格はできません。
つまり、年に2回しか試験がないためチャンスが少なく、受験費用も高く、難易度も高い試験です。そのため、しっかり計画的に勉強時間を確保して受験することをお勧めします。
また、最近増加しているPCで行うCBT試験ではなく、試験会場でのPBT試験、つまり紙と筆記用具を使用する試験なので注意してください。
試験形式
応用情報は、午前試験と午後試験で構成されており、両方の試験で6割以上得点することで合格できます。片方の試験が6割を超えていない時点で、もう片方の試験が満点であっても不合格になるので注意してください。
試験形式の概要は以下の図の通りです。

出典:https://www.ipa.go.jp/shiken/kubun/ap.html
午前試験
午前試験は四択問題であり、合計80問出題されます。その内訳は、テクノロジ系50問、マネジメント系15問、ストラテジ系20問です。テクノロジ系の出題が6割以上なのでここを重点的に対策しましょう。
問題は以下のような形式で出題されます。

出典:https://www.ipa.go.jp/shiken/mondai-kaiotu/index.html
実は、午前試験の半分程度は過去問から出題されるため、過去問さえしっかりと解けるようになれば合格ラインの6割を突破することは比較的難しくありません。
ただし一つ注意点があって、基本情報を合格済みの人も手を抜かずにしっかりと対策するべきです。なぜなら、基本情報と応用情報の午前試験の出題範囲はほぼ同じですが、応用情報の方がさらに深い知識が必要な問題が出題されるからです。
私は基本情報に合格済みだったので出題内容が全く同じ午前試験については対策しなくてもよいと考えていたのですが、実際に解いてみると解けない問題が多かったです。
午前試験が6割を超えないとそもそも午後試験は採点もされないため、しっかりと対策しましょう。
午後試験
午後試験は記述式で、必答のセキュリティに加えて、その他10問から4問を選択し合計5問解きます。各設問20点、合計100点で構成されており、合格基準は6割です。
出題される分野は以下の通りです。

出典:https://www.ipa.go.jp/shiken/syllabus/gaiyou.html
午後試験は分野選択が最重要ポイントです。各分野の詳細については、私の勉強法を紹介する記事に詳しく記載してあるのでご覧ください。
本番ではセキュリティに加えて問2~11から4問選択して回答すればよいため、自分が選択する分野以外は捨てましょう。
ただし、午後試験は試験回によって難易度のばらつきが大きいので、もし余裕があるなら1,2分野多めに勉強することをお勧めします。例えば同じ人が解いた場合でも、ある試験回は7,8割正答できても、また違う試験回は3,4割しか正答できないということがあり得ます。そのため、当日選択する問題数よりも1つか2つ多くの分野を勉強し、当日は勉強した中で難易度が簡単な分野を選択して回答するとより合格率が上がると思います。
試験当日の流れ
一日のおおまかなスケジュールは以下の通りです。

出典:https://www.ipa.go.jp/shiken/syllabus/gaiyou.html
試験の説明があるため、試験開始時間の20分前には着席している必要があります。時間ギリギリは階段やエスカレーターが混み合うため、余裕をもって試験の30分前くらいに試験会場に到着するとよいと思います。
試験会場に到着したら、受験票の番号を元に自分が試験を受ける教室を探して、そこに向かいます。試験教室に入った後は、試験の説明が始まるまでは参考書やスマホを見ても大丈夫です。
試験の説明を受ける時から、試験中に机に出してよいもの(受験票、筆記用具、目薬、メガネなど)以外はしまいます。
試験の説明後、問題用紙と解答用紙が配られ、試験官が試験開始の合図をしたら試験開始です。
試験開始40分後から試験終了10分前までの間は回答を終了し退出できます。
午後試験も基本的に午前試験と同じ流れです。午後に関しても試験説明があるため、開始20分前に着席することを忘れないでください。
試験結果については、2ヶ月後にIPAの公式サイトで発表が行われます。また模範解答について、午前試験は、当日中にIPAが公式サイトに掲載しますが、午後試験については合格発表の直前の時期に掲載されます。
おわりに
以上が「応用情報技術者試験」の概要です。
試験を受験するうえで、初めに試験の概要を把握することが大切です。初めに全体像を把握することで、受験に向けてやるべきことが明確になります。
また、試験当日に万全の状態で試験に臨むために事前情報はしっかりと把握しておきましょう。当日の注意事項を事前に把握しておくことで、焦らず落ち着いて試験を受けることができます。
前述のとおり、私が実際に受験した際の、午後試験の戦略・勉強法・忘れがちな試験当日の注意点などについては後日紹介しますので、ぜひご覧ください。

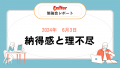
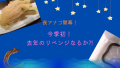
コメント