この記事は当時20歳、法律系の勉強未経験の大学生が6ヶ月間の勉強で宅建士試験に合格した話です。
はじめに
まずは簡単に宅建士について説明します。
宅建や宅建士とは「宅地建物取引士」の略称で、国家資格の1つです。
不動産会社で働く、土地や建物の売買、賃貸物件の斡旋などを行っている人のことをイメージしてみてください。
不動産業界で働くのに、必ずしも必要な資格ではありませんが、お客様が契約前に知っておくべき事項(重要事項)を説明することは宅建士にしかできません。
そのため、必ず不動産会社には1人宅建士を置かないといけないというルールがあるので需要のある資格です。
受験のきっかけ

私が19歳になった年の12月、父が宅地建物取引士に合格しました。
父が同年春ごろから予備校に通い、宅建の勉強していたのは知っていたが、不動産業務に全く興味がなかった私は何か勉強しているんだな程度にしか思っていませんでした。
資格自体に興味はありませんでしたが、父が合格できた資格なら余裕で取れるでしょという謎の自信と、20歳の年に何か形として結果を残したかったことから軽い気持ちで受験を決意しました。
翌年の試験に受験するために、すぐに某予備校の 6 ヶ月準備コースに申し込み、4月から10月の本試験に向けての勉強の日々が始まりました。
宅建試験について

宅地建物取引士試験は「一般社団法人不動産適正取引推進機構」が行う試験です。
1年に1度、10 月の第3日曜日にしか実施されないのにも関わらず、幅広い年齢層が毎年20万人前後も受験する人気の資格試験です。
受験手数料は7000 円で試験時間は2時間です。
出題形式はすべて四肢択一のマークシー ト形式で、1問1点で50 問出題される50点満点です。 試験の問題は、「宅建業法」、「法令上の制限」、「権利関係」、「税金その他」の 4 つの科目から出題されます。
受験に際して、年齢、性別、学歴、国籍すべてに制限がありませんが、過去に不正受検をした、もしくはしようとした人は最長3年間、新たに受験することが禁止されることがあります。
既に宅地建物取引業に従事されている方は、試験前に宅建登録講習を受け、修了試験に合格することで、5点免除を受けることができますので事前に準備をしておくことをお勧めします。
合格発表日は、原則として、12月の第1水曜日又は11月の最終水曜日です。
正式な日付は都道府県毎の試験案内に記載されますので確認してください。
難易度

国家資格試験の中での難易度では中程度(普通)だと言われます。
宅建士の合格率は15%前後で、難関と言われる国家資格を合格率で比較していくと、行政書士(5%)、一級建築士(5~10%)、税理士(8~ 15%)などがあります。
宅建試験の合格点は毎年異なりますが、毎年、大体50点満点中33点から35点が合格ラインです。合格率を基準としてその年の合格基準点を決めているものと予測されます。
したがって試験問題が簡単な年には合格基準点が上がり、問題が難しい年には基準点が下がるということになります。
難易度を大学受験と比較すると、日東駒専レベルの大学の難易度の大学に合格するのと同じ位の難易度と言われています。
個人的には大学受験と違い、宅建試験だけに専念する人が少なく、仕事や大学の勉強のような本業の合間の時間で勉強している人が多いため、合格へのハードルが高く思われてい るという印象です。
試験に合格するために、いつまでに何を、どのように行っていくのかを考え計画を立てる力が必要だと思います。
暗記がメインになりますので、暗記が苦手な方は苦労するかもしれませんが、宅建受験の勉強だけに専念した場合は、高校生レベルの学力でも十分合格できると思います。
独学 vs 予備校
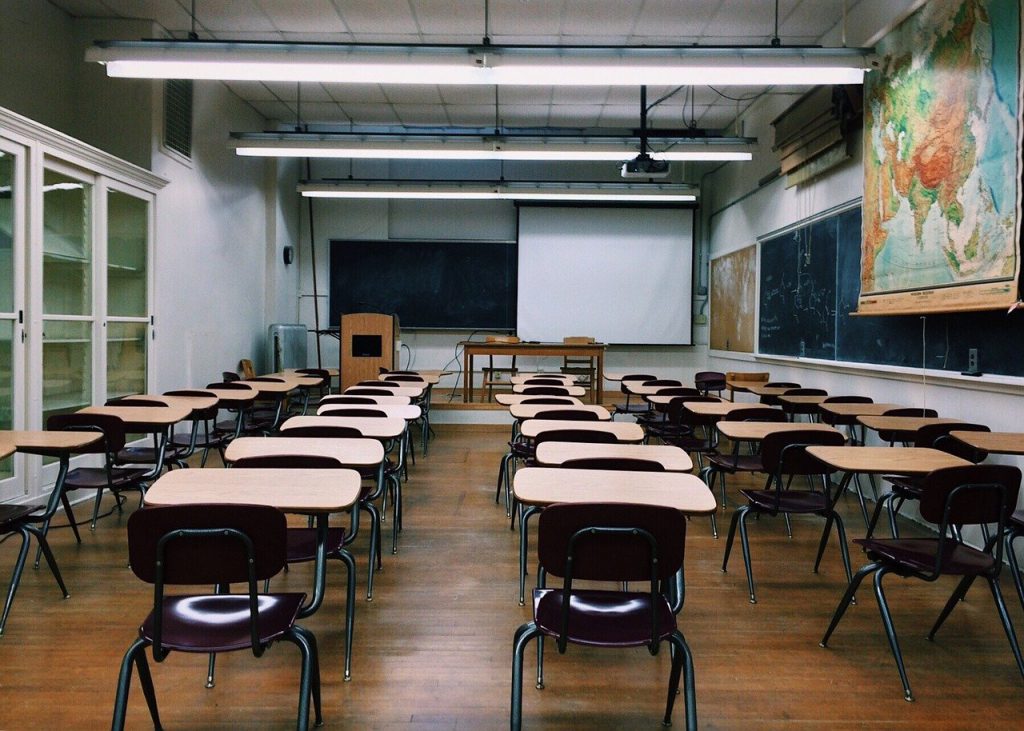
勉強を始めるにあたり、独学で勉強するか予備校に通うかを早めに決めておくと良いでしょう。
一般的に、宅建合格に必要な勉強時間は100~500 時間と言われています。
全4教科(権利関係、宅地建物取引業法、法令上の制限、税・その他)あり、事前知識や個人の得意・不得意によっても大きく差が開くため、勉強計画を立てる際は最低でも300時間は必要です。
私が予備校に通った理由は、大学での勉強と並行しながら確実に 1 回の受験で資格を取りたかったため、また合格実績が高い予備校のスケジュールに沿って勉強することで最短で合格できると判断したからです。
当時、週2回2時間半の授業を6ヶ月間受けていたので予備校でのトータル勉強時間は120時間程度です。
300時間を必要勉強時間とした場合、残りの180時間を自習の時間に勉強する必要があります。
独学で1から勉強する場合は、自分でスケジュールを立て勉強する必要があり、また過去のデータや出題予想についての情報を収集する必要があるため、予備校に通うより対策に時間が掛かるかもしれません。
勉強教材

主に予備校から配布されたテキスト、問題集を使用して試験対策をしました。
配布されたテキスト、問題集は下記の通りです。
- 基本テキスト(4冊)※全4教科(権利関係、宅地建物取引業法、法令上の制 限、税・その他)分
- トレーニング(4冊)
- ミニテスト(26回分)※ 基礎答練問題・解答冊子(4 回分)[添削付き]
- 解法テクニック講義レジュメ 問題編・解析編(各3冊)
- 応用答練問題・解答冊子(3回分)[添削付き] •
- 直前対策講義レジュメ(1冊)
- 直前答練問題・解答冊子(4回分)[添削付き]
- 全国公開模試問題・解答冊子[添削付き]
- 法律改正点レジュメ(1冊)
- 受講ガイド(1冊)
上記の他に、市販の過去30年良問厳選問題集を使用しました。
アマゾンのレビューが 良かった為購入を決め、予備校の問題集を終えた後に使用しました。
勉強方法
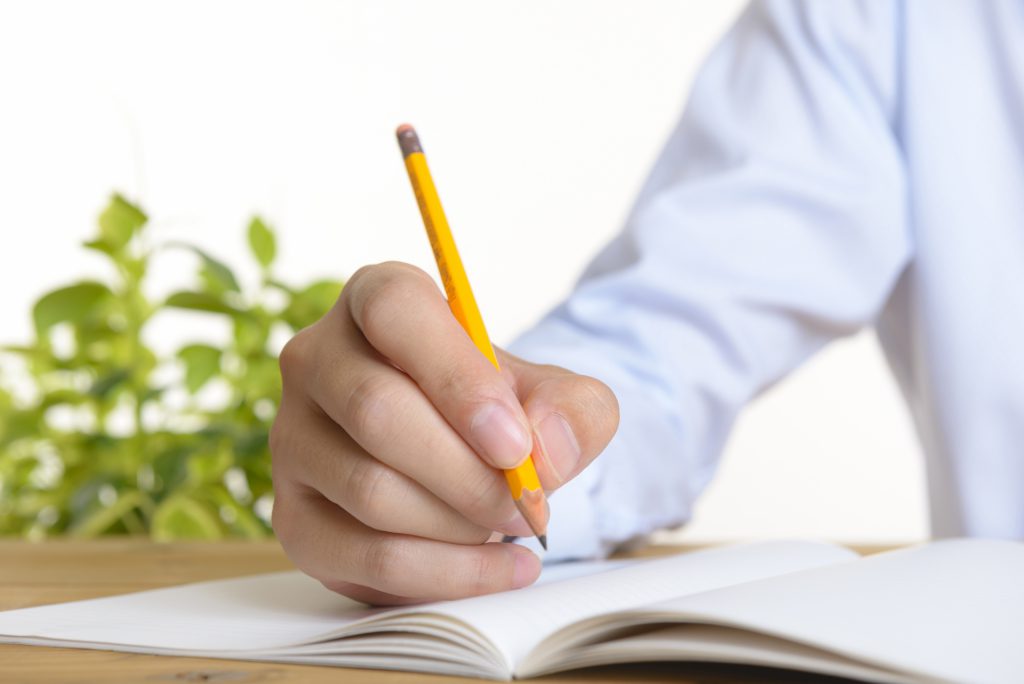
主にテキストの内容を読み進めながら、章末問題、ミニテストで定着を確認しました。
初めにテキストを読んだ理由は、試験の全体像を掴み、大まかな内容を理解する為です。
2回目以降は、熟読し暗記する作業を行いました。
4教科分のテキストを読み、章末問題、ミニテストを終えた後、過去問題集、模擬試験、時間を計りながら実践に近い形で問題を解きました。
過去問を解くことで、知識の定着を確認するのと同時に、過去の出題傾向や、出題形式、出題箇所の確認をします。
また模擬試験は、過去問や、本試験の出題予測を元に予備校講師が作成した試験ですの で、受験年に合わせた出題傾向、出題形式に関する対策が可能です。
宅建試験は、過去問から7〜8割類似問題が出題されるといわれていますので、テキストの内容をマスターし、模擬試験、過去問でコンスタントに 8 割取れていれば本番でも合格ラインに乗ってきます。
予備校を活用し、出題予想を基に無駄なく勉強することが効率的ですが、独学で勉強するぞと決めた方は、事前にインターネットを活用して出来る限り出題傾向・予想に関する情報を集めておくことをお勧めします。
過去問、模擬試験は5年分の過去問に取り組めば、その中からだいたい同じような問題が本試験で出題されますので、最低でも1周、時間に余裕があれば出来る限り過去問を回していきましょう。
受験までのスケジュール

私の通っていた予備校のコースは、4月〜10月までの6ヶ月コースで、下記のようなスケジュールに沿って勉強していました。
4 月〜7 月下旬はテキストの読み込みをメインで行い、テキストの章末問題やミニテストを用いて知識の定着を確認しました。
8 月中は、解法テクニック講座を受け、効率的な問題の解き方を学びました。
自習時間には、試過去問、模擬試験を繰り返し解きながら理解できない箇所はテキストに戻っ て確認という作業を反復して行いました。
9月から試験直前までは、直前答練という模擬試験や全国公開模試を毎週1回受験し、 本試験により近い形式での対策をメインに行いました。
早い段階でテキストを読み終え、過去問、模擬試験に取り組んでいくことが合格への近道だと思います。
受験者へのアドバイス

社会人の方は、予備校に通って効率的に勉強することをお勧めします。予備校を使い、 効率的に勉強し、かつ隙間時間をうまく利用して1日2時間程度の学習時間を確保するよう心がけてください。
学生の方は、比較的時間に余裕があると思うので、独学で勉強しながら合格を目指すというのも良いと思います。
確実に1発合格したい場合はやはり予備校を利用したほうが良いでしょう。
予備校に通うのに学費(当時は13万円位)はかかりますが、カリキュラムに沿って勉強することで時間の節約になりますし、クラスメイトがいるためモチベーション維持にも繋がります。
また、不動産や金融業界関係者が多く受験しているので、クラスでの人脈作りにも役立つと思います。
おわりに

宅建士は、合格率約15〜17%を推移している国家資格ですが、計画的に準備すれば誰もが取得できる資格だと思います。
不動産業務に興味が無くても、民法の知識は日常生活で役に立ちますし、家を借りる時にこちらに不利な事を貸主が隠しているかなど見抜くことができます。
また建築業界・金融機関・不動産管理会社・保険業界・不動産関連への転職を考えている方にもお勧めできる資格です。
何か資格の取得を考えている方は、是非宅建資格に挑戦してみてください!



コメント