この記事は、こちらの記事の続きです。

保育士資格試験を受けて、合格した私が対策方法をご紹介していきます。
筆記試験の対策方法
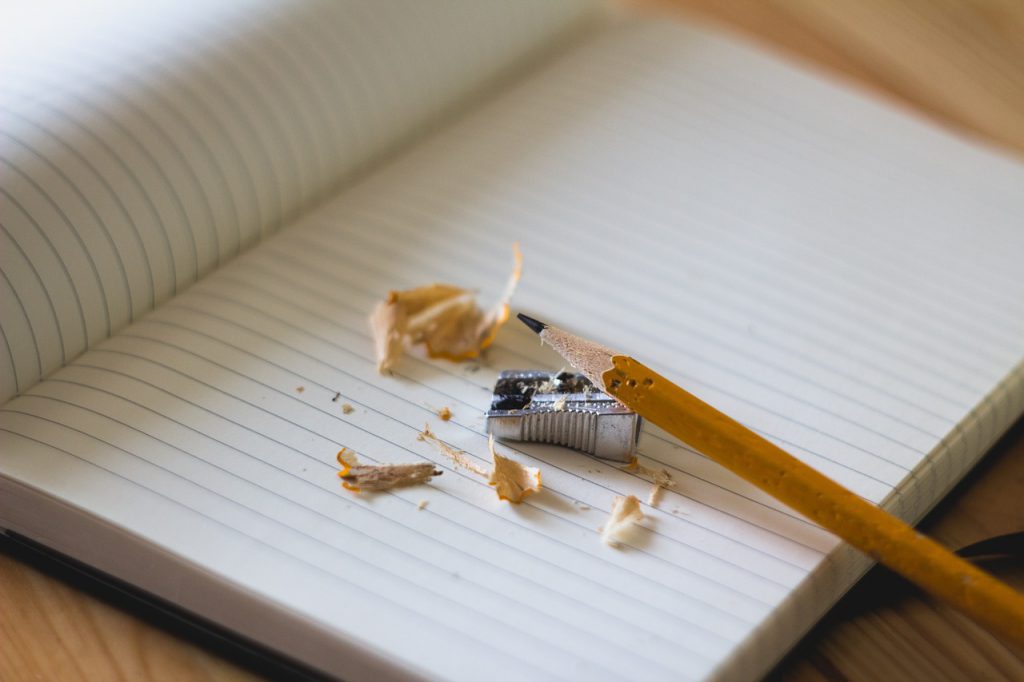
まずは筆記科目についてです。
一般的に保育士試験の勉強時間は90時間ほどと言われることが多いですが、もちろん人にもよりますし、加えてどのくらいの期間をかけるかにもよると思います。
1年など長い期間をかけすぎると、最初の方に勉強したことを忘れていってしまうということもあるので、3-6ヶ月ぐらい(90時間だとすると、1日平均1時間ぐらいの勉強)がちょうどいいのではと感じます。
私の場合は2回受験していますが、1回目も2回目も、3ヶ月ぐらい前から勉強を始めました。
まず1ヶ月ぐらいかけて、テキストを読んで、内容を理解します。
ただ読んでいるだけだと、なかなか頭に入らないので、線を引いたり、単元ごとの一問一答には取り組んでいました。
その後、テキストを1周したら、2週目をしながら、一問一答のページを使って暗記を進めていきます。
そして、1ヶ月前ぐらいから過去問に取り組みました。
過去問は過去5年分の前期と後期の問題、つまり10本の過去問が無料で公開されています。
過去問を解いて、採点し、間違えた問題についてはテキストで確認します。
点数は記録しておいて、安定して合格点がとれるようになった教科は今覚えていることを維持する程度の勉強量に減らし、合格点に届いてない教科に時間を集中させました。
最後の2週間ぐらいからは、覚えられていないことをノートにまとめたりもしました。
このように書くと、すごく順調に勉強が進んだように見えますが、これは、1回目で合格できなかった5科目分の対策をしていた2回目の例です。
8科目全てを対策していた1回目は全く予定通り進まず、8科目分のテキストを読むのでだいぶ時間がかかってしまい、過去問は数回しか解けませんでした。
(保育士試験合格のためには8科目全てに合格する必要があります。)
試験の概要についてはこちらの記事をチェック

過去問を解くのも、所要時間が1科目30分(実際の試験時間は1時間)だとしても、8科目全部で4時間かかります。
私は最初に受験した際、1回で合格は難しいとわかりつつ、もしかしたらラッキーで合格できるかもと思って、全科目の対策をしたのですが、欲をかかず5科目ぐらいに絞ればよかったなと後悔しました。
同じように考えている方がいたら、まず5科目の対策から始めてみて、全部いけるかも?と思ったら他の科目の対策も始めるのをオススメしたいです。
科目数を絞って対策する際には、科目ごとの難易度(内容の多さ)の違いや、内容の関連が強い科目などがあるので、そういったことも意識すると良いと思います。
サイトによっても多少違いますが、検索すると必要な勉強時間の目安が紹介されています。
例えば、子どもの保健は15時間、保育原理は8時間などですので、そういったのも参考にして対策する教科を選んでみてください。
そして、もし絶対に1回で合格したいという人は、余裕を持って6ヶ月前ぐらいから少しずつ勉強し始めるのが良いのではないかと思います。
実技試験の対策方法

次に実技試験についてですが、実技試験対策は筆記科目が終了してから1.5月ほどあるので、そこでやれば十分だと思います。
むしろ筆記で全科目合格していないと実技試験は受けられないので、まずは筆記試験対策に集中すべきでしょう。
(実技試験は3分野から2分野を選択して受験します。)

実際私は筆記科目試験、終了後3週間ぐらいで、言語の対策を行いました。
(言語と音楽を選択したのですが、新型コロナウイルスの影響で音楽が中止になり、言語のみで合格判断となりました。)
言語の対策
まず課題の4つのお話の中から1つを選択します。
選んだのは「3びきのこぶた」です。
理由としては主に以下の3つです。
・元々よく知っていて、お話しのおおまかな流れがわかる。(最終的に暗記が必要なため)
・表現に工夫がしやすい。(例えば:家を建てる場面「藁の家→サッサッ」「木の家→トントン」「レンガの家→よいしょっよいしょっ、など)
・3分間にまとめられそう。(3分間は結構短いので、話を簡略化する必要がある)
次に、ネットで過去の合格者のあらすじを調べて、それを参考に台本を作りました。
まず、なんとなく作ってみて、その後に読んでみて、3分間におさまるよう削るなどします。
台本が完成したら実際の練習です。
最初は見ながら読む、少し覚えてきたら台本をチラ見で話せるようにして、最終的に見ないで話せるように練習しました。
もちろん、本番と同じように、目線や身振り手振り、声の抑揚などは意識して練習をし、台本にも【ここは大きい声で】や【手を広げる】などのメモを書いていました。
また、台本については、表現が気になったりした際はその都度、修正を加えていました。
練習の回数は、2週間ほど1日1,2回ぐらい、本番前1週間は1日3-5回ぐらい練習していました。
2回読んでも6分なので、ちょっとした時間に練習できます。
私は寝る前にやるようにしていました。
練習では、本番は試験官がいるので、同居の家族に聞いてもらって人の前で話す練習をしたり、客観視するために、話しているところを動画に撮って自分で見たりもしていました。
また、私が受験した時は、マスク着用での受験だったので、マスクをしての練習もしました。
とにかく本番に近い環境で練習することで、当日の緊張も少しは緩和できた気がします。
それでも実際の試験では緊張しまくって、少し内容がとびました・・・
でも、練習時に台本が正確に思い出せなくなっても、話し続ける練習をしていたので、それが役に立ち、合格できました・
結論として、言語に関しては1週間ぐらいあれば、対策が出来るでしょうが、本番は緊張しますし、ちゃんと暗記できていないと自信を持って話せないので、余裕を持って対策するに越したことはないと思います。
私の場合、3週間ぐらいかけたので、準備万端で本番に臨むことが出来ました。
私が受験していない他の分野の対策についても少しお話しようと思います。
音楽
音楽は歌と演奏ですので、指定された楽器(ピアノ、ギター、アコーディオン)の経験が全くない人や、歌が苦手な人にはオススメできません。
また、ピアノ以外の楽器は自分で用意しないといけないので、持ってない場合は買わなくてはいけなくなってしまいます。
ある程度の経験がある人にとっては、そこまで難しくないでしょう。
私もピアノを10年以上習っていたので、音楽を選択しました。
造形
造形については絵を描くことに極端な苦手意識などがなければ、ポイントを意識した上でしっかり練習すれば大丈夫だと思います。
検索すると見本や解説もたくさん見つかります。
ただし、本番の制限時間も45分間ですので、結構な練習時間が必要になることは覚悟しておく必要があるでしょう。
どの分野を選ぶべき?

受験者数としては、言語、音楽、造形の順に多いのではないかなと思いますが、得意不得意に合わせて選ぶのがオススメです。
例えば、個人的には事前準備できて3分間話すだけの言語は楽だなと思って選びましたが、人前で話すのが苦手な人にとっては結構な苦痛になりうると思います。
ちなみに実技試験は、受験申請時に選択するので、受験分野の選択に悩んでいるという人は、それまでにYouTubeの分野別の対策動画などを見たりして考えておくのがオススメです。
新しいことに挑戦するのが大好き!インターン・資格・留学・英語などの記事を書いています。



コメント