はじめに
保育士資格は一度取得すれば更新も不要で、生涯有効な資格です(紛失などの例外を除く)。
保育園勤務に限らず、将来的に子どもと関わる仕事をしてみたいと思っている人はとっておいて損がないと思います。
かくいう私も、「とりあえず取っておこう」という軽い気持ちで受けてみた受験者の一人。
合格は簡単ではありませんが、将来的な自分の子育てなどにも役立ちそうな内容ばかりですので、ぜひ楽しんで勉強してほしいです。
受験のきっかけ
当時私は大学で、保育や福祉とは全く関係ない分野を専攻していました。
大学の勉強とバイトが中心の日々の中で、何かに挑戦してみようと思って選んだのが保育士資格です。
とはいっても、突然保育に目覚めたわけではなく、母が保育士であったり、自分も子ども好きだったりしたので、保育士資格のことは気になっていました。
保育士資格について
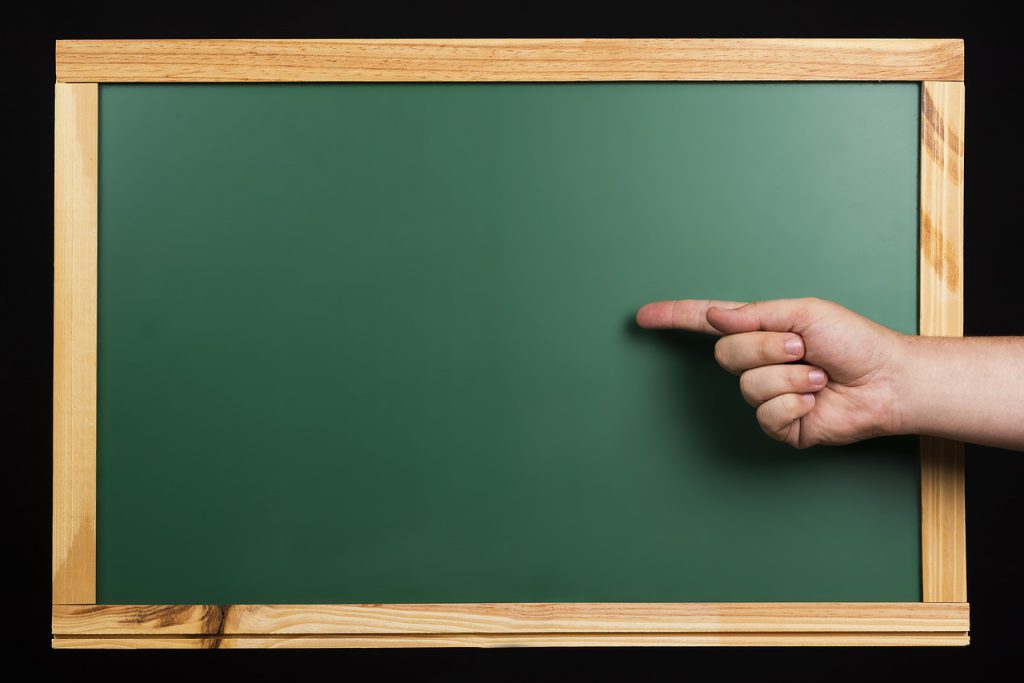
保育士は「児童福祉法」に基づく国家資格です。
名称独占資格ですので、「保育士」として働くには、保育士資格を持っていることが必須になります。(加えて都道府県への登録が必要です。)
保育士が働いているところとして、まず保育所が思い浮かぶと思いますが、それ以外にも、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、障害児施設などでも活躍しています。
(こういった内容も筆記科目の対策で勉強します。)
保育士資格をとるには、指定を受けた学校などを卒業する方法と、保育士試験に合格する方法があります。
この記事では後者の「保育士試験」について扱っていきます。
幼稚園教諭免許状との違いは?

ちなみに、保育園と近しいものといえば、幼稚園が思い浮かぶと思います。
似たようなイメージがある人も多いかもしれませんが、役割や保育対象年齢(保育園は0歳から、幼稚園は3歳から)、管轄省庁(保育園は厚生労働省、幼稚園は文部科学省)など様々な違いがあります。
幼稚園で有資格者として働くためには「保育士資格」ではなく、「幼稚園教諭免許状」が必要です。
そのため、自分が働きたい場所が保育園なのか、幼稚園なのかは、しっかり確認しておくのが重要になります。
また、保育士の資格があれば、幼稚園教諭免許が取りやすくなる特例制度もあるので、保育士資格取得後に検討してみても良いかもしれません。
試験の概要

保育士試験は年に2回(前期と後期)開催され、筆記試験と実技試験の2つがあります。
実技試験はすべての筆記試験科目に合格した人が受けられるという仕組みです。
筆記試験
筆記試験は2日間で以下の8科目を受けます。
- 保育原理
- 教育原理および社会的養護
- 子ども家庭福祉
- 社会福祉
- 保育の心理学
- 子どもの保健
- 子どもの食と栄養
- 保育実習理論
1科目につきマークシートの5択問題が20問で、試験時間は1時間です。
合格点は6割(100点満点中の60点)ですが、教育原理および社会的養護については、両分野それぞれで6割(60点満点中の30点)を取る必要があります。
1回の試験で8科目全てに合格する必要はなく、一度合格した科目は次回から免除されます。
しかし、免除の有効期間は基本3年間(延長制度あり)なので注意が必要です。
実技試験
実技試験は音楽・造形・言語から2分野を選択して受験します。
選択した両分野で6割(50点満点中30点)をとることで合格できます。
各分野の概要としては、音楽が演奏(ピアノ、ギター、アコーディオン)と歌。造形が当日発表された場面を、鉛筆と色鉛筆で表現する。言語が課題の4つのお話から1つを選択し、3分間のお話をするというものです。
受験料
受験料は科目数にかかわらず、12,950円です。
決して安くはありませんが、複数回に分けて合格を目指すことも検討できるような額ではないでしょうか。
受験資格
大卒の方は基本受験が可能です。
高卒の方、大学在学中の方などは、細かい条件があるので、ご自身でご確認ください。
私の場合は、受験の申請時はまだ大学2年生だったのですが、「大学に在学2年以上で62単位以上の取得が見込まれる者」として受験し、全て合格したのち、「2年以上在学かつ62単位以上修得済みの証明」を提出しました。
試験の詳細を確認する方法
受験資格を含めた試験の詳細が書いてある「受験申請の手引き」はネットでも閲覧は可能ですが、実際の受験申請には申請書類の取り寄せが必要になります。
2021年前期の場合ですと、筆記試験が4月17、18日で、申請書の受付は1月29日まででした。
つまり、書類の取り請求は1月初旬ごろ、筆記試験の4ヶ月以上前にする必要があるので、受験を検討している人は気をつけて下さい。
参考までにですが、2021年後期試験の書類は7月6日より請求が可能になる予定だそうです。
新しいことに挑戦するのが大好き!インターン・資格・留学・英語などの記事を書いています。



コメント