当社では、タスクをツールにより管理しており、タスク管理ツールの運用の見直しを行うこととなった。今回その業務を、当社に入社して1年半、頭脳労働かつ事務職未経験の私が主体となって担うこととなった。業務着手から運用開始までの約1か月間、タスク管理ツール運用の見直しという業務を通して、どのような業務を行い、何を学んだのか、「課題に取り組む」ということはどのようなことであるか、今後の自身に活かすために業務を振り返ろうと思う。
本作では「タスク管理ツール運用の見直し」の業務にスポットをあてた内容を記載する。(課題検討への取り組みについては続編として後日アップします。)私のように事務職未経験で同じような業務を担う方に、部分的でもよいので参考になればと思う。
タスク管理ツール運用の見直しの目的
タスク管理ツールを導入した経緯
そもそもタスク管理ツールを導入した理由として、従業員数の増加やリモートワークが中心となり、管理者1人ではタスク管理に限界を迎えたためである。当社はいわゆるベンチャー企業であり、タスク管理ツール導入前の従業員数は1桁台と少なく、また常勤者よりも学生アルバイトが多かったため、当時は代表1人のみでLINEや口頭によるタスク管理が可能であった。しかし、2年弱前から採用を強化したことで従業員数も増加し、また常勤者の数も増加した。さらに、当時はコロナ感染者数の爆増が続いたことからリモートワークが中心となることも多く、作業状況が直接的に見えづらくなったこともあり、一括管理できるタスク管理ツールを導入することとなった。
見直しの背景
タスク管理ツールを導入したことでタスク管理や従業員の評価も行いやすくなったのだが、なぜ今回ツールの見直しを行うこととなったのか。理由としては大きく2つある。
①経費削減が必要になった
初めての導入は「Backlog」という、タスク管理ツールの中でも人気のツールの1つであった。見やすく操作方法も簡単であり、タスク管理に必要な機能も充実しておりその会社にあった使い方ができるようカスタマイズ機能も充実していたが、その分費用もかかる。
昨年は無駄な経費が多く発生したこともあり財政状況の見直しが必要となり、その対象にBacklogも入ることとなった。導入当初は従業員と活用状況がコストに見合っていたため、コスト面の問題はなかったものの、最近では従業員数が減少したことにより、活用状況がコストと見合わなくなった。
②タスク管理ツールを使用する中で、様々な課題が発生した
導入当初、「なんとなく」で使用を開始したこともあり、運用ルールに整備不良があった。また、管理が十分なツールと言っても、やはり機能制約の限界も見えてきていた。(特に%による進捗度合い、タスク評価、タスク担当者の評価をツールを通して行うことに課題があった。)
見直しの目的
今回の見直しの背景を受け、見直しの目的は以下の3つである。
①コスト削減
②タスクにおける主要な課題を解決する
③タスク管理を人事評価に連携し、給与や待遇の決定に貢献する
新ツール運用までの業務と、業務を通して学んだこと
新ツールの選定
まずは新ツールの選定から行った。始めは代表から「ASANA」というツールを使用する指示があったものの、最終的には「Jooto」を使用することとなった。
- ASANAが却下となった理由
トライアルで使用してみた結果、直感的に分かりづらいと感じた。登録作業やタスク照会作業の際に、情報過多かつ細かい文字が多いことでパっと見がわかりづらかった。
- Jootoを採用した理由
「費用が安い」、「わかりやすい」という点であった。
費用が安い点としては、Backlogと比較して約15万弱の削減ができることが大きかった。また、わかりやすい点としては、ASANAと比べてシンプルな表示であり、パっと見がわかりやすかった。
- 選定業務で学んだこと
ツールの選定にはまず情報収集が必要となるが、まずはツールの情報の前に、会社の管理に合った機能や項目や条件が明確になっていなければならない。明確になっていない状態でツール調査をしてもただ闇雲にツールを洗い出すだけになってしまい、時間のロスに繋がる。まずはコスト、必要な管理項目、使用にあたり必要な条件などを明確にしてから、ツール調査を行う必要がある。
「タスク管理ツール運用の見直し」概要資料の作成
今回の見直し業務を行う上で、業務の概要を代表に明示し、認識合わせを行うための資料を作成した。内容としては今回の見直し業務の概要、新ツールJootoの概要をメインとした資料を作成した。
資料を作成するためのポイントを紹介する。
- 概要資料作成の目的を明確にする
まずはおもむろに資料を作成しようとしても内容がまとまらずただ時間を喰うだけである。何事にも言えることだが、まずは作成の目的を明確にする。
今回の資料で言えば、この業務の目的を果たすために、管理者やこの業務を一緒に進めるメンバーと、どんな目的で何を行い、どのように進めていくのか、認識を合わせるためである。この目的に沿ってAgendaを考えることで、今回の見直しの背景と目的、見直しのポイント、運用までの作業スケジュール、作業に取り掛かるための準備など、自然と必要な情報を記載した資料を作成することができる。
- 概要資料作成で学んだこと
記載内容は、「定量的」かつ「シンプル」、「ストレート」に表現すること。私はこの3つ全てにおいて表現することが大の苦手であり、脈略なくツラツラと表現してしまう癖がついてしまっている。そんな私が意識したことは、①結論から記載する、②無駄を削ぐ、③ストレートな表現で、である。
①について、まずは結果として何が言いたいのか伝えること。ツラツラとした文章は余程表現が上手でない限り読み手の読む気をなくしてしまうし、何が言いたいのかわかりづらくなってしまう。
②について、わざわざいらない表現や接続詞などを使わないこと。文章はできるだけ短いほうが伝わりやすい。文章が長くなってしまった場合は、もう一度文章を読み返し、最後の締めの表現である「~である」や「しかしながら」の「ながら」など、不要な表現がないかどうかを確認する。
③について、回りくどい表現はしないこと。読み手からは、「だから結局こう言いたいんでしょ」と思われてしまう。資料はわかりやすいことが大前提となる。
作業スケジュール計画
まずスケジュールを立てるために、必要な作業を洗い出す必要がある。洗い出しは指折り数えて出しては抜け漏れや重複が発生するため、「大タスク→中タスク→小タスク」とかみ砕きながら出す。今回新ツール運用までに必要な作業を出すために、まずは大タスクに「新ツールのセットアップ」「データ移行」「運用の切り替え」を切り口とした。このように大きい概念から入ることで、抜け漏れや重複なく作業を洗い出すことができる。
Fit&Gap分析と課題表の作成
新ツール移行にあたり、①旧ツールで生じた課題、②新ツールに移行するにあたり発生する課題、③タスク管理自体が抱える課題を明確にしなければならなかった。課題を明確にするために行ったことを紹介する。
- Fit&Gap分析
Fit&Gap分析は、新しいツールの導入を行うために、これまでできていたことが新しいツールになっても実現可能かどうかを明確にし、実現するためにはどんなことを検討し何を行わなければならないのか、課題を整理するために行った。例えば、今回においては旧ツールで行っていた管理を出し、新ツールでは旧ツールで行っていた管理が可能であるかどうかを分析するなどである。
Gap、すなわち新ツールになるとできないことは当然課題として挙げられるが、Fitするからといって課題がないということではない。新ツールでも実現可能であっても、旧ツールと同じような機能や操作方法とは限らない。新ツールではどのように実現するのかということも課題として挙げられる。
- 課題表の作成
新ツール導入にあたり、課題一覧表を作成した。課題には、当項の冒頭でも述べた通り大きく分けて3つの課題が挙げられた。これらの課題を表にし、1つ1つ解決案と結果、アクションアイテムを明らかにしたことで、運用までに課題を解決するための進め方が明確になった。
- Fit&Gap分析と課題表作成から学んだこと
「内容をごちゃまぜにしない」、ということ。私は日頃から話をごちゃまぜにする癖がついており、そのせいで頭が混乱して思考が停止してしまうことがよくある。そして、課題解決のためにはこのごちゃまぜ思考は非常によくない。1つ1つの話を切り分けて考えなければならない。
例えば、Fit&Gap分析を行う際も、Fitしたから課題がないわけではなく、FitはしていてもどのようにFitされるのか、という課題は生じる。Fit&Gapと課題のあり/なしは切り分けて考えることを学んだ。
新ツールのセットアップ
新ツールのセットアップで主に行うことは、新ツールの契約、ツール内の管理項目設定、プロジェクト設定、ユーザー登録である。セットアップをスムーズに行うためには予め準備が必要である。
- トライアルで一通りの使い方を把握しておく
ただ闇雲に使い方を調べるのではなく、まずは登録・更新・照会作業に使い方を分ける。そこからさらに、各作業で管理者と従業員が行うことと分け、作業を細分化し、使い方を調べていく。
- 使い方やルールをまとめておく
どんなツールを使用しても、基本は登録・更新・照会という共通の作業ができるが、ツールによって操作方法や機能などは違ってくるため、使い方やルールを予めまとめておくとよい。さらに、ツールだけの話ではなく、プロジェクト毎にも設定する項目は違ってくる。予めプロジェク毎にも使い方やルールをまとめておくことにより、セットアップにかける時間が大幅に違ってくる。
- ツールセットアップで学んだこと
課題表作成時にも言えたことだが、「整理する」ということ。私は短絡的に結果だけを求めてしまうタイプなので、場当たり的に解決しようとする癖がついており、全体観を把握することができていなかった。まずは大きいことから徐々にかみ砕き整理することで、作業の抜け漏れや重複を防ぐことができる。また、作業もスムーズに進められることも実感できた。
データ移行
旧ツールの残タスクを新ツールに移行する作業を行った。データ移行においてのポイントを紹介する。
- データ移行前
①過渡期の対応方法検討
旧ツールから新ツールにデータを移行し、新ツール運用開始まではツールの使用を停止しなければならない。停止期間中も当然タスクの発生や更新作業、管理作業も発生する。そのため、停止期間中の対応も検討し、実施しなければならない。
②残タスクのデータバックアップ
データ移行前に、残タスクのデータをバックアップしておく必要がある。なぜならば、新ツール運用開始後に停止期間中のタスク状態の更新などが必要であることや、移行ミスを確認するためである。
③データ移行するタスクの選定
タスクは基本的には全て移行することが前提ではあるものの、手作業で行う場合、少しでも手間を減らすことも重要な考えである。そのため、もう少しで完了となるタスク(最終レビューのみのタスク)は移行しないなど、移行タスクの選定も視野に入れること。
- データ移行時
データ移行時、ミスをしてしまった。今回データ移行するタスクとしないタスクを分けたが、私はここで、移行しないタスクを旧ツールで完了処理することから始めてしまった。本来であれば、移行しないタスクは旧ツールに残しておき、移行したタスクを完了処理しなければならない。私はここに違和感を感じてはいたものの、もともと認識のズレが発生したことにも気にかけず、思い込みでそのまま作業を続けてしまった結果、残タスクが旧ツールでは完了扱いとなり、移行した後のタスクが旧ツールにも新ツールにも残ってしまうこととなった。
- データ移行で学んだこと
違和感を放置し、なんの確認もせず思い込みで作業をしてしまったことから、まずは違和感を放置しない、ということ。違和感を感じたらまずは立ち止まり、違和感の原因を探ることや、上長に確認しなければならない。
次に、辻褄が合わないことに気付かなければならないこと。仕事もプライベートも関係はないが、特に仕事においては論理的思考が求められるが、辻褄が合わないことに気付けないことはきちんと考えられておらず、ただのToDoをするだけの作業員になっているだけである。
資料整備・従業員への周知
運用開始にあたり、新ツールの従業員への周知をしなければならない。そのためにはまずマニュアルが必要となる。
- マニュアル作成
マニュアルを作成するときは、何よりも分かりやすいことが重要である。そのためには、客観的視点を持ちながら作成することが求められる。そして、「もの」など、抽象的な表現を避けるべきである。
- マニュアル作成で学んだこと
スピードの意識である。今回はなんとか予定通りの日程に運用は開始できたものの、マニュアル作成は運用2日前のギリギリの作成になってしまった。そのため、スピード重視で作成し、一先ず最低限のマニュアルを作成し、運用開始後にアップデートを行った。
私は完璧思考があるため、時間を気にしていると言いながらも結局クオリティーを重視しすぎてしまい、とにかく作業に時間がかかることが多い。今回のマニュアル作成を通して、限られた時間以内に最低限のクオリティーの作成物を作成することの重要性を学んだ。確かに完璧なクオリティーであることはとてもよいことであるが、自分のタスクは常にいくつも抱えており、そしてそれぞれのタスクにも納期があることから、1つ1つに完璧なクオリティーを注ぐことはできない。そして、最低限のクオリティーになったとしても、何よりも納期遵守は必須である。今回のマニュアル作成を通して、スピードの重要さを実感できた。
最後に
今回のタスクを通して大きく実感できたことは、達成感と責任感である。これまでも長期に渡るタスクを経験してきたが、いつも精神的な甘えが生じ、「できない」ばかりを嘆いていた。しかし今回のタスクでは、これまでに比べて自ら積極的に主体的に動くことが多かったタスクでもあった。ミスや嘆くこともあったが、嘆いていても仕方なく、ミスをいつまでも引きずってはいられない。常に前に進むことを考えられた経験にもなった。
今回の業務を振り返ることで改めて自分を振り返ることもでき、以前よりもマシになったこと、初めてやってみたことによる新たな気付きなど、学びも増えた。この学びを無駄にしないよう、試行錯誤して精進していきたい。
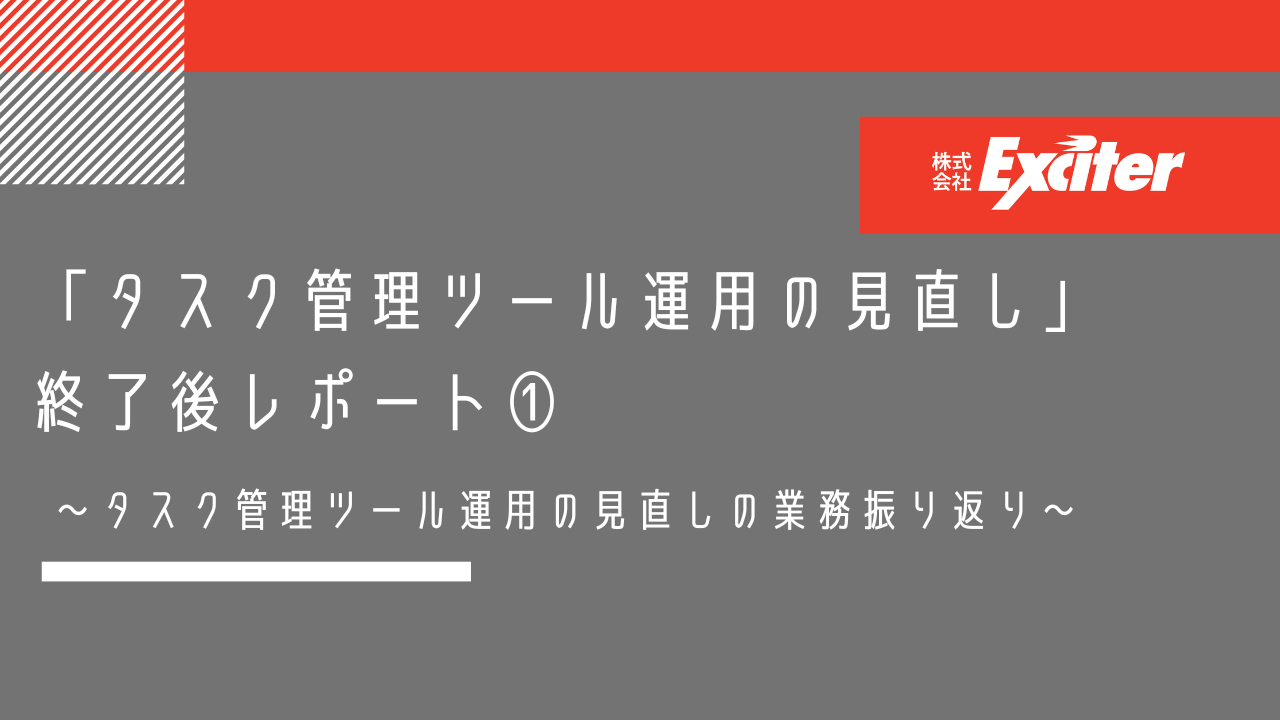


コメント