3月に1回目の簿記3級を受験し不合格であったため、今回5月に再び受験したが今回も不合格であった。
2回とも不合格であった事実と向き合い、そこから原因や合格するために行うことを明確にし、3回目は確実に合格することを目的としたレポートである。
※簿記3級試験の概要については、前回の記事をご覧ください
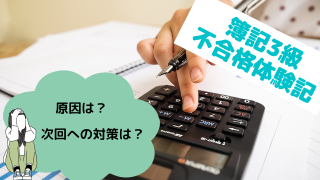
1回目と2回目の結果、実情
結果
簿記3級の配点は「第1問:45点」、「第2問:20点」、「第3問:35点」の計100点満点であり、合格点は70点以上である。
- 1回目の結果
計24点(第1問:21点、 第2問:0点、 第3問:3点)
- 2回目の結果
計40点(第1問:27点、 第2問:0点、 第3問:13点)
上記結果から、第2問「帳簿」と第3問「決算」に大きく問題がある。第1問「仕訳」についても理解が不十分である。
実際に行った勉強法
前回の受験から約2ヵ月空いたが、今回は試験日の1ヶ月前から勉強を始めた。とは言っても計画性はまるでなく、集中して行ったのは試験の1週間前からであった。
2回目の受験であったが、1回目と同じテキストと問題集を使用した。
- テキスト
まずは簿記の基本となる仕訳について、仕訳の項を2周読んだ。元々理解できていた商品売買や現金等の項目は、改めて内容を復習する程度であったので軽く読み流した。そして理解に苦しんだ債権債務や貸倒れ等の項目は、1回目はどんなものであるのか知るために軽く読み流し、2回目は1つ1つの内容を理解するためにじっくりと読んだ。
帳簿編と決算編は、試験前に軽く1周流し読みをしただけであった。
- 問題集
仕訳は一通り解いたものの、解きっぱなしで解説はあまり読み込まなかった。
仕訳の問題とテキストを読むことに時間を費やしたため、試験までの時間がほぼなく、帳簿編はテキストの練習問題を解いた程度で問題集は使用しなかった。
決算についても、試験直前に3問程度の問題を解き、解説を読んだだけであった。
また、実際の試験形式の問題については、試験直前に1回解いただけであった。
結論、1回目の反省点は何も活かせなかった。むしろ、1回目のレポートの内容を覚えておらず、見返すこともしなかった。
不合格の原因
《勉強への意欲や方法について》
勉強への意欲について、仕事で手いっぱいであったこと、またゆっくりと休めていなかったため疲労していたこと等、何かしらの理由をつけて勉強しようとしなかった。確かに仕事や休息は生きるために必要であり優先度も高いが、そもそも普通の社会人はそれらの環境で勉強し、両立を図ることが当たり前である。そのため、私はそんな環境にただ甘えていただけであった。
方法について、まずはテキストと問題集をまるで活用できておらず、また勉強するという行為を習慣化できていなかったため、全体的に理解が定着しなかった。そもそも勉強することを習慣化していないどころか、学生以来、普段から集中して勉強することをしてこなかったため、まずは勉強を習慣化するための方法を考えなければならない。習慣化することにより、自ずとテキストや問題集等が活用される。
《内容について》
主に以下の4つである。
- 普段聞き慣れない勘定科目の理解(勘定科目の名称と、意味)ができていない
- 仕訳パターンの概念が半分くらいしか理解できていない
- 債権債務、貸倒れ、有形固定資産と減価償却等の、業務がイメージできていない
- 帳簿と決算についてはほぼ理解できていない
《実際の出題形式について》
実際の出題形式の演習をほぼ行わなかったため、問題を解くペース配分や、勉強した内容がどのような形で出題されるのかを把握しておらず、いざ問題を目にすると解き方が分からず理解していないことが判明した。すなわち、テキストの内容自体は納得しながら読んでいたものの、実際に活用するための理解は何もできていなかった。
次回の試験までに行うこと
《勉強することを習慣化する》
- 昼食時に勉強する
お行儀はよくないが、食べながら勉強することは「食べる」ということをしているため、まず脳がさえている状態であり、仕事から離れられる時間として、仕事以外のことをすると気分転換にもなる。そして昼食は必ず毎日摂るため、昼食時間=勉強時間となり、自動的に勉強することが習慣化される。
- 日曜日は最低でも3時間勉強する
平日はなかなか多くの時間を確保できないため、週に1日はまとまって勉強する時間を確保する必要がある。そうなると土日に行うことになるが、土曜日は別のバイトが入っていることや、金曜日の夜に飲み過ぎて二日酔いである可能性も大いにあるため、ここは無理なく日曜日に行うと決めておく。
- 外飲みは週1~2回に減らす
今私にとって重要なことは飲みに行くことではなく勉強である。ただし、私は飲みに行くことによりストレス発散にもなるため、合格するまで飲みに行かない、のではなく、週に1~2回に抑える。
《理解を定着させる》
- 仕訳パターンと勘定科目について
一からもう一度テキストを読むのではなく、理解が不十分な箇所を読み込む。そして練習問題や問題集を解き、理解を定着させる。問題集については理解が定着するまで繰り返し行い、正解不正解に関係なく自信を持って回答できなかった問題についてはチェックをつけ、必ず解説を読む。
- 「帳簿」と「決算」について
とにかく理解できていないため、集中的に勉強する。まずはもう一度テキストを読み、1つの項を読むごとにテキストの練習問題を解き、いったん理解する。そして一通りの理解ができたら、問題集を繰り返し解き、解説も読み込み、理解を定着させる。
《試験慣れする》
一通りテキストと問題集を解いた後、実際の試験形式の問題を解いてみる。そして試験の1週間前は実際の試験形式の問題に注力し、当日の試験において時間や出題形式に焦らないよう、試験慣れしておく。また、理解が不十分な箇所については再度テキストと問題集を使用し、理解度を上げていく。
感想
自分の性格が甘ったれていることもあるが、やはり前回のレポートにおいて、レポートの内容がかみ砕けておらず、具体性がなかったため何をしたらよいのか分からず、勉強する意欲すら沸かないことに気付いた。そのためには嫌な結果と冷静に向き合い、そこから原因が判明し、具体的に何を行えばよいのか分かるようになる。今回のレポートを通して、嫌なことと向き合わず逃げている状態では何も前に進まないことを理解でき、そもそもの自分を見つめ直す機会ともなった。自分に自信をつけるためにも、今回こそは絶対合格する。
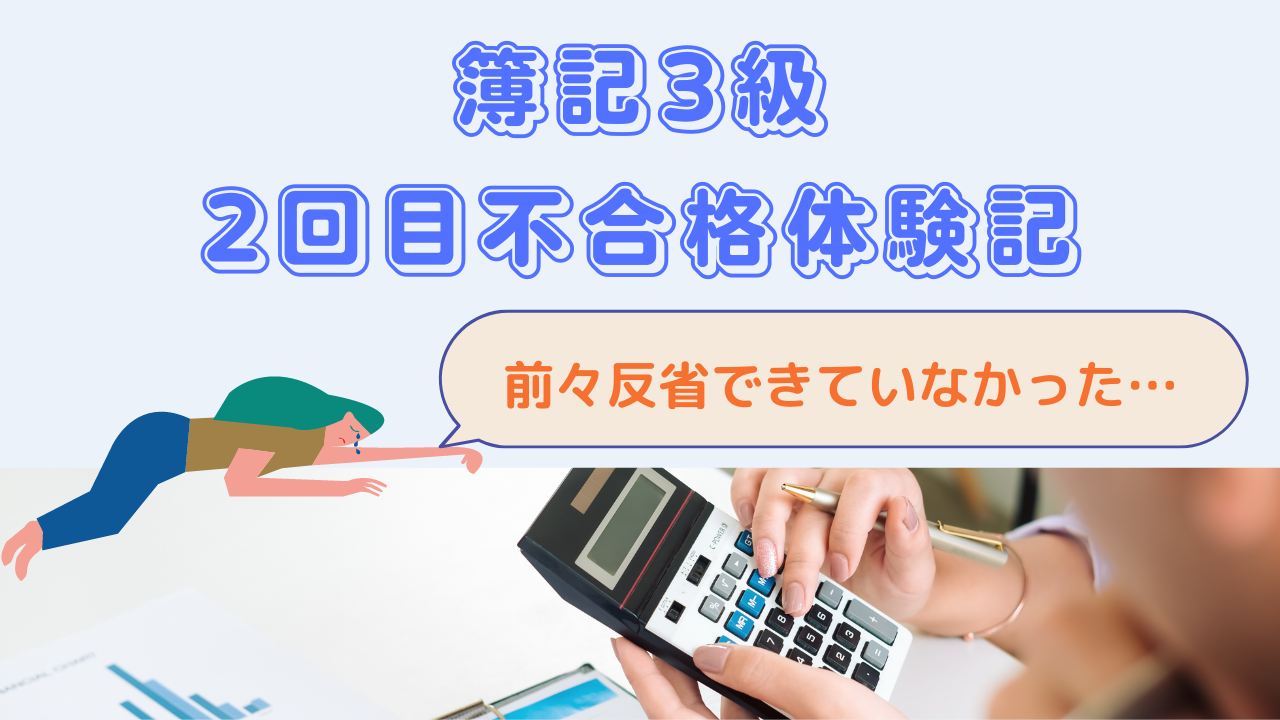


コメント