この記事では、私が簿記2級を受験・合格した際の勉強方法や時間などを紹介したいと思います。一回挫折しながらも何とか合格できましたので、勉強に行き詰っている方やこれから受験を検討されている方の参考になれば幸いです。
簿記2級とは
経理管理に役立つ知識として、企業から最も求められる資格の1つと言われています。
商業簿記・工業簿記を習得し、企業活動や会計実務を踏まえ適切な処理・分析を行うために求められるレベルであり、就職や転職、起業にも役立つとも言われています。
簿記3級と違い、商業簿記に加えて工業簿記が登場します。配点は商業簿記が60点、工業簿記が40点です。特にそれぞれ何点以上取らなくてはいけないということはありませんが、合格ラインの70点を突破するには工業簿記の対策が必須となります。
試験方式
2021年11月現在ではコロナ禍を踏まえ、ネット試験の選択も可能になりました。
私はコロナが流行り始める前に受験したため、まだネット試験は導入されておらず、予め日程が決められている統一試験型での受験でした。
CBT受験が取り入れられたことによって、以前のように年3回のみというよりは少し受けやすくなったのではないでしょうか。
統一型で受ける場合には商工会議所によって申込期限が異なり、いつの間にか最寄りの商工会議所では申込期間が終わっていたというケースもあったため、早めにチェックしてくださいね。

受験のきっかけ

会計学を専攻していたため大学1年の頃から簿記を勉強していたことと、就活での強みにするためには2級以上を取得しなくてはならないと思っていたためです。簿記3級は様々な学生が受験していますが、1級・2級は本格的に勉強しないと取得できない試験のため、しっかり勉強したことの証明にもなります。
私は大学3年から本格的に就活を始めるつもりだったため、2年生のうちには取得しなくてはならないという思いで勉強をしていました。
受験の感想

問1が8/20、問2が14/18、問3が18/20、問4が20/20、問5が20/20で計80/100で合格しました。
カテゴリー別にすると商業簿記が40/60、工業簿記が40/40(満点)です。
私はその前の試験(2019/11)でギリギリ落ちてしまったのですが、そのときも工業簿記は満点で、商業簿記が原因でした。そこで工業簿記は内容を忘れないことだけ意識しつつ、商業簿記を重点的に勉強した結果が出たと思います。
以前の試験では問題用紙を持ち帰れたため、問題用紙に回答を全て書き写し、試験後の速報で自己採点を行いました。試験結果の発表は2週間後でしたが、自己採点で合格を確信していたため特に不安に思うこともありませんでした。
試験対策
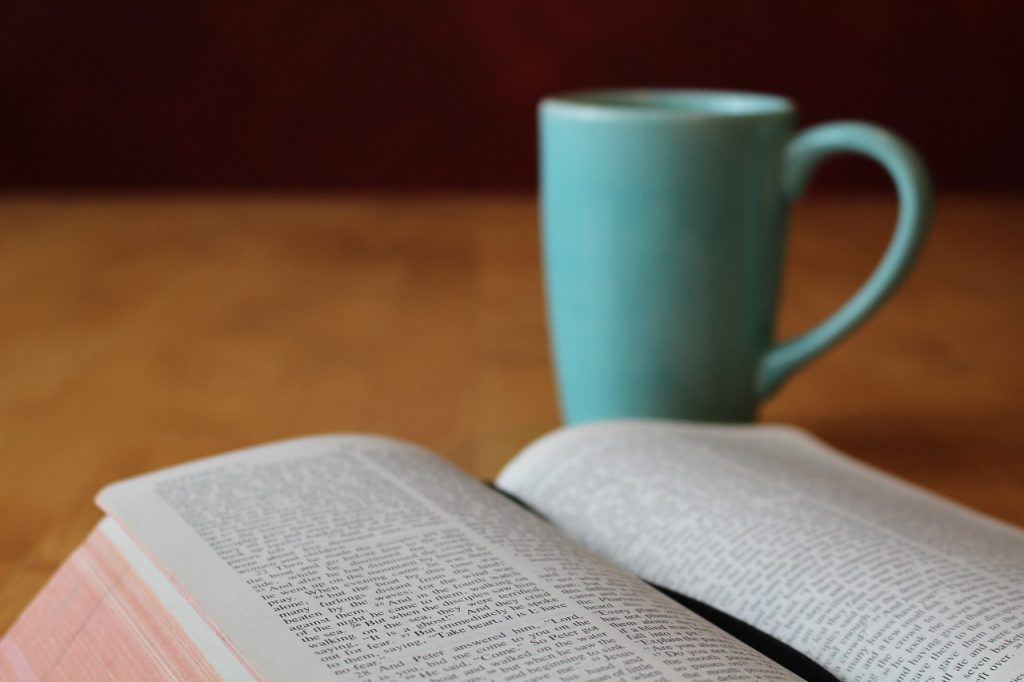
独学or講座
結論は「独学でも十分に受かる」だと思います。
簿記2級取得のためにわざわざどこかのスクールに通う人は周りにいませんでしたが、校内の講座にはかなりの人数が受講していました。
講座にお金をかけることでモチベーションになる方がいれば、私のように自分のペースで勉強を進めたいという方もいらっしゃると思います。やはり自分に合った勉強方法からどちらにするか選択するのが良いと思います。
勉強法
最初はテキスト1冊を読み、残りはすべて過去問や練習問題での勉強を行いました。
これはあくまで試験に受かるための勉強法であり、概念より合格することを重視したやり方です。当時は経理志望でもなかったため、会計知識はそこまで必要にならないと思っていました。しかしSAP業界においてはとても重要となってくる基礎知識なので、もっと概念から理解すべきだったと今になって後悔しています。
過去問は、1周目が「本番のように通しで解き、間違えた部分を復習する」、2周目が「間違えた部分、なんとなく解けた部分だけ解きなおす」、3周目は再度「本番のように解く」、というやり方でした。やり方は自分に合う方法で良いとは思いますが、最低3周やるくらいの気持ちがないと受からないと感じます。
また、過去問の段階で工業簿記の得点率は100%を目指しましょう。
商業簿記の方が難しいため、工業簿記は大きな得点源となります。周りの合格した友人も工業簿記は満点という人が多かったと思います。
勉強時間
途中で挫折したためトータルではおよそ1年かかりましたが、本格的に勉強したのは5ヶ月ほどだと思います。合格した時は試験3週間前から5~7時間は勉強するようにしていました。それ以外は1~3時間程度だったと思います。
3級は正直、直前に詰め込んで何とかなる資格なのですが、2級はそう簡単ではありません。しっかり継続的に勉強を続けるよう頑張りましょう。
実際に使用していた教材

テキスト
★TAC みんなが欲しかった!簿記の教科書 日商2級 滝澤ななみ 著
https://shuppan.tac-school.co.jp/koukou/books/nb2q-mh-tx_s/
※TAC出版のスッキリわかるシリーズを使っている友人も多かったので、そちらもチェックしてみて下さいね。
過去問
★TAC よくわかる簿記シリーズ 合格するための本試験問題集 日商簿記2級
⇒過去問はこれ1択と言っていいほど周りの同級生も使用していました。最低限3周解くことをお勧めします。私の場合はさらに中古屋で古いバージョンの過去問も購入し、出題範囲内の部分に絞って解きました。
予想問題集
★TAC/あてる!直前予想模試 日商簿記2級
https://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/08854/
⇒これも3周して、同じ問題が出たら確実に解けるように復習もしていました。また冒頭にどういった出題傾向かの分析も記載されているので、参考程度にチェックしていました。
★ネットスクール/日商簿記 ズバリ!2級的中 完全予想模試
https://www.amazon.co.jp/第156回日商簿記-ズバリ-2級的中-完全予想模試-ネットスクール/dp/4781042414
⇒TACの予想問題だけでは不安だったのでこちらも3周しました。TACよりは優先順位は低いですが、不安な際は最後の総復習として解いてみるのもいいと思います。
なぜ挫折したのか

3級とのレベルの差を感じたからだと思います。2級の本番試験は捨て問のような難しい問題が出題される回があり、捨て問以外を確実に取れるかという視点で勉強を進めなくてはなりません。もちろんきっちりと勉強されている方には関係のない話かもしれませんが、私にとっては安定した点を取れるまでに物凄く時間がかかり、嫌になってしまった部分が大きかったです。
1回試験に落ちると次の試験まで4か月も空いてしまい、モチベーションが保てなかったというのも大きな理由の1つだったと思います。
結局は就活までに「受からなければならない」という焦りで挫折を乗り越えたのですが、問題が多く解けるようになると楽しさが戻ってきたような気持ちになりました。
簿記の楽しさは貸借対照表や損益計算書の借方・貸方の数字が揃うことにあると思うのですが、それをようやく簿記2級でも感じられるようになったのが大きかったです。そこからは毎日長い時間簿記の勉強を続けられるようになりました。
学生での資格取得のメリット
やはり就活での強みの1つになることだと思います。簿記2級が無敵の資格とまでは言えませんが、3級取得者とはレベルがかなり異なり、企業に対して自信を持って勉強したことを伝えることができます。
ITと会計の親和性が高いことからIT業界での就活でも役立ったため、経理関係志望でなくても勉強しておいて損は全くないと思います。
受験生へアドバイス

簿記2級は3級と同じような勉強量では足りず、圧倒的な演習量不足を感じたことが多々ありました。
ネット試験型の登場により、柔軟な試験スケジュールの組み立てもできるようになりましたが、今でも変化球の問題は出題されているため、まずは基礎の確立を第一の目標とすることをお勧めします。
そしてどこから対策すべきか迷っている人は工業簿記を満点にするまで対策した方が良いと思います。商業簿記より工業簿記の方が圧倒的に得点しやすく、ここで落とすと7割という合格点に達するまでかなり苦労します。過去問の段階で工業簿記が満点近く取れない場合は勉強不足と考えた方がよいレベルです。
そんな2級も解けるようになってくると、次第に楽しく感じてきます。3級と比べて点数が伸びにくく、ニアミスによって不合格になるとやる気がなくなりそうですが、落ち着いて計画的に勉強を頑張ることが大切です!




コメント