はじめに
突然ですが、ハンク・アーロンという伝説のメジャーリーガーをご存知ですか?
彼は1960年代ごろ、まだ人種差別が当たり前だった時代のアメリカで、差別や貧困に負けることなく、野球界の歴史に残る偉業を達成したことで知られています。
幼少期はとても貧しく、ソーダの栓やボロ布で野球の真似事をしていたそうです。
こんな話を聞くと、「努力と才能で貧困や差別に打ち勝った素晴らしい人」という感想を持つ人も多いでしょう。
しかし、政治哲学者のマイケル・サンデル教授は、このような話を美談として扱うことに警鐘を鳴らしています。
努力と才能で不平等を乗り越えたというのは素晴らしいことではあるが、そもそも不平等が存在する状態が問題だからです。
このような、個人の能力が全てであり、それは努力の結果であるという考え方は「メリトクラシー(能力主義)」と呼ばれます。
では、努力と才能を賛美する能力主義にはどのような問題があるのでしょうか。
メリトクラシー(能力主義)
メリトクラシーの誕生
メリトクラシー(能力主義)は、生まれや人種、性別などに関わらず、能力のある者=努力した者が成功するという考え方です。
この考え方は、20世紀半ばのイギリスで生まれました。
その当時のイギリスでは、それまでの貴族の子は貴族、労働者の子は労働者という階級の固定に意義を唱える労働者によって、激しい階級闘争が行われていました。
その階級闘争の中心にいた労働党のブレーン、マイケル・ヤングが小説として出版したのが「メリトクラシーの夜明け(The Rise of the Meritocracy)」です。
メリトクラシーの夜明け(The Rise of the Meritocracy)
この本は当時から80年後の2033年、メリトクラシーがはびこった世界を批判的に描いています。
この世界では、才能と努力で全てが決められます。成功した人は全て自分の努力のおかげだと考え、そうでない人は努力不足だとみなされます。
生まれつきの身分や人種、性別などで差別されない平等な世界だと思われるかもしれませんが、能力を基準とした再配分が行われるだけで、不平等は無くなっていません。
メリトクラシーの正当化と必要性
メリトクラシーは不平等を無くさないと書きましたが、一方で、事実として能力主義は現代社会の基礎となっています。
なぜなら、資本主義経済の中心となる企業活動において、なんらかの評価軸は必須だからです。
そこで、生まれつきで決まってしまう身分や人種、性別などではなく、本人の意思で変える余地のある学歴、経歴、資格などを評価することとなったのです。
また、能力主義はどの階級の人にとっても気持ちのよい考え方です。
成功者は自分の努力を証明することが出来、低い階級の者は努力次第で自分も上に上がれるというモチベーションになります。
機会の平等と結果の不平等
先ほど、学歴、経歴、資格などは本人の意思で変えうると述べました。
では本当にそうなのでしょうか?
努力すれば誰でも成功できるのか
よくスポーツ選手などの成功者は努力について語ります。では、誰しもがハンク・アーロンと同じだけ努力すれば伝説のメジャーリーガーになれるのでしょうか。
また、成功者の中には自身の経験をノウハウという形で売る人もいます。誰しもが成功者のノウハウを真似すれば成功できるのでしょうか。
教育の機会均等は重要なことです。しかし、同じ教育を受ければ誰もが同じ結果を出せるのでしょうか?
そうでないことは想像に容易いでしょう。
つまり、努力の影響が無ではないにしても、運や生まれ持った才能によって、結果は大きく変わるのです。
そもそも、努力する才能というのが遺伝子によって決められるという研究もあります。
文化による努力と成功に対する考え方の違い
余談ですが、努力と成功に関する考え方は文化圏によって差があります。
成功のために必要な要素を尋ねたところ、アメリカでは77%の人が「努力だ」と答えました。一方でフランスでは25%のみで、成功は運や生まれによるものだと考える人も少なくありません。
これにはアメリカにはそもそも階級社会が存在しなかったことが関係していると言われています。
結果、成功は生まれ持ったものでなく、努力次第という考え方が強くなり、成功した上流階級の人々と、貧しい人々の分断が大きくなっています。
また、知的上流階級は生まれつきの差別(人種や性別など)を嫌う一方で、能力の低い人を見下すことに罪悪感を抱いていません。
なぜなら、それは努力の欠如による結果だと考えているからです。
一方、メリトクラシーが比較的弱いヨーロッパでは、結果の不平等があるのだから、成功した人は社会保障の負担や寄付といった形で弱者に還元しようという考え方が一般的です。
このようにメリトクラシーに対する考え方は社会保障制度にも関係しているのです。
結果の平等は実現できるのか
では、結果の平等を実現することは可能なのでしょうか。
結果の平等を目指した世界をディストピア的に描いた小説があります。
そこでは全ての人が平等でいられるよう、ハンディキャップが課されています。
例えば、美しい顔を持つ人は醜い仮面をつけられ、スタイルのいい人はみっともない服を着せられ、体力のある人は常に重しを持たされます。
これでは誰も幸せになっていません。
メリトクラシーとの付き合い方
ここまで、メリトクラシー(能力主義)を批判的に捉えてきましたが、良い悪いはさておき、メリトクラシーは現代社会の基礎となっています。
そのため、影響力を持つ人物になるためには、メリトクラシーの中で上流に位置する必要があります。
そのために、成功者を真似することは無駄ではありません。
しかし、成功したという結果だけを見て、表面を模倣することに意味はありません。
その成功者がどういう人で、何に長けていて、何をどれだけして成功したのかという本質を知った上で、自分に活かす必要があります。
感想
そもそも私は努力すれば誰でも成功できるというようには思っていません。
わかりやすいところで言えば、親の経済的状況は子どもの将来に大きな影響を与えます。
一方で、メリトクラシーの話を聞いて、機会を平等に与えたところで結果は同じにはならないというのは、普段あまり考えていない点でした。
よく考えてみれば当たり前のことなのですが、平等主義を信奉しすぎた結果、機会の平等が全ての問題を解決するような気がしてしまっていました。
機会を平等にしたところで、結果が平等にならないのだから、不平等は無くなりません。
ただし、気になった点としては、メリトクラシーが適材適所という考え方をどう扱うかという点です。
人間には得意不得意があり、一言に「能力」といっても種類があると思います。
マイケル・サンデル教授の本はもちろん、最初にメリトクラシーを提唱した「メリトクラシーの夜明け(The Rise of the Meritocracy)」も読んで、理解を深めてみたいと思いました。
新しいことに挑戦するのが大好き!インターン・資格・留学・英語などの記事を書いています。
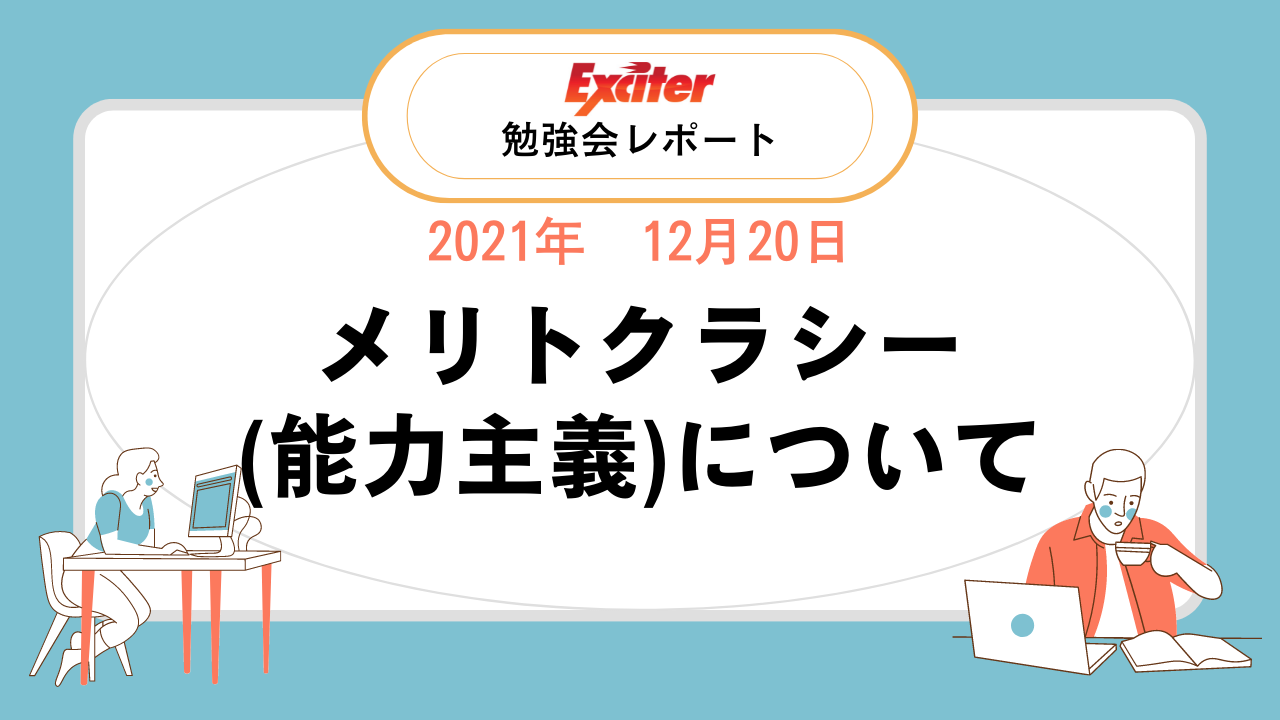

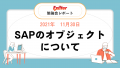
コメント