processである「考える力」とoutputである「書く力」は、仕事において良い評価を得て信頼を得ることだけでなく、頭脳労働者にとって重要なことであるため、日頃からトレーニングをして鍛えなければならない。
ここでは12月23日に行った勉強会の内容について、書く力と考える力を鍛えるための例題を元に、ポイントを交えながら学んだことや感じたことを記載する。
書く力
例題①
「叔父が海外に行く」、「私は父と見送りに行った」、「急いで見送りに行った」
上記の内容を一文で表した時、解釈をする上で誤解の生じないものはどれか。
- 父と私は急いで海外に行く叔父を見送りに行った。
- 父と私は海外に行く叔父を急いで見送りに行った。
- 私は父と海外に行く叔父を急いで見送りに行った。
- 私は父と急いで海外に行く叔父を見送りに行った。
「書く」というoutputにおいて重要なポイントが、「順序性」と「句読点」である。この2つのポイントは文章として相手に何かを伝える場合、いずれの内容にしても誤解の生じない内容を表すために欠かせない重要なポイントであり、文章を作成する上での基礎となる。
順序性
上記の例題①の正解は「2」である。相手に物事を伝える上で、何よりもまず重要なことは「順序性」である。ただし、順序性を生かすためには、文章を構成する語句の内容に過不足や重複がない状態が前提となる。
一見順序性を意識しながら文章で表すことは簡単なように思えるが、文章を作成する自身の主観で表した文章になりがちになってしまうことも多く、客観的な視野で表さなければならない。
単純な短い文章であれば相手にも伝わるかもしれないが、長文になる場合は特に注意しなければならない。
句読点
先述の順序性が不完全な場合、句読点は相手に誤解を生じることなく表すための補助となる。特に長文においては、句読点があることで読みやすく、誤解の生じない文章を表すことができる。
例題①の(1)~(4)において、順序性だけを見ると(2)が正解となるが、句読点を付け足すことでどの回答も誤解のない文章として成立する。
会話で相手にoutputをする際は、話し方やジェスチャーを交えることで誤解を回避できるが、文章においては「書いてあること」そのものでしか伝えることができないため、会話と比較して、伝え方をより意識しなければならない。
相手に誤解のない文章で伝えるということは、伝わらない可能性を極限まで減らさなければならない、ということであり、その要素に「順序性」と「句読点」が含まれる。
また、頭脳労働者として上記以外にも重要なことは、比較や分析ができる文章を書けるようになることである。問題を出される側は、比較や分析をすることで答えを導き出すことができるが、問題を出す側になった場合、比較や分析ができる文章を書くことができなくなる。
頭脳労働者は、相手の理解や納得を得ることが重要であるが、決して容易ではなく、日頃から誤解のない伝え方を意識してoutputしなければならない。
考える力
例題②
偶数と奇数を足すと、どのような答えになるのか。
- 必ず偶数になる
- 必ず奇数になる
- 奇数になることも偶数になることもある
※大学生の正答率33%
問いの答え、理由、所見を述べよ。
上記例題のように、答えは出るものの相手に納得してもらえるような理由が説明しづらい場面は多々あるが、理由が説明できない=本質を理解していない=相手に納得させることができない、ということである。
相手を納得させるための力をつけるには、その都度「なぜ」を考え突き止めることと分析をする、ということが重要なポイントとなる。
「なぜ」の説明
頭脳労働者として「なぜ」を考え突き止めることは何よりも重要なことである。
前述の書く力でも説明した通り、頭脳労働者は相手から理解や納得を得なければならない立場にあるため、明確な根拠を有する内容を伝えなければならない。
例題②のように、自分の考え方で正解は分かっていても、理由が上手く説明できないということは自分の正解の理由も明確でないということである。根拠が曖昧なことは何の説得力も無いため、まずは「なぜ」を抱き根拠を突き止めることが重要である。
「そういうものでしょ?」で終わらせない
上記の「なぜ」の説明にも繋がることであるが、根拠が明確であるから相手に納得してもらえる内容を伝えることができる。根拠もなくただ主観的感覚で「そういうものでしょ」で終わらせてしまうことは、根拠が無いゆえに何も進まず、何の役にも立たない言葉である。
友人との他愛もない会話であれば「そういうものでしょ」で成り立つ場合もあるが、仕事においてはそうはいかない。生産性のある会話をするためにも「そういうものでしょ」で終わらせてはならない。
疑問や疑いをもつこと
例題の回答の選択肢の下に、「大学生の正答率33%」とあるが、答えを導き出す中でこの一文により主観的な思い込みで惑わされてしまうことがある。
しかし、この一文にも分析する点は多くあり、例えばそもそも母数はいくつなのか、どのような人が集めたデータなのか、地域や年齢のターゲットはどこなのか、等を深掘りしなければならない内容が多く含まれる。
見たものを純粋に受け入れるのではなく、その根拠はどこから生じたものなのか突き止めなければならず、根拠に無頓着であってはならない。特に仕事においては、絶対的な正解や結果を持つ数字が重要であるにも関わらず、根拠に無頓着であるということは数字にも無頓着であることに繋がり、生産性が無いと捉えられてしまうだろう。
正解を出すために「考える」ことをするが、正解を導き出す過程において「なぜ」を抱き根拠を突き止めることに加え、突き止める過程においても、情報に惑わされていないか、疑いが無いだけの情報量が揃っているのかを考えることが重要である。
最後に
書くことや考えることについて過去の自身を振り返ると、書くことや考えることについて深く考えることをしてこなかったことを改めて実感した。
相手に何かを伝える際は説得力が必要であるが、主観的な目線で考えることではなく、受け取る側の視野になって伝えなければならない。そのためには十分な情報も必要であるが、まずは伝え方が重要であり、自身は伝え方を鍛えなければならないと感じた。
考えることにおいても、「なぜ」を抱くことが重要であることは分かっているが、与えられた情報に対して純粋に受け取ってしまい、その情報への深堀にまで視野が及んでいないこと、また、及ばないことで十分な情報を得られていないことを感じ、疑問や疑いを持つことを鍛えなければならないと感じた。
現在は資料作成やレポートだけでなく、社内に関する規定やルールおよび文書や表等を作成しているが、十分な情報を得るためにもあらゆる角度からの視野で物事を見ること、また文章や表にする際に相手に伝わりやすいものを作成しなければならない立場にあるため、今回の勉強会の内容を今後の自身の能力に繋げなければならない。
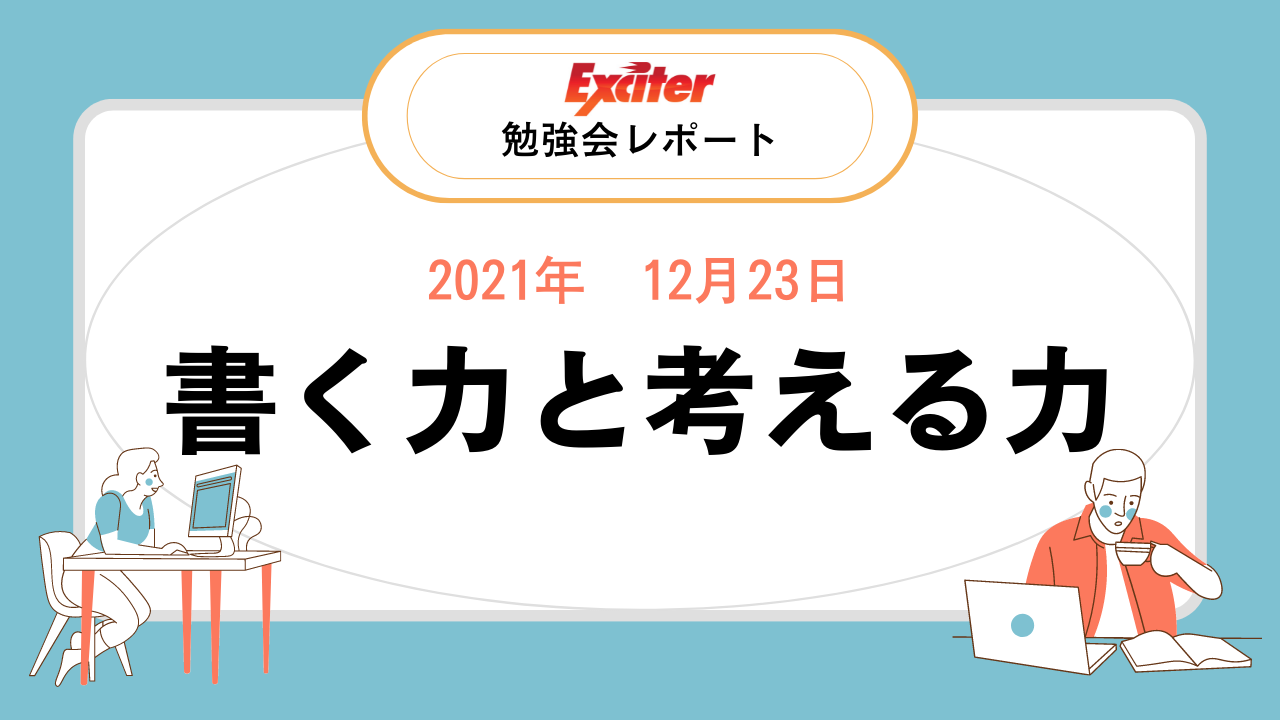
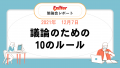
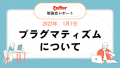
コメント