今回の勉強会では仕事の辞め方について。
仕事を辞めることは悪いことではないが、辞める理由や何を考えるべきかをこのレポートでは扱う。
仕事を辞めるとは
辞めることによる負荷
仕事を辞めることは悪いことではないが、頻繁に変わらない方が良いとされる。
仕事を変えることで様々なものをリセットすることになるからである。
それは技能やキャリア、経験、人間関係、金銭面に対するものである。
技能やキャリア、経験が次の仕事で役に立たない、需要が失われるなど積み上げてきたものを崩すことになるため、継続して利用する方が良い。
人間関係の面では、新しい職場、前職の同僚と二つの問題がある。
新しい場所で人間関係を築くことは自分が気づかないところで心身に負荷がかかってくる。
また前職の同僚と同じ関係でいられることはほぼ稀であるため、それによる負荷も発生する。
金銭面においては仕事を変えたことにより、給料がない月が発生する、今までよりも額が減ってしまうなどの問題は必ず発生するといっても過言ではない。
辞める理由の妥当性
上記のことから仕事を頻繁に変えることは良しとされないが、これらは仕事を辞める理由にもなりえる。
働いていた業界や会社に愛想つかした場合、それまで培った技能やキャリア、経験、人間関係をリセットしても問題ない。
さらに金銭面でも給料が低い場合、結果に見合った給料につながらない場合も辞める理由になりえる。
また自身の境遇や、妊娠・出産などのライフステージの変化が訪れた場合に、それまでと同じように続けることが難しく働くことができないというのは辞める理由として妥当と言える。
辞める理由と感情
辞めると決めたとき、それまで働いていた会社に対して懐かしさや、縁が切れることに対する感情、同僚に対する感謝など様々な感情が浮かぶ可能性が高い。
しかしそのような自分の感情と辞める理由を混同させることはよくないといえる。これも辞める理由として妥当であるとは言えない。
自分の問題と社会の問題
仕事を辞めることで発生する負荷や理由の妥当性について話してきたが、これらには自分の問題と社会の問題が関係する。
自分の問題とは、辞める理由が自分には合ってない、続けていいのかわからないなどの場合である。
これらは現実に向き合わず、次の会社でも少しのことで真正面からぶつからずに逃げてしまう、逃げ癖がついてしまう可能性がある。
社会の問題とは、辞める理由が転職先の人間にどう見られるかということである。
激務による体調不良が理由であれば、転職先の会社の人間は、残業が少なく週休二日であるとすぐ辞めてしまう心配がないと判断する。
この理由が人間関係によるトラブルとなると、同じように辞めてしまうのではないかと不安に思われる可能性が高い。
そのトラブルは内容にもよるが、何か問題が発生するたびにトラブルにつながってしまうことを避けたいと誰もが考えることである。
辞める理由とは、自分自身を納得させるため、社会に対しての説得力を持たせるという二つの観点から重要になる。
引き留めと負うべき責任
辞める理由が妥当であると、次の段階に進むことになるが、辞めたいという意思を伝えた場合、大抵の人間は引き留められることが多い。
それは辞められると困るという理由もあるが、新しい人間を採用し教育して一人前に育てるまでには時間が掛かるという問題もあるからである。
そして引き留めによって仕事を辞めることを撤回する場合は理由が弱いといえる。
よくあるのが給料に関する問題や、在籍期間を延ばしてくれという会社からの要望である。
それに応じるかは辞める側が決めることであるが、これには法的責任と道義的責任という二つの責任が浮かびあがる。
法的責任
そもそも従業員は法によって強く保護されている。
仕事を辞めることを会社に伝えた場合、法律規定により2週間前に通知を行えば問題はない。
従業員が負うべき責任とはこの程度である。
その理由は会社と従業員が入社・退社・契約条件の見直しなどに関しては対等な力関係であるから。
業務などにおいては肩書・キャリア・社会的立場・実力などによって力関係に差があることは当然といえるが、法的責任においては全くの別物であり切り離して考えなければならない。
道義的責任
法的責任と対比する概念に、道義的責任がある。これは法律のようにわかりやすく規定されたものではなく、感情や責任感に訴えかけてくるものであり、どこまでの責任を果たすべきなのか明確な基準が存在しないため扱いづらい問題である。
転職をする場合ある程度の人間はその先の幸せを願って転職する可能性が高いため、辞めるといった時に逆恨みされないために、転職先で不自由にならないために、会社からの要望をある程度は受け入れる必要はあるかもしれないといえる。
法的責任と道義的責任はいわば従業員の権利と義務ともいえる。
前述した通り、従業員が会社に対して負う責任は多くはない。
さらにそれなりの権利を有している。
会社側の要望に応じるかわりに、従業員側から給料や有給に関する条件を提示できるという権利である。
そのため全てに応じる義務は存在せず、従業員側からも提案は可能であり、それに関して負い目を感じる必要はどこにもないといえる。
まとめ
仕事を辞めることは、すべてが悪いわけではない。
これまでよりも幸せになるために仕事を辞め新しい道に行くなど可能性が広がる。辞めるための理由が妥当であるかが重要である。
なんとなくや続ける意味が無いと感じたなど曖昧な理由の場合、社会的に人間性が低いと見られる場合がある。
さらに人間関係のトラブルによるものだと同じ理由で戦線離脱してしまうのではという印象も抱かれやすい。
仕事を続けていると辞めたいと思うことは幾度となく考える人間は必ずいると思う。
そのとき感情任せに行動するのではなく、仕事を辞めるリスクや他人からの評価を見直し、冷静に考えられるような人間になるべきであり、さらに悩みを抱えた時にうまく付き合う方法も自分で知っておくべきだと感じた。
自分自身、転職を経験し考えるべきことや問題は想像していたものよりも多かったこと、自分の考えが浅かったことを認識したため、今回のテーマは今後を考えたとき大いに活かすべき内容であると思う。
それは辞めるためということでなく、自分自身が選んだ場所で続けるために、立ち止まってしまったときに考えるべきことを、今回の内容から自身の考えを改めることが重要であるのではないだろうか。
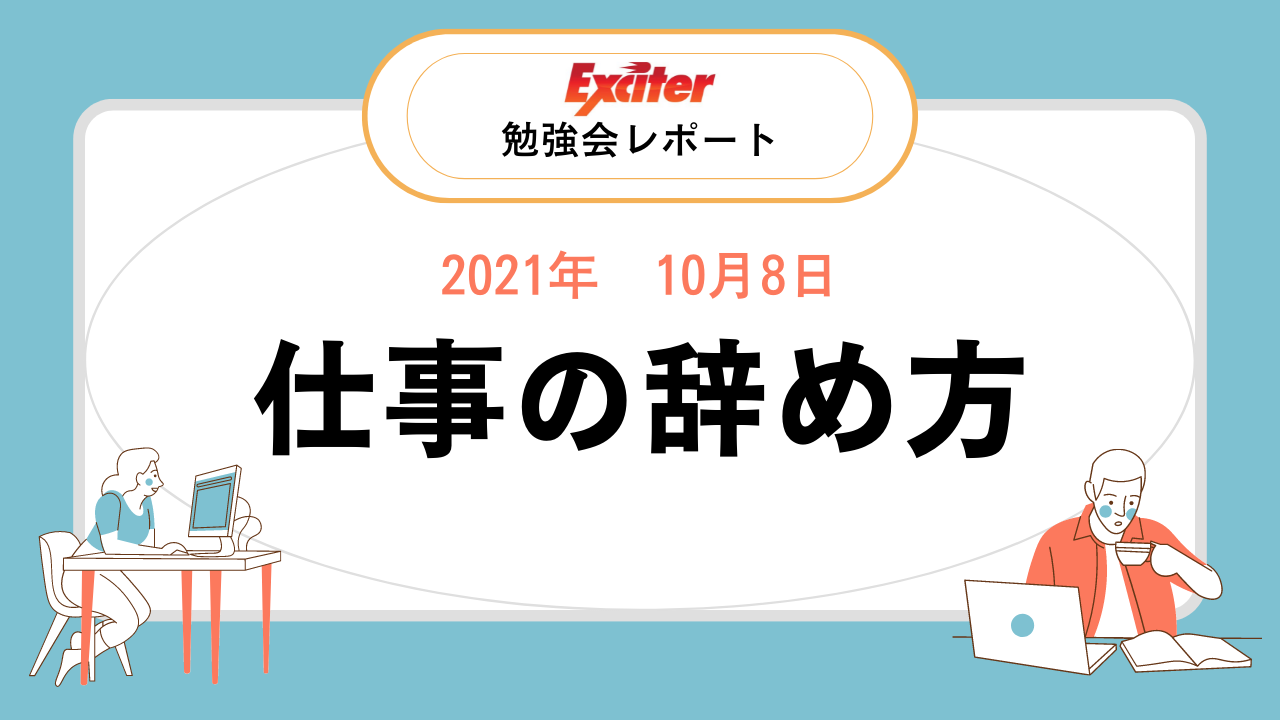
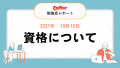
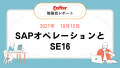
コメント