はじめに
お給料・良い待遇を得るには評価を得なければならない。偶然に良い評価を得られることはなく、得るための過程が存在する。
評価を得るための過程として、知識・経験・技術を磨き、そのために聞く力・見る力・考える力・書く力・伝える力を鍛える。
ではこの評価の中身はどういうものかについてこのレポートでは扱う。
評価とは
評価とは価値を見定めるという意味だが、仕事における評価の中身は「実務的評価」「人間性評価」「将来性評価」「組織的評価」「政治的評価」の5つで構成され、この5つが総合されて評価につながる。
そのため「実務的評価」が高い場合でも、「人間性評価」が低いと判断されてしまうと総合得点は低くなる。
1つ1つの評価ももちろん重要であるが、これらは総合的に見定められるものであり、評価の度合いに優劣は存在しない。
ただし、「実務的評価」はあらゆる評価のベースとなるものであるため、これをなくして良い評価を得ることは難しい。
経験年数による評価
5つの評価の基準は新人・中堅・ベテランと経験年数によって変わる。
新人…「人間性評価」「将来性評価」
新人の場合、実務に関しては評価されるレベルに達していないため、人間性・将来性で判断する。
人間性とは1つ1つこなせる業務を増やす、クオリティを上げられているかなどの最低限の実務をこなすことができるか。それによって将来性の評価につながる。
5年~10年目…「実務的評価」「組織的評価」
中堅の場合、実務はある程度のレベルに達していて当たり前とされる、さらに組織のことを考えられるようになっているかを判断される。
10年目以降…「政治的評価」「組織的評価」
実務的なことはもちろん、組織のために動き貢献しているか、経験で得た繋がりの強さや多さなどで判断される。
繰り返しになるが、5つの評価において「実務的評価」は基本となるものである。
評価方法
評価の中身のほかに、どのように評価されていくのかを理解すること。
「ポジティブ要素が多い」「ネガティブ要素がない」、「加点法」「減点法」と、業種や会社、自身に与えられた立場や業務によって評価方法は異なる。
自身が何によって評価されるかを把握せずに、良い評価を得られるはずがない。
評価を得る目的
評価を得る目的とは、端的には「上に上がるための評価」か「勝つための評価」のいずれか。似
たような部分はあるが、根本的な目的は全く異なり、またそれまでの手段も異なる。
「上に上がるため」というのは自己ベストを出すということ。
「勝つための評価」とはその時に競い合っている誰かに勝つこと。
実力を伸ばし自己ベストの達成を目指すことは大前提だが、「勝つための評価」を得たい場合はアプローチが異なる。
人間性と将来性による評価
5つの評価のなかで「実務的評価」が基本であるが、その評価には「人間性評価」と「将来性評価」が関わってくる。
実務ができないと判断される要素は「見る力」「聞く力」などの人間性がないということだが、客観的に見れば「話をちゃんと聞いていない」や「ちゃんと考えていない」となり、真面目に取り組んでいないと判断されてしまう。
実力を身につけベストを尽くしているという姿勢が見られないと、人間性に問題があるとされ、つまり将来性がないと判断されてしまう。
業務やポジションのステージが上がると、求められるハードルも高くなる。
そのハードルは簡単に乗り越えられるものではないが、求められる実務のレベル上がり、期待されている度合いが増えているということである。
その中で基礎力を身につけ実務に活かし、人間性、さらには将来性につなげることで評価を得ることができる。
まとめ
評価というものに対して、どのような基準で評価され、その時に求められている評価の中身、方法などについて触れてきたが、いかに評価というものに対しての理解が曖昧であるかを痛感した。
仕事において良い評価を得るためには、実務が伴っているだけでは成立しないこと、実務を得るために人間性や将来性が必要であること、経験年数が上がれば経験値とともに組織や政治的なことも実務に関わってくることなど、求められる対象や方法が変わってくることを理解しておくことはとても重要であり、身につけるべき知識であると感じた。
そのためには自己ベストを出し続けることが重要だが、自己満足の頑張りにならないこと、評価のモノサシは自分ではなく評価する人のモノサシで判断されること、評価方法の中で自分に合っているもの・苦手なものを認識し、実力を上げることを注視することが評価を上げることにつながるのではないだろうか。

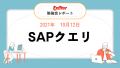

コメント